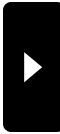2010年12月29日
反省と懺悔します!!
反省と懺悔します!!
「今年は皆さんにとってどんな1年?」などとブログを書きましたが、私自身は総括としては良く頑張った一年でした。
経営にも一生懸命でした。
人のお世話やボランティア、地域活動や経営者団体・・・・・その全てに全力投球した一年でした。
多分、傍目で見たおられた方々や社員、家族にもその事は評価してもらっていると推測します。
あくまでも推測です。
他人の評価はそうではない事もありますから。
それでもいいんです。
これが自己満足っていう奴でしょう。
でもこの一年は、人生の中で「これほどの事あるのか」と思うようなこともありました。
どうして私にこんな苦難を、とか
思い出すたびに悲しく涙をつい流してしまうような出来事が発生してしまいました。
これも人間ならではの事ですので、甘んじて受けなくてはいけませんし、乗り越えなくてはいけない事ですのでむしろ前向きに捕えて日々を送っております。
これも懺悔の一つでしょう。
一つは、健康上の事、
決して不摂生や無理、不養生をしているわけではないのですが、数年に一度襲ってくる七転八倒に悩まされてしまいました。
例年ですと、2,3日で治まる痛みも今回ばかりは約1週間に及ぶ戦いになってしまいました。
日赤病院の救急にタクシーで3回も飛び込む始末です。
救急車は隣近所の皆さんに心配をお掛けするのでどうしても呼べません。
這ってでも・・・・・
会社で倒れましたので社員にも心配を掛けてしまいました。
そんな弱、弱しい姿など社員には見せた事はありませんので、不安を与えたのかもしれませんね。
その分、元気になったら以前にも増して溌剌としていないとね。
これも懺悔ですね。
「悔い改める」事が懺悔ですから、やはり改めないといけません。
『進歩とは反省のきびしさに正比例する。本田宗一郎』
『反省とは悔やむことではない。
前進するための土台である)
「今年は皆さんにとってどんな1年?」などとブログを書きましたが、私自身は総括としては良く頑張った一年でした。
経営にも一生懸命でした。
人のお世話やボランティア、地域活動や経営者団体・・・・・その全てに全力投球した一年でした。
多分、傍目で見たおられた方々や社員、家族にもその事は評価してもらっていると推測します。
あくまでも推測です。
他人の評価はそうではない事もありますから。
それでもいいんです。
これが自己満足っていう奴でしょう。
でもこの一年は、人生の中で「これほどの事あるのか」と思うようなこともありました。
どうして私にこんな苦難を、とか
思い出すたびに悲しく涙をつい流してしまうような出来事が発生してしまいました。
これも人間ならではの事ですので、甘んじて受けなくてはいけませんし、乗り越えなくてはいけない事ですのでむしろ前向きに捕えて日々を送っております。
これも懺悔の一つでしょう。
一つは、健康上の事、
決して不摂生や無理、不養生をしているわけではないのですが、数年に一度襲ってくる七転八倒に悩まされてしまいました。
例年ですと、2,3日で治まる痛みも今回ばかりは約1週間に及ぶ戦いになってしまいました。
日赤病院の救急にタクシーで3回も飛び込む始末です。
救急車は隣近所の皆さんに心配をお掛けするのでどうしても呼べません。
這ってでも・・・・・
会社で倒れましたので社員にも心配を掛けてしまいました。
そんな弱、弱しい姿など社員には見せた事はありませんので、不安を与えたのかもしれませんね。
その分、元気になったら以前にも増して溌剌としていないとね。
これも懺悔ですね。
「悔い改める」事が懺悔ですから、やはり改めないといけません。
『進歩とは反省のきびしさに正比例する。本田宗一郎』
『反省とは悔やむことではない。
前進するための土台である)
Posted by misterkei0918 at
17:07
│Comments(1)
2010年12月29日
今年は皆さんにとってどんな1年?
今年は皆さんにとってどんな1年?
今年のように勉強の機会を積極的に作った1年はありませんでした。
今までの不勉強を反省しての事です。
決して、時間を無駄にしたつもりもありませんし、遊びに費やしたわけでもありません。
それはそれは人並み以上に懸命に走り続けたつもりです。
「良くやった」位の褒め言葉は自分にも差し上げたいとも思っています。
経営の事、ボランティア活動、地域の事、家族の事・・・・・
私の体の動く範囲では、粉骨砕身走ったつもりでした。
それでも忘れている事に気付いたのです。
ただ、身辺の事に夢中になる余り自己投資と言えば大げさですが、自らに勉強を課すことを少し怠っていたような気がします。
決してやっていなかったわけではないのですが。
やはり意識的にしないといけませんね。
元来、頭のいい方ではありませんし、物忘れが良くて理解が遅い方ですので人1倍時間を割かないと駄目な人間です。
その分苦労はしますが、延べ時間や機会を人の倍割けば、ほぼ一緒で人並みと思えば良さそうです。
自分なりに、勉強の成果は確実に上がっているような気もします。
この調子で、ハードスケジュールにはなりますがせいぜい頑張ってみようと思っております。
来年も楽しみな1年にしたいものですね。
『一生勉強 一生青春。相田みつを』
『幸福になりたいのだったら、人を喜ばすことを勉強したまえ。Mプリオール』
『学問なんて、覚えると同時に忘れてしまってもいいものなんだ。
けれども、全部忘れてしまっても、その勉強の訓練の底に一つかみの砂金が残っているものだ。
これだ。これが貴いのだ。勉強しなければいかん。太宰治』
『新しいことを勉強してると世の中は怖くありません。
何もしないで、じっとしているから、怖くなるんです。林家彦六(落語家)』
今年のように勉強の機会を積極的に作った1年はありませんでした。
今までの不勉強を反省しての事です。
決して、時間を無駄にしたつもりもありませんし、遊びに費やしたわけでもありません。
それはそれは人並み以上に懸命に走り続けたつもりです。
「良くやった」位の褒め言葉は自分にも差し上げたいとも思っています。
経営の事、ボランティア活動、地域の事、家族の事・・・・・
私の体の動く範囲では、粉骨砕身走ったつもりでした。
それでも忘れている事に気付いたのです。
ただ、身辺の事に夢中になる余り自己投資と言えば大げさですが、自らに勉強を課すことを少し怠っていたような気がします。
決してやっていなかったわけではないのですが。
やはり意識的にしないといけませんね。
元来、頭のいい方ではありませんし、物忘れが良くて理解が遅い方ですので人1倍時間を割かないと駄目な人間です。
その分苦労はしますが、延べ時間や機会を人の倍割けば、ほぼ一緒で人並みと思えば良さそうです。
自分なりに、勉強の成果は確実に上がっているような気もします。
この調子で、ハードスケジュールにはなりますがせいぜい頑張ってみようと思っております。
来年も楽しみな1年にしたいものですね。
『一生勉強 一生青春。相田みつを』
『幸福になりたいのだったら、人を喜ばすことを勉強したまえ。Mプリオール』
『学問なんて、覚えると同時に忘れてしまってもいいものなんだ。
けれども、全部忘れてしまっても、その勉強の訓練の底に一つかみの砂金が残っているものだ。
これだ。これが貴いのだ。勉強しなければいかん。太宰治』
『新しいことを勉強してると世の中は怖くありません。
何もしないで、じっとしているから、怖くなるんです。林家彦六(落語家)』
Posted by misterkei0918 at
16:32
│Comments(0)
2010年12月29日
今年の貴方の「ありがとう」は何万遍?
今年の貴方の「ありがとう」は何万遍?
今日で私の仕事納めになりました。
でも、福岡にいる限りは必ず会社へ出てくるでしょうが。
毎年、反省ばかりで納得できる一年が過ごせませんがそれでも良いのかもしれませんね。
年の初めには、今年一年の抱負や希望、
年の瀬には、反省と回顧。
ある方から、「ありがとう百万遍」の事を教えていただき、約6年ほど経過したような気がします。
貴方は今年一年で「ありがとう」を何回言われましたか。
確かな計算は出来ませんが、私の大凡はこのようになると思われます。
1、毎日のブログやメールの返信やお礼の中で文章の最初と最後に必ずつけるようにしています。
一日・30返信×前後2=60 60×300日として 18,000遍
2、言葉で発する「ありがとう」
一日100回×300日=30,000遍
合計して 48,000遍
多分これよりも1~2万遍は多くの回数になっているであろうと思います。
百万遍/48,000遍≒21年
あと20年位ですが、多分達成はもう少し早いと思われます。
いつも「すみません」の連発だった私が今では「ありがとう」に置き換えてしまいました。
どうもその方が良さそうです。
色んな不思議な経験をするようにもなりました。
皆さんも試されてみませんか。
来年はよりスピードを上げて、せめて8万遍のペースでいければ、生きている内に100万遍達成という事にもなります。
不思議な現象はいつか機会がありましたら、ブログにも書いてみたいと思います。
「ありがとう」、「ありがとう」・・・これで2回です。
でも、キーボードを叩きながらでも口にしないといけませんよね。
今日で私の仕事納めになりました。
でも、福岡にいる限りは必ず会社へ出てくるでしょうが。
毎年、反省ばかりで納得できる一年が過ごせませんがそれでも良いのかもしれませんね。
年の初めには、今年一年の抱負や希望、
年の瀬には、反省と回顧。
ある方から、「ありがとう百万遍」の事を教えていただき、約6年ほど経過したような気がします。
貴方は今年一年で「ありがとう」を何回言われましたか。
確かな計算は出来ませんが、私の大凡はこのようになると思われます。
1、毎日のブログやメールの返信やお礼の中で文章の最初と最後に必ずつけるようにしています。
一日・30返信×前後2=60 60×300日として 18,000遍
2、言葉で発する「ありがとう」
一日100回×300日=30,000遍
合計して 48,000遍
多分これよりも1~2万遍は多くの回数になっているであろうと思います。
百万遍/48,000遍≒21年
あと20年位ですが、多分達成はもう少し早いと思われます。
いつも「すみません」の連発だった私が今では「ありがとう」に置き換えてしまいました。
どうもその方が良さそうです。
色んな不思議な経験をするようにもなりました。
皆さんも試されてみませんか。
来年はよりスピードを上げて、せめて8万遍のペースでいければ、生きている内に100万遍達成という事にもなります。
不思議な現象はいつか機会がありましたら、ブログにも書いてみたいと思います。
「ありがとう」、「ありがとう」・・・これで2回です。
でも、キーボードを叩きながらでも口にしないといけませんよね。
Posted by misterkei0918 at
16:04
│Comments(0)
2010年12月28日
昨日の「ピーターパン」、今日の「白雪姫」
昨日の「ピーターパンシンドローム」、今日の「白雪姫コンプレックス」
昨日は、12月27日の記念日を調べていましたら、「ピーターパンの日」という事がわかりましたので「ピーターパンシンドローム」の事を調べてブログにしました。
今日は、それと良く対峙して言われる「白雪姫コンプレックス」を調べました。
何かご参考になればと思いますし、私の頭の整理の為に記載いたします。
********************
白雪姫コンプレックス(しらゆきひめコンプレックス)とは、子どもの時に虐待された母親が、今度は自分の娘に対して虐待をしてしまう被虐待児症候群、及びそれに連なる一連の症候のことである。
母親の娘に対する憎悪を意味する概念でもあるが、混同しやすいために白雪姫の母コンプレックスと区別することもある。
白雪姫コンプレックスは、1990年代に出現した用語であるが、白雪姫の母コンプレックスの方は、1980年代半ばでも使用が確認されている。
********************
概論
白雪姫の物語は、継母が娘を殺そうとする物語として知られているが、実はグリム童話初版本では実母となっており、実際には実母ではまずいと言うことで、無理矢理に修正されたものであった。
白雪姫が7歳になったある日、王妃が魔法の鏡に「世界で一番美しい女性は?」と聞くと、白雪姫だという答えが返ってきた。
王妃は怒りのあまり、猟師に白雪姫を森に連れて行くように命令する。
白雪姫は家を追い出され遂には猟師に殺されかけ、肺と肝臓を母親に食べられそうになる。
その後、白雪姫は森の中で7人の小人たちと出会い、暮らすようになる。
しかし、王妃が魔法の鏡に「世界で一番美しいのは?」と聞いたため、白雪姫がまだ生きていることが露見。
王妃は物売りに化けて胸紐を白雪姫に売り、胸紐を締め上げ息を絶えさせる。
最終的に、母親の毒リンゴを食べ意識不明になっていたところを、通りがかった王子が引き取り鑑賞していたが、ある日家臣が背中を叩いたためリンゴが吐き出され白雪姫は起きる。
王妃は、真っ赤に焼けた鉄の靴を履かされ、死ぬまで踊らされた。
********************
この初版を基にして造られた用語が、白雪姫コンプレックスである。
このコンプレックスは、実母や保護されずに育ったために復讐の意味合いをこめ、全く関係ない自分の子供に虐待を加えてしまう状況を作り出すとされる。
また、このコンプレックスはその経緯のため、世代を越えて連鎖していくとされる。
登場した1990年代半ばは、母親の容姿に関することが主題とされたが、近年[いつ?]は性的虐待に関する話も多くなっている。
********************
昨日は、12月27日の記念日を調べていましたら、「ピーターパンの日」という事がわかりましたので「ピーターパンシンドローム」の事を調べてブログにしました。
今日は、それと良く対峙して言われる「白雪姫コンプレックス」を調べました。
何かご参考になればと思いますし、私の頭の整理の為に記載いたします。
********************
白雪姫コンプレックス(しらゆきひめコンプレックス)とは、子どもの時に虐待された母親が、今度は自分の娘に対して虐待をしてしまう被虐待児症候群、及びそれに連なる一連の症候のことである。
母親の娘に対する憎悪を意味する概念でもあるが、混同しやすいために白雪姫の母コンプレックスと区別することもある。
白雪姫コンプレックスは、1990年代に出現した用語であるが、白雪姫の母コンプレックスの方は、1980年代半ばでも使用が確認されている。
********************
概論
白雪姫の物語は、継母が娘を殺そうとする物語として知られているが、実はグリム童話初版本では実母となっており、実際には実母ではまずいと言うことで、無理矢理に修正されたものであった。
白雪姫が7歳になったある日、王妃が魔法の鏡に「世界で一番美しい女性は?」と聞くと、白雪姫だという答えが返ってきた。
王妃は怒りのあまり、猟師に白雪姫を森に連れて行くように命令する。
白雪姫は家を追い出され遂には猟師に殺されかけ、肺と肝臓を母親に食べられそうになる。
その後、白雪姫は森の中で7人の小人たちと出会い、暮らすようになる。
しかし、王妃が魔法の鏡に「世界で一番美しいのは?」と聞いたため、白雪姫がまだ生きていることが露見。
王妃は物売りに化けて胸紐を白雪姫に売り、胸紐を締め上げ息を絶えさせる。
最終的に、母親の毒リンゴを食べ意識不明になっていたところを、通りがかった王子が引き取り鑑賞していたが、ある日家臣が背中を叩いたためリンゴが吐き出され白雪姫は起きる。
王妃は、真っ赤に焼けた鉄の靴を履かされ、死ぬまで踊らされた。
********************
この初版を基にして造られた用語が、白雪姫コンプレックスである。
このコンプレックスは、実母や保護されずに育ったために復讐の意味合いをこめ、全く関係ない自分の子供に虐待を加えてしまう状況を作り出すとされる。
また、このコンプレックスはその経緯のため、世代を越えて連鎖していくとされる。
登場した1990年代半ばは、母親の容姿に関することが主題とされたが、近年[いつ?]は性的虐待に関する話も多くなっている。
********************
Posted by misterkei0918 at
00:30
│Comments(0)
2010年12月28日
エレファントシンドローム?
エレファントシンドローム?
私どもの日常の中でこのような事はないでしょうか。
「エレファントシンドローム」という言葉を以前教えていただきました。
もうすっかり忘れていたのですが、最近送り届けていただいたメルマガで再びしらべてみることのしたのです。
『目標達成出来ない人の多くが、「学習性無力感」になっているということでした。
「学習性無力感」とは心理学者のマーティン・セリグマンが提唱した説。(自己啓発用語で言うと、エレファントシンドロームですね)』
繰り返し繰り返し経験する事、虐げられることで無力化してしまう。
学習した事を当然としてしまうという事ですね。
与えられた現状にいつの間にか馴染んでしまう。
刷り込まれる、洗脳されるといってもいいのでしょうね。
では、エレファントシンドロームとは?
『子どもの像を大きな木に鎖で繋いでおく⇒どんなに暴れても逃げられないとわかる⇒大人になっても逃げられないと思う(実際は簡単に逃げられるのに)⇒逃げたいとも思わなくなる。
⇒知らず知らずに心に蓄積してしまった「自分自身の能力に限界を持つこと」=エレファントシンドローム』
と教えてくれています。
犬の実験もありますよね。
犬を拘束して、電気デンキショックを与え続けたら、最初は怖がっていたのに後には怖がりながらも甘んじて電気ショックを受けようとする。
私どもにもそのような事がありはしないでしょうか。
物事を最初から諦めている、
行動を起こすこと自体を最初から拒否、
出来そうな気はするけど、なぜか一歩が出ない、
つい尻込みをする・・・・・
人間は、動物と違う側面を持っており、自分自身を修正、修復、想像する力を持っていますから、全てその事に拘束される事はありませんが、自分を変えようとする力さえも起きてこない人にとっては悲劇です。
また、中には変えなくてもいいと思っている人や決して変えたくないという人もいるでしょうから悲劇というのも言い過ぎかもしれませんが。
でも、人間としての可能性や創造性を否定された状態で日常を送るのも嫌なものです。
出来れば自分の力の限りを尽くして一生を全うしたいと思います。
このように考えますと、親の教育、学校、社会、国・・・・・
しっかりしないといけませんよね。
駄目な親、つまらない学校、無気力な社会、無能な政治や堕落した国・・・・・
どれをとっても一個人にも大きな打撃です。
或いはそれを逆手にとって、行動する親や学校、社会、国が存在するとしたらこれは大変なことです。
「エレファントシンドローム」
改めて、考えさせられました。
私どもの日常の中でこのような事はないでしょうか。
「エレファントシンドローム」という言葉を以前教えていただきました。
もうすっかり忘れていたのですが、最近送り届けていただいたメルマガで再びしらべてみることのしたのです。
『目標達成出来ない人の多くが、「学習性無力感」になっているということでした。
「学習性無力感」とは心理学者のマーティン・セリグマンが提唱した説。(自己啓発用語で言うと、エレファントシンドロームですね)』
繰り返し繰り返し経験する事、虐げられることで無力化してしまう。
学習した事を当然としてしまうという事ですね。
与えられた現状にいつの間にか馴染んでしまう。
刷り込まれる、洗脳されるといってもいいのでしょうね。
では、エレファントシンドロームとは?
『子どもの像を大きな木に鎖で繋いでおく⇒どんなに暴れても逃げられないとわかる⇒大人になっても逃げられないと思う(実際は簡単に逃げられるのに)⇒逃げたいとも思わなくなる。
⇒知らず知らずに心に蓄積してしまった「自分自身の能力に限界を持つこと」=エレファントシンドローム』
と教えてくれています。
犬の実験もありますよね。
犬を拘束して、電気デンキショックを与え続けたら、最初は怖がっていたのに後には怖がりながらも甘んじて電気ショックを受けようとする。
私どもにもそのような事がありはしないでしょうか。
物事を最初から諦めている、
行動を起こすこと自体を最初から拒否、
出来そうな気はするけど、なぜか一歩が出ない、
つい尻込みをする・・・・・
人間は、動物と違う側面を持っており、自分自身を修正、修復、想像する力を持っていますから、全てその事に拘束される事はありませんが、自分を変えようとする力さえも起きてこない人にとっては悲劇です。
また、中には変えなくてもいいと思っている人や決して変えたくないという人もいるでしょうから悲劇というのも言い過ぎかもしれませんが。
でも、人間としての可能性や創造性を否定された状態で日常を送るのも嫌なものです。
出来れば自分の力の限りを尽くして一生を全うしたいと思います。
このように考えますと、親の教育、学校、社会、国・・・・・
しっかりしないといけませんよね。
駄目な親、つまらない学校、無気力な社会、無能な政治や堕落した国・・・・・
どれをとっても一個人にも大きな打撃です。
或いはそれを逆手にとって、行動する親や学校、社会、国が存在するとしたらこれは大変なことです。
「エレファントシンドローム」
改めて、考えさせられました。
Posted by misterkei0918 at
00:23
│Comments(0)
2010年12月27日
今日はピーターパンの日。「ピーターパンシンドローム」考察
今日はピーターパンの日。「ピーターパンシンドローム」考察
今日はピーターパンの日。昔、PTA活動をしていた時に良く耳にしていた言葉です。
私の事の様な気がしますし、今の子供達のような気もします。
調べてみました。
********************
ピーターパンの日・1904年のこの日、イギリスの劇作家ジェームス・バリーの童話劇『ピーターパン』がロンドンで初演されたことに由来。
ピーターパンシンドロームとは、1983年にアメリカの心理学者、ダン・カイリー博士の著した『ピーターパン症候群』(原題:Peter Pan Syndrome)で提唱された精神疾患としての概念。
********************
1、 心理学的アプローチ
ピーターパン症候群患者の心理学的なアプローチとしては、言動が「子供っぽい」という代表的な特徴をはじめ、精神的・社会的・性的な部分にリンクして問題を引き起こし易いという事が挙げられている。過去に解析されてきた事象のほとんどでその症状に陥ったと思われる人物が「男性」であるという点もこの症候群が単性にのみ訪れるという特色を示している。
「ピーターパン」は人間的に未熟でナルシズムに走る傾向を持っており、『自己中心的』・『無責任』・『反抗的』・『依存的』・『怒り易い』・『ずる賢い』というまさに子供同等の水準に意識が停滞してしまう大人を指す。ゆえにその人物の価値観は「大人」の見識が支配する世間一般の常識や法律を蔑ろにしてしまうこともあり、社会生活への適応は困難になり易く必然的に孤立してしまうことが多い。また「ピーターパン」は年齢的には大人の男性である「少年」で、母親に甘えている時や甘えたいと欲している時に、母性の必要を演じる傾向も持ち合わせている。(所謂幼児回帰の要素も含んでいる)
これらの症状に陥る条件としては、近親者による過保護への依存、マザーコンプレックスの延長、幼少期に受けた苛めもしくは虐待による過度なストレス、社会的な束縛感・孤立感・劣等感からの逃避願望、物理的なものでは脳の成長障害なども関係しているのではないかと諸説が唱えられているものの、現段階での学識的な因果関係としてはあくまで推測の域である。
********************
2、性感覚における特徴
カイリー博士の提起から受け継がれた各国の心理専門家によって、さらにその症状や特徴は詳細に分析されてきている。特に注目すべき点として、その症候群を患った男性は一般の男性とは一線を画す「性感覚」を持ち合わせる傾向があるという点である。自分を幼少期という幻想に位置付ける傾向にあるため、異性、つまりは女性との対話を不得手とするケースがほとんどである。大人の人間として現実的な将来への展望、ひいては人生の構想諸々への意識が著しく欠如しているため、相手に対して釣り合いがとれるだけの話題を共有することができないというのがその原因と推測される。
その反面で想像内での理想的な女性像というものは強烈なまでに描かれており、そのほとんどが母性を持ち合わせた「母親像」またはカイリー博士によっても触れられている「ウェンディ」のような女性像を理想としている場合がほとんどであるという。
上記のような結果、現実的に恋愛などによって女性と交わることは基より、結婚によって家庭を築いていくということも困難な境遇に陥り易い。可能性があるとすれば、積極的なリードができ、なおかつ相当な放任主義者の女性に限られてくるであろう。
またこの手の症状は小説をはじめとする各著書でも取り上げられることもあり、世間認識を逸脱した異型の男女関係を画くひとつのセオリーとしてピックアップされることもある。
********************
女の子の「白雪姫コンプレックス」については次に!!
今日はピーターパンの日。昔、PTA活動をしていた時に良く耳にしていた言葉です。
私の事の様な気がしますし、今の子供達のような気もします。
調べてみました。
********************
ピーターパンの日・1904年のこの日、イギリスの劇作家ジェームス・バリーの童話劇『ピーターパン』がロンドンで初演されたことに由来。
ピーターパンシンドロームとは、1983年にアメリカの心理学者、ダン・カイリー博士の著した『ピーターパン症候群』(原題:Peter Pan Syndrome)で提唱された精神疾患としての概念。
********************
1、 心理学的アプローチ
ピーターパン症候群患者の心理学的なアプローチとしては、言動が「子供っぽい」という代表的な特徴をはじめ、精神的・社会的・性的な部分にリンクして問題を引き起こし易いという事が挙げられている。過去に解析されてきた事象のほとんどでその症状に陥ったと思われる人物が「男性」であるという点もこの症候群が単性にのみ訪れるという特色を示している。
「ピーターパン」は人間的に未熟でナルシズムに走る傾向を持っており、『自己中心的』・『無責任』・『反抗的』・『依存的』・『怒り易い』・『ずる賢い』というまさに子供同等の水準に意識が停滞してしまう大人を指す。ゆえにその人物の価値観は「大人」の見識が支配する世間一般の常識や法律を蔑ろにしてしまうこともあり、社会生活への適応は困難になり易く必然的に孤立してしまうことが多い。また「ピーターパン」は年齢的には大人の男性である「少年」で、母親に甘えている時や甘えたいと欲している時に、母性の必要を演じる傾向も持ち合わせている。(所謂幼児回帰の要素も含んでいる)
これらの症状に陥る条件としては、近親者による過保護への依存、マザーコンプレックスの延長、幼少期に受けた苛めもしくは虐待による過度なストレス、社会的な束縛感・孤立感・劣等感からの逃避願望、物理的なものでは脳の成長障害なども関係しているのではないかと諸説が唱えられているものの、現段階での学識的な因果関係としてはあくまで推測の域である。
********************
2、性感覚における特徴
カイリー博士の提起から受け継がれた各国の心理専門家によって、さらにその症状や特徴は詳細に分析されてきている。特に注目すべき点として、その症候群を患った男性は一般の男性とは一線を画す「性感覚」を持ち合わせる傾向があるという点である。自分を幼少期という幻想に位置付ける傾向にあるため、異性、つまりは女性との対話を不得手とするケースがほとんどである。大人の人間として現実的な将来への展望、ひいては人生の構想諸々への意識が著しく欠如しているため、相手に対して釣り合いがとれるだけの話題を共有することができないというのがその原因と推測される。
その反面で想像内での理想的な女性像というものは強烈なまでに描かれており、そのほとんどが母性を持ち合わせた「母親像」またはカイリー博士によっても触れられている「ウェンディ」のような女性像を理想としている場合がほとんどであるという。
上記のような結果、現実的に恋愛などによって女性と交わることは基より、結婚によって家庭を築いていくということも困難な境遇に陥り易い。可能性があるとすれば、積極的なリードができ、なおかつ相当な放任主義者の女性に限られてくるであろう。
またこの手の症状は小説をはじめとする各著書でも取り上げられることもあり、世間認識を逸脱した異型の男女関係を画くひとつのセオリーとしてピックアップされることもある。
********************
女の子の「白雪姫コンプレックス」については次に!!
Posted by misterkei0918 at
10:21
│Comments(0)
2010年12月25日
過去肯定から始めた方が良さそう
過去肯定から始めた方が良さそう
自分の過去は出来れば忘れ去りたいと思う人が大半ではないでしょうか。
人は、苦労した過去や悲しかった出来事は何故かしら脳裏から離れないものです。
逆に楽しかった事や幸せだった事はつい心の片隅に追いやられ、思い出すのもなかなかないものです。
所が振り返ってみると苦難の時代や時期こそ、実は貴重であって、その時をどのようにして乗り切ってきたかが今の自分を決定づけているような気がします。
当然「あの時は幸せだった」などと懐古する事もありますが、どうも生産的ではなかったし危機感は当然存在しません。
反対に貧しかった時、苦しかった時、さまざまなものに反目していた時代は、いつか来るべき時代の為に頑張ることを旨としていたようですし、気持が入っていたものです。
そんな時代こそ、時々は振り返り大事にすることが必要と思われます。
例え今が幸せとしても、その時のことを常に念頭に置くことによって戒めにもなりますし反省の大いなる材料にもなります。
また、新たな飛躍に向って努力する原動力にもなるものです。
自らの困難な過去ただの遺産として葬るのではなく、これからの糧にこそすべきなのでしょうね。
であれば、それこそ苦難の過去を経験している人間こそこれからを有利に進める事が出来るというものです。
凄惨な過去を自慢こそすれ、卑屈になる材料でもありませんし、それがために気後れなど決してしてはなりません。
勇気を持って、英知を兼ね備えて、それに過去の経験をプラスすれば「鬼に金棒」
それこそ明日からが楽しみという所でしょう。
『どんなに悔いても過去は変わらない。
どれほど心配したところで未来もどうなるものでもない。
いま、現在に最善を尽くすことである。松下幸之助』
『私の現在が成功というのなら、
私の過去はみんな失敗が土台づくりをしていることにある。
仕事は全部失敗の連続である。本田宗一郎』
自分の過去は出来れば忘れ去りたいと思う人が大半ではないでしょうか。
人は、苦労した過去や悲しかった出来事は何故かしら脳裏から離れないものです。
逆に楽しかった事や幸せだった事はつい心の片隅に追いやられ、思い出すのもなかなかないものです。
所が振り返ってみると苦難の時代や時期こそ、実は貴重であって、その時をどのようにして乗り切ってきたかが今の自分を決定づけているような気がします。
当然「あの時は幸せだった」などと懐古する事もありますが、どうも生産的ではなかったし危機感は当然存在しません。
反対に貧しかった時、苦しかった時、さまざまなものに反目していた時代は、いつか来るべき時代の為に頑張ることを旨としていたようですし、気持が入っていたものです。
そんな時代こそ、時々は振り返り大事にすることが必要と思われます。
例え今が幸せとしても、その時のことを常に念頭に置くことによって戒めにもなりますし反省の大いなる材料にもなります。
また、新たな飛躍に向って努力する原動力にもなるものです。
自らの困難な過去ただの遺産として葬るのではなく、これからの糧にこそすべきなのでしょうね。
であれば、それこそ苦難の過去を経験している人間こそこれからを有利に進める事が出来るというものです。
凄惨な過去を自慢こそすれ、卑屈になる材料でもありませんし、それがために気後れなど決してしてはなりません。
勇気を持って、英知を兼ね備えて、それに過去の経験をプラスすれば「鬼に金棒」
それこそ明日からが楽しみという所でしょう。
『どんなに悔いても過去は変わらない。
どれほど心配したところで未来もどうなるものでもない。
いま、現在に最善を尽くすことである。松下幸之助』
『私の現在が成功というのなら、
私の過去はみんな失敗が土台づくりをしていることにある。
仕事は全部失敗の連続である。本田宗一郎』
Posted by misterkei0918 at
23:42
│Comments(0)
2010年12月25日
「愛されている事を忘れないで!!」
「愛されている事を忘れないで!!」
人は愛されていることを意識すること、確認できる事で、逞しくもなり勇気を奮い立たせることもできるものです。
逆に、人は愛されていない事を意識し、確認できると生きる希望を失い、自暴自棄の世界へと落ち込んでしまうものです。
愛を語る事は、恋を語るよりも困難なことであり、その深遠さは語る事の難しさが象徴的に示しています。
ラジオだったと思いますが、
作詞家・星野哲郎さん、
「男はつらいよ」「なみだ船」「アンコ椿は恋の花」「三百六十五歩のマーチ」「兄弟船」など、名曲の数々を手がけた山口県大島郡周防大島町出身で名誉町民ですが、ご自分の記念館へ訪れた時に、
「子供たちへのメッセージを」と求められて暫し考えた後に
「愛されている事を忘れないで!!」と答えられたとお聞きします。
とりわけ、子供達は愛を自ら語る事はありませんが、彼らが発する信号、つまり言葉や行動、表情は見事に愛情表現であって、しかも無垢なものであります。
一方の親や兄弟、周囲の人々から無償の愛を受け取る事が出来る子供と、逆に親愛の情から取り残されたり、真逆の行動を与えられる子供がいる事はまさしく社会の責任であり親の責任であります。
悲しいかな、人はそれぞれに与えられた境涯が存在し、決して一様なものではないものです。
また、考えてみますと愛情の限りを尽くされた子供が幸せな生涯であるのかと問われれば、決してそうでもない事に気付きます。
波乱万丈な子供時代を経験した人が、その後も不幸な生涯に終始するわけでもありません。
これは私の個人的な思いですが、
愛情にまみれた子供であっても、愛情過多、溺愛がどれだけ不幸な道を歩ませることになるのか、
不幸な育ち方を経験し、屈折した心やコンプレックスにまみれていても上手に世渡りをする人もいるものです。
人は「適度な」愛情に育まれ、時には叱咤を受け、葛藤も経験しながら育つ方が良さそうです。
基本的に人を愛する事、人から愛されている実感を忘れる事のない育ち方が根本ではありますよね。
また、人は愛されていることにのみ執着する事もいけませんし、愛することにのみ神経が走り相手の立場に配慮が行き届かないのも大いに困りものです。
『愛にあふれた人は、愛にあふれた世界に住みます。
敵対的な人は、敵対的な世界に住みます。
あなたが出会う人は、あなたの鏡です。ケンケイエスジュニア』
『どんなにその人を愛していても、その人のためにすべてを犠牲にしてはならない。
なぜなら、必ず後で、その人を憎むようになるからだ。曾野綾子』
『たいていの人は愛の問題を、「愛する」という問題、愛する能力の問題としてではなく、「愛される」という問題として捉えている。
つまり、人びとにとって重要なのは、どうすれば愛されるか、どうすれば愛される人間になれるか、ということなのだ。エーリッヒフロム「愛するということ」』
『人間の生活の苦しみは、愛の表現の困難に尽きるといってよいと思う。
この表現のつたなさが、人間の不幸の源泉なのではあるまいか。太宰治』
『愛は人生に没我を教える。それ故に愛は人間を苦しみから救う。トルストイ』
『愛にあふれた人は、愛にあふれた世界に住みます。
敵対的な人は、敵対的な世界に住みます。
あなたが出会う人は、あなたの鏡です。ケンケイエスジュニア』
人は愛されていることを意識すること、確認できる事で、逞しくもなり勇気を奮い立たせることもできるものです。
逆に、人は愛されていない事を意識し、確認できると生きる希望を失い、自暴自棄の世界へと落ち込んでしまうものです。
愛を語る事は、恋を語るよりも困難なことであり、その深遠さは語る事の難しさが象徴的に示しています。
ラジオだったと思いますが、
作詞家・星野哲郎さん、
「男はつらいよ」「なみだ船」「アンコ椿は恋の花」「三百六十五歩のマーチ」「兄弟船」など、名曲の数々を手がけた山口県大島郡周防大島町出身で名誉町民ですが、ご自分の記念館へ訪れた時に、
「子供たちへのメッセージを」と求められて暫し考えた後に
「愛されている事を忘れないで!!」と答えられたとお聞きします。
とりわけ、子供達は愛を自ら語る事はありませんが、彼らが発する信号、つまり言葉や行動、表情は見事に愛情表現であって、しかも無垢なものであります。
一方の親や兄弟、周囲の人々から無償の愛を受け取る事が出来る子供と、逆に親愛の情から取り残されたり、真逆の行動を与えられる子供がいる事はまさしく社会の責任であり親の責任であります。
悲しいかな、人はそれぞれに与えられた境涯が存在し、決して一様なものではないものです。
また、考えてみますと愛情の限りを尽くされた子供が幸せな生涯であるのかと問われれば、決してそうでもない事に気付きます。
波乱万丈な子供時代を経験した人が、その後も不幸な生涯に終始するわけでもありません。
これは私の個人的な思いですが、
愛情にまみれた子供であっても、愛情過多、溺愛がどれだけ不幸な道を歩ませることになるのか、
不幸な育ち方を経験し、屈折した心やコンプレックスにまみれていても上手に世渡りをする人もいるものです。
人は「適度な」愛情に育まれ、時には叱咤を受け、葛藤も経験しながら育つ方が良さそうです。
基本的に人を愛する事、人から愛されている実感を忘れる事のない育ち方が根本ではありますよね。
また、人は愛されていることにのみ執着する事もいけませんし、愛することにのみ神経が走り相手の立場に配慮が行き届かないのも大いに困りものです。
『愛にあふれた人は、愛にあふれた世界に住みます。
敵対的な人は、敵対的な世界に住みます。
あなたが出会う人は、あなたの鏡です。ケンケイエスジュニア』
『どんなにその人を愛していても、その人のためにすべてを犠牲にしてはならない。
なぜなら、必ず後で、その人を憎むようになるからだ。曾野綾子』
『たいていの人は愛の問題を、「愛する」という問題、愛する能力の問題としてではなく、「愛される」という問題として捉えている。
つまり、人びとにとって重要なのは、どうすれば愛されるか、どうすれば愛される人間になれるか、ということなのだ。エーリッヒフロム「愛するということ」』
『人間の生活の苦しみは、愛の表現の困難に尽きるといってよいと思う。
この表現のつたなさが、人間の不幸の源泉なのではあるまいか。太宰治』
『愛は人生に没我を教える。それ故に愛は人間を苦しみから救う。トルストイ』
『愛にあふれた人は、愛にあふれた世界に住みます。
敵対的な人は、敵対的な世界に住みます。
あなたが出会う人は、あなたの鏡です。ケンケイエスジュニア』
Posted by misterkei0918 at
20:09
│Comments(0)
2010年12月24日
出会い・・・その人の能力、レベル以上の出会いはない
出会い・・・その人の能力、レベル以上の出会いはない
聞いた途端に、何かおかしい発言?と思いました。
差別的とか、出会いにそんな筈はないだとか。
ただ聞くだけではそんな気がしますよね。
所が、よくよく考えてみると確かに世の中はそんなところがあります。
例えば、大企業の社長に会える、
オーバーに言えば総理大臣に会える、
大都市の首長に会える、例えば東京都知事や大阪府知事
商工会議所の会頭、銀行の頭取
身近では、学校の校長に親しく会える
トップクラスの俳優や歌手に会える
・
・
そんな方に偶然に遭ったとか、すれ違ったなどは良くあることです。
空港でたまたま見かけたとか。
そうではなく、親しく会える、会話が交わせる、談笑ができる・・・・・
となるとなかなか機会が作れるものではありません。
社会的地位や経済的立場、年齢・・・などによって初めて実現できるものであってそんなに簡単に機会を持てるものでもありません。
そういうことから考えると確かに、
「出会い・・・その人の能力、レベル以上の出会いはない」という言葉も確かさを感じさせてくるものです。
であれば、やはりそういうレベルの方々と肩を並べることは無理にしても何らかの会える機会を作る事は何とかできそうな気がしないでもありません。
自分の能力、スキル、レベルを上げることができるとすればそのレベル程度の人々に会う機会は作れるということになります。
不思議なもので、そのレベルの方々に接しているうちにあと一段のレベルにも到達するチャンスがあるものです。
やはり意識する事なのではないでしょうかね。
継続艇努力によって、自らが成長しようとする事が大事だと思われます。
その事が、自分の人間性を高め、品性を磨き、それなりの素養の拡大に寄与していくものです。
日ごろから、自分を高める意識を持っている事が大事なようですね。
『生涯出会い、生涯夢、生涯感動、それが私の人生訓。上海貿易発展局顧問、筒井修』
『人生とは出会いであり、その招待は二度と繰り返されることはない。カロッサ』
聞いた途端に、何かおかしい発言?と思いました。
差別的とか、出会いにそんな筈はないだとか。
ただ聞くだけではそんな気がしますよね。
所が、よくよく考えてみると確かに世の中はそんなところがあります。
例えば、大企業の社長に会える、
オーバーに言えば総理大臣に会える、
大都市の首長に会える、例えば東京都知事や大阪府知事
商工会議所の会頭、銀行の頭取
身近では、学校の校長に親しく会える
トップクラスの俳優や歌手に会える
・
・
そんな方に偶然に遭ったとか、すれ違ったなどは良くあることです。
空港でたまたま見かけたとか。
そうではなく、親しく会える、会話が交わせる、談笑ができる・・・・・
となるとなかなか機会が作れるものではありません。
社会的地位や経済的立場、年齢・・・などによって初めて実現できるものであってそんなに簡単に機会を持てるものでもありません。
そういうことから考えると確かに、
「出会い・・・その人の能力、レベル以上の出会いはない」という言葉も確かさを感じさせてくるものです。
であれば、やはりそういうレベルの方々と肩を並べることは無理にしても何らかの会える機会を作る事は何とかできそうな気がしないでもありません。
自分の能力、スキル、レベルを上げることができるとすればそのレベル程度の人々に会う機会は作れるということになります。
不思議なもので、そのレベルの方々に接しているうちにあと一段のレベルにも到達するチャンスがあるものです。
やはり意識する事なのではないでしょうかね。
継続艇努力によって、自らが成長しようとする事が大事だと思われます。
その事が、自分の人間性を高め、品性を磨き、それなりの素養の拡大に寄与していくものです。
日ごろから、自分を高める意識を持っている事が大事なようですね。
『生涯出会い、生涯夢、生涯感動、それが私の人生訓。上海貿易発展局顧問、筒井修』
『人生とは出会いであり、その招待は二度と繰り返されることはない。カロッサ』
Posted by misterkei0918 at
23:01
│Comments(0)
2010年12月24日
「一流の人は学び続ける、変化を続ける」
「一流の人は学び続ける、変化を続ける」
ある方が講演会でおっしゃった言葉です。
「一流の人は学び続ける、変化を続ける」
確かにそういう側面がありますよね。
学び続けるだけではなく、変化をすると云う所が大事なのでしょう。
学ぶ事はちょっと気のきいた人であればだれでも学びます。
変わる事が大事。
それとついでに言えば、学び方にも相違があるのかも。
闇雲に学ぶのではなく、大事なポイントをつくのが上手だったり、何を学べばいいのかを直感的につかめるのではないでしょうか。
或いは、日常的な会話の中にでも敏感に反応することも含めて日ごろからの訓練の賜物なのでしょう。
私もそうですが、学ぶ事は分かっていても自分を高めるために必要な学びやレベルやスキルを上げるための教養、自分の経営や社会活動に有用に働く知識の所在も分かっていないような気がします。
また、継続的な練磨を忘れ、一時的に知識が高まる事に一喜一憂。
そんな自分のような気がするのです。
あの、野球のイチローもそうでしょうし、
大相撲の白鳳だって・・・・・
或いはノーベル賞を貰われる方々もそうでしょう。
もしかするとそこまでいかなくても、身近で社会をリードしている方々や経済界のトップ、文化や芸能で秀でた能力を発揮する方々がそうです。
一流の人でなくても、一流の家庭や一流の企業でもそのような事だと思います。
一流の家庭は、学ぶ事に躊躇がなく自然な形で溶け込んでいるようにも思えますし、
一流の企業は、社会の動きを捕まえるのが上手ですし社員教育にも時間と予算を配慮し、常に変化する事を旨としているものです。
周りの人を見ていても、努力をする人や意識的に学ぶ人、会うたびに違った側面を見せる人は魅力的ですし、会うのが楽しみでもあります。
習慣化する事が大事なのでしょうね。
その為には、やはり環境が大事ですからそれを諭してくれる人や親に恵まれる事も大事でしょう。
「一流の人は学び続ける、変化を続ける」
心の片隅にでも置いておいたら、少しでもそのような一流の人や人生にいずれ傾いて行くやもしれません。
ある方が講演会でおっしゃった言葉です。
「一流の人は学び続ける、変化を続ける」
確かにそういう側面がありますよね。
学び続けるだけではなく、変化をすると云う所が大事なのでしょう。
学ぶ事はちょっと気のきいた人であればだれでも学びます。
変わる事が大事。
それとついでに言えば、学び方にも相違があるのかも。
闇雲に学ぶのではなく、大事なポイントをつくのが上手だったり、何を学べばいいのかを直感的につかめるのではないでしょうか。
或いは、日常的な会話の中にでも敏感に反応することも含めて日ごろからの訓練の賜物なのでしょう。
私もそうですが、学ぶ事は分かっていても自分を高めるために必要な学びやレベルやスキルを上げるための教養、自分の経営や社会活動に有用に働く知識の所在も分かっていないような気がします。
また、継続的な練磨を忘れ、一時的に知識が高まる事に一喜一憂。
そんな自分のような気がするのです。
あの、野球のイチローもそうでしょうし、
大相撲の白鳳だって・・・・・
或いはノーベル賞を貰われる方々もそうでしょう。
もしかするとそこまでいかなくても、身近で社会をリードしている方々や経済界のトップ、文化や芸能で秀でた能力を発揮する方々がそうです。
一流の人でなくても、一流の家庭や一流の企業でもそのような事だと思います。
一流の家庭は、学ぶ事に躊躇がなく自然な形で溶け込んでいるようにも思えますし、
一流の企業は、社会の動きを捕まえるのが上手ですし社員教育にも時間と予算を配慮し、常に変化する事を旨としているものです。
周りの人を見ていても、努力をする人や意識的に学ぶ人、会うたびに違った側面を見せる人は魅力的ですし、会うのが楽しみでもあります。
習慣化する事が大事なのでしょうね。
その為には、やはり環境が大事ですからそれを諭してくれる人や親に恵まれる事も大事でしょう。
「一流の人は学び続ける、変化を続ける」
心の片隅にでも置いておいたら、少しでもそのような一流の人や人生にいずれ傾いて行くやもしれません。
Posted by misterkei0918 at
20:15
│Comments(0)
2010年12月24日
人生は出会った事のない自分に出会う旅
人生は出会った事のない自分に出会う旅
人はどうも学んでも学んでも際限はなさそうです。
一つの事に集中しての学び、
幅広く博識を求める学びなど、学び方にもそれぞれです。
私はどちらかとういうと、博識を求める訳ではありませんが満遍なく学びたい方でしょうね。
できる事なら誰とでも、一応は会話ができる状況にはなりたいものです。
今更、物事を掘り下げて勉強するほど時間が残されていませんし、第一記憶能力や融通性や柔軟性が損なわれていますので、もう無理でしょう。
ならば今までの学んだ事を土台にして、少し上乗せをするくらいが丁度良さそうです。
一生学んでいく姿勢や新たな人生の開拓、引いてはできるだけの多くの人にお会いするにはそれなりに自分を向上させる事が大事ですし、光らなくても磨き続ける必要がありそうです。
人生はそのようにして、幅が広がるのでしょうし深化していくのでしょうね。
又出会いのない人生は寂しく、悲しいものです。
人は一人でも多くの人々と対面し、集い、そしてお互いを高め合うことで充実していきますし、豊かになるものです。
そして、その暁には今まで知らなかった自分の姿を垣間見たり、新しい自分の発見に感動したりするもの。
そんな事を思い描きながら過ごす人生は、決してマイナスにはなりませんし、その事だけでも新しい自分発見の旅の力づけになるものです。
「人生は出会った事のない自分に出会う旅」
森信三先生の言葉?
明日もそうであって欲しいと願いながら、頑張っていきたいものですね。
『どんな女でも、本気になって口説くことを決心した男にはなびかずにはいられないように、人生というものも、それを根気よく口説く人間には、その最上のものを提供せざるを得ないものだ。仏作家デュマ「パリの王様」より』
『常に何かを聞き、常に何かを考え、常に何かを学ぶ。これが人生の真の生き方である。何事も切望せず、何事も学ばない者は、生きる資格がない。Aヘルプス』
『何を始めるにしても、ゼロからのスタートではない。失敗や無駄だと思われたことなどを含めて、今までの人生で学んできたことを、決して低く評価する必要はない。カーネルサンダース』
人はどうも学んでも学んでも際限はなさそうです。
一つの事に集中しての学び、
幅広く博識を求める学びなど、学び方にもそれぞれです。
私はどちらかとういうと、博識を求める訳ではありませんが満遍なく学びたい方でしょうね。
できる事なら誰とでも、一応は会話ができる状況にはなりたいものです。
今更、物事を掘り下げて勉強するほど時間が残されていませんし、第一記憶能力や融通性や柔軟性が損なわれていますので、もう無理でしょう。
ならば今までの学んだ事を土台にして、少し上乗せをするくらいが丁度良さそうです。
一生学んでいく姿勢や新たな人生の開拓、引いてはできるだけの多くの人にお会いするにはそれなりに自分を向上させる事が大事ですし、光らなくても磨き続ける必要がありそうです。
人生はそのようにして、幅が広がるのでしょうし深化していくのでしょうね。
又出会いのない人生は寂しく、悲しいものです。
人は一人でも多くの人々と対面し、集い、そしてお互いを高め合うことで充実していきますし、豊かになるものです。
そして、その暁には今まで知らなかった自分の姿を垣間見たり、新しい自分の発見に感動したりするもの。
そんな事を思い描きながら過ごす人生は、決してマイナスにはなりませんし、その事だけでも新しい自分発見の旅の力づけになるものです。
「人生は出会った事のない自分に出会う旅」
森信三先生の言葉?
明日もそうであって欲しいと願いながら、頑張っていきたいものですね。
『どんな女でも、本気になって口説くことを決心した男にはなびかずにはいられないように、人生というものも、それを根気よく口説く人間には、その最上のものを提供せざるを得ないものだ。仏作家デュマ「パリの王様」より』
『常に何かを聞き、常に何かを考え、常に何かを学ぶ。これが人生の真の生き方である。何事も切望せず、何事も学ばない者は、生きる資格がない。Aヘルプス』
『何を始めるにしても、ゼロからのスタートではない。失敗や無駄だと思われたことなどを含めて、今までの人生で学んできたことを、決して低く評価する必要はない。カーネルサンダース』
Posted by misterkei0918 at
18:39
│Comments(0)
2010年12月24日
2010年12月20日
徳川家康は偉い!!
徳川家康は偉い!!
天下の家康に向って「偉い!!」などと大変失礼なことです。
身の程知らずというか、身分を弁(わきま)えていないというか。
今の世の中の方がむしろ混迷の度合いでいえば、深いような気がします。
過ぎ去った過去はつい美化してしまうものですから、正確ではないのでしょうがどうも素人判断にしてもそのような気がします。
国内も今の政治の混迷は、悲しくさえなります。
私どもの悲痛なまでの声は何処まで聞こえているのか。
国際的にも一触即発、危ない状態です。
江戸時代は、260年。
良くもこんなに続いたものだと思いますが、日本2600年の歴史からみれば不思議ではありませんよね。
若いころ、書物だったか、人から教えていただいたか定かではありませんが徳川家康の言葉として「人は重荷を背負うて行くがごとし」?という言葉を覚えています。
字句は正確ではないかもしれません、ご勘弁を。
確かにそうですよね。
人間の肩には、いつもズシッと重いものが乗っかっているものです。
家康が天下を取り、長い年月を経た後に明治維新を迎えるわけですが、考えてみたらその長い江戸時代があったからこそ、或いは鎖国の時代を経験していればこその開国であり、一挙に燃え上がる炎になったのでしょうね。
外見の印象から、「たぬき」などと揶揄されますが、案外そうでもなかったかもしれません。
また、家康からはこんな言葉も教えていただけます。
「勝つ事ばかり知りて、負くる事を知らざれば、害その身に至る」
**********
勝ってばかりで負けた経験がなければ、やがて痛い目に遭う。
負けたり失敗したりする経験は、さまざまな事を学べるだけでなく、再び立ち向かうための精神力も鍛えてくれる。
勝ってばかりで負けた経験がない人間は、そのどちらも身につける事が出来ない。
そのため、いずれ大きな負けを経験するであろうばかりか、その負けから立ち直る力も知恵も持てない。
**********
失敗を怖がらないで、果敢に挑戦する。
たとえ失敗しても次の高いステップへの踏み台と思えばいいのです。
繰り返すうちに、不思議な事が起きてきます。
失敗を怖がらなくなりますし、
結果的に人生において決定的な失敗をしなくなったり、
破滅や挫折を経験しなくなるものです。
身の程をわきまえて、足元を見つめる癖。
そんな事が、備わってくるのでしょうね。
でも、独断横着な言動や他人に迷惑をかけたり、人との関係をないがしろにしたり、真剣に物事に取り組む姿勢を忘れては世の中から見捨てられてしまいます。
先人の言葉は重いものです。
天下の家康に向って「偉い!!」などと大変失礼なことです。
身の程知らずというか、身分を弁(わきま)えていないというか。
今の世の中の方がむしろ混迷の度合いでいえば、深いような気がします。
過ぎ去った過去はつい美化してしまうものですから、正確ではないのでしょうがどうも素人判断にしてもそのような気がします。
国内も今の政治の混迷は、悲しくさえなります。
私どもの悲痛なまでの声は何処まで聞こえているのか。
国際的にも一触即発、危ない状態です。
江戸時代は、260年。
良くもこんなに続いたものだと思いますが、日本2600年の歴史からみれば不思議ではありませんよね。
若いころ、書物だったか、人から教えていただいたか定かではありませんが徳川家康の言葉として「人は重荷を背負うて行くがごとし」?という言葉を覚えています。
字句は正確ではないかもしれません、ご勘弁を。
確かにそうですよね。
人間の肩には、いつもズシッと重いものが乗っかっているものです。
家康が天下を取り、長い年月を経た後に明治維新を迎えるわけですが、考えてみたらその長い江戸時代があったからこそ、或いは鎖国の時代を経験していればこその開国であり、一挙に燃え上がる炎になったのでしょうね。
外見の印象から、「たぬき」などと揶揄されますが、案外そうでもなかったかもしれません。
また、家康からはこんな言葉も教えていただけます。
「勝つ事ばかり知りて、負くる事を知らざれば、害その身に至る」
**********
勝ってばかりで負けた経験がなければ、やがて痛い目に遭う。
負けたり失敗したりする経験は、さまざまな事を学べるだけでなく、再び立ち向かうための精神力も鍛えてくれる。
勝ってばかりで負けた経験がない人間は、そのどちらも身につける事が出来ない。
そのため、いずれ大きな負けを経験するであろうばかりか、その負けから立ち直る力も知恵も持てない。
**********
失敗を怖がらないで、果敢に挑戦する。
たとえ失敗しても次の高いステップへの踏み台と思えばいいのです。
繰り返すうちに、不思議な事が起きてきます。
失敗を怖がらなくなりますし、
結果的に人生において決定的な失敗をしなくなったり、
破滅や挫折を経験しなくなるものです。
身の程をわきまえて、足元を見つめる癖。
そんな事が、備わってくるのでしょうね。
でも、独断横着な言動や他人に迷惑をかけたり、人との関係をないがしろにしたり、真剣に物事に取り組む姿勢を忘れては世の中から見捨てられてしまいます。
先人の言葉は重いものです。
Posted by misterkei0918 at
19:43
│Comments(1)
2010年12月18日
人の欠点が気になり始めたら要注意!!
人の欠点が気になり始めたら要注意!!
「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」
「箸の上げ下ろしまで気になる」
人同士は歯車が狂い始めたら、何処まで行くのだろうと思うほど際限なく、傷口が広がったりするものです。
人間とはそのようなものでしょうが、いったん離れた気持ちはなかなか元には戻りにくく、元の関係に戻るということはほとんだないものです。
修復は困難ですよね。
その点、親子や兄弟は有難いものです。
少々悪口を言っても、気に食わない事をしても許せるものです。
でも限度がありますよね。
また、夫婦などのようにそこに他人が挟まってくると時として肉親の情も何処かへ追いやられてしまうことだって生じます。
日ごろからなるべく欠点は見ないように心掛けることが大事なようです。
黙っていても人の欠点は目につくものです。
その点、自分のことは見えているようで見えていないんですね。
また、自分のことは美化しますし、許せますし、場合によってはむしろ長所にだってしてしまいます。
社員に対してでもそうです。
当然、経営者が見る目は厳しいものですし、要求が過大になりがちで、つい能力を過小評価したり無理難題を押し付けたりもします。
そういう目で見る経営者自身も実はたいしたことはないのですがね。
過去を振り返ってみると、他人の欠点が気になりだしたり、過剰な要求に終始したりする時は自分の心の内にこそ、危ないものが潜んでいたり、問題を抱えていることが多いものです。
平常心を欠いていたり、落ち着きがなかったり、自分自身の能力の低下や経営の状態が良くなかったり、
家庭の問題やお世話ごとに問題を抱えていたりもします。
他人を見る目に変化が出てきたら、自らの何処かに危険が潜んでいることを認識していた方が賢明なようです。
案外、自分をカムフラージュする為の自己防衛の行動であることがあるのです。
不思議なもので、他人の言動が気になる時は自分の言動に変化が出てきている時が多いものです。
「目は心の窓」などと言いますが、結局は他人の事が気になることは自分自身が気になる状態であることに心を砕かないといけないようですね。
『他人の悪を能(よ)く見る者は、己が悪これを見ず。足利尊氏』
「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」
「箸の上げ下ろしまで気になる」
人同士は歯車が狂い始めたら、何処まで行くのだろうと思うほど際限なく、傷口が広がったりするものです。
人間とはそのようなものでしょうが、いったん離れた気持ちはなかなか元には戻りにくく、元の関係に戻るということはほとんだないものです。
修復は困難ですよね。
その点、親子や兄弟は有難いものです。
少々悪口を言っても、気に食わない事をしても許せるものです。
でも限度がありますよね。
また、夫婦などのようにそこに他人が挟まってくると時として肉親の情も何処かへ追いやられてしまうことだって生じます。
日ごろからなるべく欠点は見ないように心掛けることが大事なようです。
黙っていても人の欠点は目につくものです。
その点、自分のことは見えているようで見えていないんですね。
また、自分のことは美化しますし、許せますし、場合によってはむしろ長所にだってしてしまいます。
社員に対してでもそうです。
当然、経営者が見る目は厳しいものですし、要求が過大になりがちで、つい能力を過小評価したり無理難題を押し付けたりもします。
そういう目で見る経営者自身も実はたいしたことはないのですがね。
過去を振り返ってみると、他人の欠点が気になりだしたり、過剰な要求に終始したりする時は自分の心の内にこそ、危ないものが潜んでいたり、問題を抱えていることが多いものです。
平常心を欠いていたり、落ち着きがなかったり、自分自身の能力の低下や経営の状態が良くなかったり、
家庭の問題やお世話ごとに問題を抱えていたりもします。
他人を見る目に変化が出てきたら、自らの何処かに危険が潜んでいることを認識していた方が賢明なようです。
案外、自分をカムフラージュする為の自己防衛の行動であることがあるのです。
不思議なもので、他人の言動が気になる時は自分の言動に変化が出てきている時が多いものです。
「目は心の窓」などと言いますが、結局は他人の事が気になることは自分自身が気になる状態であることに心を砕かないといけないようですね。
『他人の悪を能(よ)く見る者は、己が悪これを見ず。足利尊氏』
Posted by misterkei0918 at
23:25
│Comments(0)
2010年12月18日
晩学の勧め
晩学の勧め
若いころ、或いは勉学に勤しまねばならない時期をおろそかにしてきた事の付けが今頃になって回ってきたのでしょうか。
頭の回転は良くない癖に勉強だけはしたいのです。
所謂、今までしてこなかった分の欲望が頭をもたげてきたのでしょうね。
でも、義務感とか際立った必要性に駆られているのでもなく、ただ淡々と時間にあまり拘束もされないで、しかも拘束感もなくて学ぶのが大好きになってきました。
これが、試験対策だとか競争に駆られるとなると多分私の性格では勉強の機会を作ることをしないかもしれません。
自分のペースで、自分が学びたいものをわがままに学んでおります。
しかも一貫性もなく。
先日から読んでいる、と言ってもまとまった時間がとれませんので、車で走っている赤信号の待ち時間とか、汚い話ですが、トイレの中だとかで断片的に読んでいるのです。
こんなところが目に留まりました。
本居宣長が書いた本で「うひ山ふみ」という本があるらしいのです。
この本は、「初学(うひまなび)」を「山踏み(やまあるき)」にたとえた学問の入門書のようです。
1798年10月、宣長69歳の時に書いた10ページに満たない小著。
私にとって嬉しいことが書かれています。
「晩学(おそまなび)」について、かなりの年をとってからの晩学であってもそれなりの成果はあるであろうし、「人の才、不才」ということも「怠らず勉めだにすれば」・・・・・
と言っているのです。
嬉しいことです。
遅まきながら、勉学に勤しもうとすると今更という気持ちにもなりますし、無駄な抵抗でもありますし、幾らか気後れなども感じるものです。
役に立てようとか、人様と競い合うとか余分な思いに走らないでマイペースで学びたいものを年をとっても学ぶ姿勢が大事なのでしょうね。
若いころ、或いは勉学に勤しまねばならない時期をおろそかにしてきた事の付けが今頃になって回ってきたのでしょうか。
頭の回転は良くない癖に勉強だけはしたいのです。
所謂、今までしてこなかった分の欲望が頭をもたげてきたのでしょうね。
でも、義務感とか際立った必要性に駆られているのでもなく、ただ淡々と時間にあまり拘束もされないで、しかも拘束感もなくて学ぶのが大好きになってきました。
これが、試験対策だとか競争に駆られるとなると多分私の性格では勉強の機会を作ることをしないかもしれません。
自分のペースで、自分が学びたいものをわがままに学んでおります。
しかも一貫性もなく。
先日から読んでいる、と言ってもまとまった時間がとれませんので、車で走っている赤信号の待ち時間とか、汚い話ですが、トイレの中だとかで断片的に読んでいるのです。
こんなところが目に留まりました。
本居宣長が書いた本で「うひ山ふみ」という本があるらしいのです。
この本は、「初学(うひまなび)」を「山踏み(やまあるき)」にたとえた学問の入門書のようです。
1798年10月、宣長69歳の時に書いた10ページに満たない小著。
私にとって嬉しいことが書かれています。
「晩学(おそまなび)」について、かなりの年をとってからの晩学であってもそれなりの成果はあるであろうし、「人の才、不才」ということも「怠らず勉めだにすれば」・・・・・
と言っているのです。
嬉しいことです。
遅まきながら、勉学に勤しもうとすると今更という気持ちにもなりますし、無駄な抵抗でもありますし、幾らか気後れなども感じるものです。
役に立てようとか、人様と競い合うとか余分な思いに走らないでマイペースで学びたいものを年をとっても学ぶ姿勢が大事なのでしょうね。
Posted by misterkei0918 at
01:45
│Comments(0)
2010年12月17日
「愛の欲求」について語る
「愛の欲求」について語る
私にとって愛について語るほど、難しく感じることはありません。
それは、私の幼児体験がそうであり、また幼児時代の生育の過程がそうであったようにどちらかというと歪(いびつ)でねじ曲がった精神の在り方がそのようにさせているような気がします。
ある方のメルマガを拝見していましたら、十分に頷ける内容でしたので引用をさせていただきました。
読んでいただけば、残念ながら頷けるところが殆どであることに気づきます。
******************************
◆『三つの愛の欲求』を満たすことが心身のバランスを保つコツ
宗像恒次教授(筑波大学大学院)
私たちが心身ともに健康であるためには、この世に生まれ、生きていることの幸福を実感できることが大前提となり、そのためには、欲求の充足・不充足のバランスが取れていることが不可欠なのだ。
問題は、多くの人が根本にある「三つの愛の欲求」の存在に気づいていないことにある。
人は、例えば「愛してもらえない」あるいは「愛してもらえそうもない」といった状況に遭遇すると、本人がその理由に気づいていても、腹が立ったり不安になったりする。
なかには、衝動を抑えることができず、パニック状態に陥ってしまう人もいる。
そのような抑えがたい怒りや悲しみ、みじめさといった否定的な情動(身体的・生理的変化をともなう感情の動き)は、愛の欲求が充足されないときに生じる生体反応である。
多くの人は、自分のなかにそのような情動が生じることはあっても、そんな思いがどこから、なぜ湧き上がってくるのかという本当の理由を知らない。
しかし、その「知らない」ということが、身体疾患や精神疾患をつくり出す重大なストレスとなりうるのである。
がんやうつ病をはじめ、糖尿病、高血圧などの生活習慣病のほとんどは、不健康な行動習慣をつくり出す「ストレス性格病」である。
だが、その根元になるものは、こうした愛の欲求が満たされない飢餓感の持続が生み出した愛のストレス病であると、私はみている。
愛の渇望感が生まれるとき三つの愛の欲求についてもう少し詳しく見ていこう。
●一つ目の愛の欲求「慈愛願望欲求」
他人に評価されることによって自分を認めようとする「人から認められたい、愛されたい」欲求である。 だいたい10歳頃までの生育過程で、両親や周囲の大人たちに十分に認められ愛されていれば、この欲求は十分に満たされ、渇望感は、大人になってまで尾を引くことはない。
しかし、両親の仲がよくなかった、あるいは片親が早くに死んだなどという過去の記憶があると、大人になってからも、「私を愛して!」「私を認めて!」という心の衝動に振り回されることになる。
●二つ目の愛の欲求「自己信頼欲求」
他人の評価にかかわらず、自分自身を信じて認めようとする欲求である。
一つ目の慈愛願望欲求が適切に満たされた環境のなかで育つと、次に人は、自分に自信を持ちたいと欲求が強まる。
そして、自分を信じて自分の意思で行動するようになり、行動することによって目標を達成する喜びを知り、自分に対する信頼感を深めていく。
ところが、自己信頼欲求を充足しようとする子どもの行動は、親から発せられる「~してはだめ」「~しなさい」という禁止・指示・命令語でしばしば阻まれる。あなたも自分の子ども時代や、あるいは子育て時代を振り返ってみると思い当たるのではないだろうか。
自己信頼欲求を充足させるような理想の生育環境など、現実にはなかなかありえないことなのだ。
何かをするにしても親の監視のもとであったり、やりたいことをやらせてもらえなかったり、反対にやりたくないことを強制されたりと、ほとんどの人が、自己信頼欲求を十分に満たすことがないまま大人になっているというのが現状だろう。
他人の評価に一喜一憂し「誰がどう評価しようが、自分は自分」というふうに考えられないのは、自分を信頼するために必要な行動体験を子どもの頃にしていないからにほかならない。
●三つ目の欲求「慈愛欲求」
最後に、自分を信じることができて始めて強まってくる欲求である。
他人の評価はどうあれ、自分の損得はどうあれ、他人を無条件に認め、愛したいという欲求である。この欲求は、自己信頼欲求がある程度満たされていないと生まれてはこない。
自分に自信がなく、他人に認めてもらうだけで精一杯という人に、他人を思いやるゆとりがあろうはずもない。
ただ、「人を愛したい」という慈愛欲求は、一つ目の「人に愛されたい」という慈愛願望欲求と勘違いされやすく、本人でさえそのすり替えに気がつかないことがある。
世の中にはやたらに人の面倒を見たがるおせっかい焼きや、善意の押し付けをして自己満足している人が、けっこういるようだ。
本人は人のためにしているつもりでも、はたからは自己満足でやっているとしか見えない。
こういった人たちの行動は、一見すると慈愛欲求から出ていると思うかもしれないが、実は「必要とされたい」という慈愛願望欲求を満たす行動である場合がほとんどである。
「人に必要とされている」「人の役に立っている」そう思えるような行動をとることにより、「自分を認めてほしい、愛してほしい」という慈愛願望欲求を満たそうとしているのだ。
*****************************
私にとって愛について語るほど、難しく感じることはありません。
それは、私の幼児体験がそうであり、また幼児時代の生育の過程がそうであったようにどちらかというと歪(いびつ)でねじ曲がった精神の在り方がそのようにさせているような気がします。
ある方のメルマガを拝見していましたら、十分に頷ける内容でしたので引用をさせていただきました。
読んでいただけば、残念ながら頷けるところが殆どであることに気づきます。
******************************
◆『三つの愛の欲求』を満たすことが心身のバランスを保つコツ
宗像恒次教授(筑波大学大学院)
私たちが心身ともに健康であるためには、この世に生まれ、生きていることの幸福を実感できることが大前提となり、そのためには、欲求の充足・不充足のバランスが取れていることが不可欠なのだ。
問題は、多くの人が根本にある「三つの愛の欲求」の存在に気づいていないことにある。
人は、例えば「愛してもらえない」あるいは「愛してもらえそうもない」といった状況に遭遇すると、本人がその理由に気づいていても、腹が立ったり不安になったりする。
なかには、衝動を抑えることができず、パニック状態に陥ってしまう人もいる。
そのような抑えがたい怒りや悲しみ、みじめさといった否定的な情動(身体的・生理的変化をともなう感情の動き)は、愛の欲求が充足されないときに生じる生体反応である。
多くの人は、自分のなかにそのような情動が生じることはあっても、そんな思いがどこから、なぜ湧き上がってくるのかという本当の理由を知らない。
しかし、その「知らない」ということが、身体疾患や精神疾患をつくり出す重大なストレスとなりうるのである。
がんやうつ病をはじめ、糖尿病、高血圧などの生活習慣病のほとんどは、不健康な行動習慣をつくり出す「ストレス性格病」である。
だが、その根元になるものは、こうした愛の欲求が満たされない飢餓感の持続が生み出した愛のストレス病であると、私はみている。
愛の渇望感が生まれるとき三つの愛の欲求についてもう少し詳しく見ていこう。
●一つ目の愛の欲求「慈愛願望欲求」
他人に評価されることによって自分を認めようとする「人から認められたい、愛されたい」欲求である。 だいたい10歳頃までの生育過程で、両親や周囲の大人たちに十分に認められ愛されていれば、この欲求は十分に満たされ、渇望感は、大人になってまで尾を引くことはない。
しかし、両親の仲がよくなかった、あるいは片親が早くに死んだなどという過去の記憶があると、大人になってからも、「私を愛して!」「私を認めて!」という心の衝動に振り回されることになる。
●二つ目の愛の欲求「自己信頼欲求」
他人の評価にかかわらず、自分自身を信じて認めようとする欲求である。
一つ目の慈愛願望欲求が適切に満たされた環境のなかで育つと、次に人は、自分に自信を持ちたいと欲求が強まる。
そして、自分を信じて自分の意思で行動するようになり、行動することによって目標を達成する喜びを知り、自分に対する信頼感を深めていく。
ところが、自己信頼欲求を充足しようとする子どもの行動は、親から発せられる「~してはだめ」「~しなさい」という禁止・指示・命令語でしばしば阻まれる。あなたも自分の子ども時代や、あるいは子育て時代を振り返ってみると思い当たるのではないだろうか。
自己信頼欲求を充足させるような理想の生育環境など、現実にはなかなかありえないことなのだ。
何かをするにしても親の監視のもとであったり、やりたいことをやらせてもらえなかったり、反対にやりたくないことを強制されたりと、ほとんどの人が、自己信頼欲求を十分に満たすことがないまま大人になっているというのが現状だろう。
他人の評価に一喜一憂し「誰がどう評価しようが、自分は自分」というふうに考えられないのは、自分を信頼するために必要な行動体験を子どもの頃にしていないからにほかならない。
●三つ目の欲求「慈愛欲求」
最後に、自分を信じることができて始めて強まってくる欲求である。
他人の評価はどうあれ、自分の損得はどうあれ、他人を無条件に認め、愛したいという欲求である。この欲求は、自己信頼欲求がある程度満たされていないと生まれてはこない。
自分に自信がなく、他人に認めてもらうだけで精一杯という人に、他人を思いやるゆとりがあろうはずもない。
ただ、「人を愛したい」という慈愛欲求は、一つ目の「人に愛されたい」という慈愛願望欲求と勘違いされやすく、本人でさえそのすり替えに気がつかないことがある。
世の中にはやたらに人の面倒を見たがるおせっかい焼きや、善意の押し付けをして自己満足している人が、けっこういるようだ。
本人は人のためにしているつもりでも、はたからは自己満足でやっているとしか見えない。
こういった人たちの行動は、一見すると慈愛欲求から出ていると思うかもしれないが、実は「必要とされたい」という慈愛願望欲求を満たす行動である場合がほとんどである。
「人に必要とされている」「人の役に立っている」そう思えるような行動をとることにより、「自分を認めてほしい、愛してほしい」という慈愛願望欲求を満たそうとしているのだ。
*****************************
Posted by misterkei0918 at
23:28
│Comments(0)
2010年12月16日
人を思い煩うな、因は自らの心にあり
人を思い煩うな、因は自らの心にあり
私の悪い癖です。
責任転嫁を得意技としています。
問題が発生するとすぐ人の精にする、
被害妄想に捕らわれる、
逃げ出す、
知らんふりを決め込む・・・・・
得意分野は、自慢の種ですがこればかりはどうにも困ったものです。
人としての在り方を、しっかり身につけていない証拠です。
昔からというか、仏教用語で「因果応報」とは良く聞かされました。
ネット上の辞書から頂いてきました。
『人はよい行いをすればよい報いがあり、悪い行いをすれば悪い報いがあるということ。
もと仏教語。
行為の善悪に応じて、その報いがあること。
現在では悪いほうに用いられることが多い。
「因」は因縁の意で、原因のこと。
「果」は果報の意で、原因によって生じた結果や報いのこと』
どうも、さまざまな事象の原因のほとんどは私にあって、慎むべき、反省すべき、謝るべきは私のようです。
そのように判断するか、結論付けた方が案外気持ちの座りもいいですし、丸く収まるような気がするのです。
それでも、尊厳や人権に関わること、命に関わることは簡単に飲むわけにはいきませんが。
徹底抗戦しないといけませんよね。
また、明らかに相手が間違っていることや譲れない事、物事の真実、不誠実に関わることなどもそうかもしれませんね。
何事もそうですが、「自分はどうなのか」や「自分に責任や間違いは何のか」などの自問を繰り返す癖が大事に思われます。
人は不思議なもので、自らに原因があると認められるときに限って必要以上に憤ってみたり、自己保身や自己保全に努めるものです。
反省の日々です。
「人を思い煩うな、因は自らの心にあり」ですよね。
私の悪い癖です。
責任転嫁を得意技としています。
問題が発生するとすぐ人の精にする、
被害妄想に捕らわれる、
逃げ出す、
知らんふりを決め込む・・・・・
得意分野は、自慢の種ですがこればかりはどうにも困ったものです。
人としての在り方を、しっかり身につけていない証拠です。
昔からというか、仏教用語で「因果応報」とは良く聞かされました。
ネット上の辞書から頂いてきました。
『人はよい行いをすればよい報いがあり、悪い行いをすれば悪い報いがあるということ。
もと仏教語。
行為の善悪に応じて、その報いがあること。
現在では悪いほうに用いられることが多い。
「因」は因縁の意で、原因のこと。
「果」は果報の意で、原因によって生じた結果や報いのこと』
どうも、さまざまな事象の原因のほとんどは私にあって、慎むべき、反省すべき、謝るべきは私のようです。
そのように判断するか、結論付けた方が案外気持ちの座りもいいですし、丸く収まるような気がするのです。
それでも、尊厳や人権に関わること、命に関わることは簡単に飲むわけにはいきませんが。
徹底抗戦しないといけませんよね。
また、明らかに相手が間違っていることや譲れない事、物事の真実、不誠実に関わることなどもそうかもしれませんね。
何事もそうですが、「自分はどうなのか」や「自分に責任や間違いは何のか」などの自問を繰り返す癖が大事に思われます。
人は不思議なもので、自らに原因があると認められるときに限って必要以上に憤ってみたり、自己保身や自己保全に努めるものです。
反省の日々です。
「人を思い煩うな、因は自らの心にあり」ですよね。
Posted by misterkei0918 at
16:57
│Comments(0)
2010年12月16日
学びの場は日常の何処にもある
学びの場は日常の何処にもある
学業の時期にある世代の頃は、思い起こせば幾らでも学業の為に時間が作れたのですがそんな時に限って時間を無駄?に消費していたものです。
無駄が大事なのもわかりますし、そんな多感な時期は友人関係や恋愛、親との関係、スポーツや遊びとそれなりに時間に追われていたような気もします。
勉学のみに集中することも大事ですが、その時期にしか学べない大切なものが周りには山積していたものです。
当時はそれらが人生にとって、必要不可欠、貴重なものとは感じることはありませんでしたが年を重ねてみると十分に納得ができます。
ですが、何事も学ぼうとする姿勢だけは、若いころから備える努力はしていた方が良さそうです。
学びの癖とでも言うのでしょうかね。
私の今までは、意識的に学ぶ時間を持たなかったことが今日の後悔に繋がっているような気がします。
ただ、経営や社会活動、ボランティアの為に前ばかりを見詰めて我武者羅に突っ走ってばかりの日々でした。
心のゆとりがなかったのでしょうね。
最近、ここ数年ですが学びの喜びと言いますか、人様から教えていただくことの有難さや楽しさを満喫できるようになってきました。
知らない事の多さにただただ驚嘆するばかり、
物知りの人がどんなに世の中に多いことか、思い知ることしきりです。
ある特定のことを学びたいということであれば別ですが、人生や一般常識的なこと、歴史や自然・・・のことであれば私どもの日常の中に幾らでも転がっていますし、教えていただける機会や人も探すのにそんなに無理はなさそうです。
若い方々の中に、混じって学ぶのも良いものです。
「その年になって何事か?」
「年寄りの来るところではない」などと幾らか気後れがしたり、恥ずかしい気はしますが、彼らに生きざまを見せるためにも良いかと、自分に言い聞かせながらのことであります。
考えてみれば、学びの場は幾らでも存在したのですね。
時間が足らないとか、忙しいとかはただの言い訳にすぎない事に気付きます。
学業の時期にある世代の頃は、思い起こせば幾らでも学業の為に時間が作れたのですがそんな時に限って時間を無駄?に消費していたものです。
無駄が大事なのもわかりますし、そんな多感な時期は友人関係や恋愛、親との関係、スポーツや遊びとそれなりに時間に追われていたような気もします。
勉学のみに集中することも大事ですが、その時期にしか学べない大切なものが周りには山積していたものです。
当時はそれらが人生にとって、必要不可欠、貴重なものとは感じることはありませんでしたが年を重ねてみると十分に納得ができます。
ですが、何事も学ぼうとする姿勢だけは、若いころから備える努力はしていた方が良さそうです。
学びの癖とでも言うのでしょうかね。
私の今までは、意識的に学ぶ時間を持たなかったことが今日の後悔に繋がっているような気がします。
ただ、経営や社会活動、ボランティアの為に前ばかりを見詰めて我武者羅に突っ走ってばかりの日々でした。
心のゆとりがなかったのでしょうね。
最近、ここ数年ですが学びの喜びと言いますか、人様から教えていただくことの有難さや楽しさを満喫できるようになってきました。
知らない事の多さにただただ驚嘆するばかり、
物知りの人がどんなに世の中に多いことか、思い知ることしきりです。
ある特定のことを学びたいということであれば別ですが、人生や一般常識的なこと、歴史や自然・・・のことであれば私どもの日常の中に幾らでも転がっていますし、教えていただける機会や人も探すのにそんなに無理はなさそうです。
若い方々の中に、混じって学ぶのも良いものです。
「その年になって何事か?」
「年寄りの来るところではない」などと幾らか気後れがしたり、恥ずかしい気はしますが、彼らに生きざまを見せるためにも良いかと、自分に言い聞かせながらのことであります。
考えてみれば、学びの場は幾らでも存在したのですね。
時間が足らないとか、忙しいとかはただの言い訳にすぎない事に気付きます。
Posted by misterkei0918 at
15:42
│Comments(0)
2010年12月12日
今は過去の遺産であって未来の土台に
今は過去の遺産であって未来の土台に
先月の13,14日は奈良へ行ってきました。
「平城京1300年祭」の後でしたので、物静かな雰囲気の中の行脚でした。
大和三山や唐招提寺・・・・・などを回ってきたのです。
走行距離約15キロ。
良くも歩いたものだと我ながら感心しています。
家内も一緒でしたが、不思議なことに全く疲れがなかったのはどういうことだったのでしょうかね。
今思うと尋ねるところいたる所で、両手を合わせて拝んで参りましたのでそれもご利益の一つだったのかもしれません。
それだけではなく、普段から歩く習慣をつけていたのも良かったのでしょう。
多くの世界遺産の存在する日本の宝ですから、じっくり時間をかけたかったのですが今回の旅は歩くことが主目的でしたのでいつかまた訪問をしたいと思っています。
世界遺産は遥か歴史の彼方の財産ですが、それが私どもの国民性や文化の代表的なものですから現代を生きる私どもの決して無縁ではないと思われます。
私どもでもそうですよね。
自分の過去に付きまとうもの、或いはご先祖が培った遺構。
それが例え自分が気に入らない、存在を否定したいようなことであっても歴然とした捨てがたい刻印であると思っています。
悲しい過去、苦しい昔、失敗の時代・・・・・
それぞれは人生において消し難い歴然とした過去であります。
むしろそれを捨て去るより、逃げることより、それを踏み台、栄養として逞しく生きることことこそ称賛されるべきであり、むしろ貴なものであることに思いを馳せることが大事だと思うのです。
過去は捨てるものではなく活かすもの・・・そうありたいものです。
『苦悩こそ人生の真の姿である。我々の最後の喜びと慰めは、苦しんだ過去の記録に他ならない。ミュッセ』
『過去の因を知らんと欲せばその現在の果を見よ。未来の果を知らんと欲せばその現在の因を見よ。「心地観経」』
『現在のあなたは、過去の思考の産物である。そして明日のあなたは、今日何を考えるかで決まる。ジェームズアレン』
先月の13,14日は奈良へ行ってきました。
「平城京1300年祭」の後でしたので、物静かな雰囲気の中の行脚でした。
大和三山や唐招提寺・・・・・などを回ってきたのです。
走行距離約15キロ。
良くも歩いたものだと我ながら感心しています。
家内も一緒でしたが、不思議なことに全く疲れがなかったのはどういうことだったのでしょうかね。
今思うと尋ねるところいたる所で、両手を合わせて拝んで参りましたのでそれもご利益の一つだったのかもしれません。
それだけではなく、普段から歩く習慣をつけていたのも良かったのでしょう。
多くの世界遺産の存在する日本の宝ですから、じっくり時間をかけたかったのですが今回の旅は歩くことが主目的でしたのでいつかまた訪問をしたいと思っています。
世界遺産は遥か歴史の彼方の財産ですが、それが私どもの国民性や文化の代表的なものですから現代を生きる私どもの決して無縁ではないと思われます。
私どもでもそうですよね。
自分の過去に付きまとうもの、或いはご先祖が培った遺構。
それが例え自分が気に入らない、存在を否定したいようなことであっても歴然とした捨てがたい刻印であると思っています。
悲しい過去、苦しい昔、失敗の時代・・・・・
それぞれは人生において消し難い歴然とした過去であります。
むしろそれを捨て去るより、逃げることより、それを踏み台、栄養として逞しく生きることことこそ称賛されるべきであり、むしろ貴なものであることに思いを馳せることが大事だと思うのです。
過去は捨てるものではなく活かすもの・・・そうありたいものです。
『苦悩こそ人生の真の姿である。我々の最後の喜びと慰めは、苦しんだ過去の記録に他ならない。ミュッセ』
『過去の因を知らんと欲せばその現在の果を見よ。未来の果を知らんと欲せばその現在の因を見よ。「心地観経」』
『現在のあなたは、過去の思考の産物である。そして明日のあなたは、今日何を考えるかで決まる。ジェームズアレン』
Posted by misterkei0918 at
10:48
│Comments(0)
2010年12月12日
春の息吹の為に輝きを失うも大事
春の息吹の為に輝きを失うも大事
今朝も福岡市中央区の大濠公園のウォーキングで汗を流してきました。
長距離のスポーツのシーズンになると、大濠公園も早朝から賑わいが戻ってきます。
今朝は、公園を周回するマラソンが開催されるようで大勢のスタッフの方々がテントの設営やスタート地点の整備・・・・・に余念がありません。
7時を過ぎたころから、多分参加すると思われる高校生や中学生が集団をなして集まってきました。
嬉しいですね、
子供たちが寒さを押してスポーツに勤しむことは頼もしいことですし、嬉しくもなります。
だって、将来を担う彼らが健康で逞しく育つことは、未来に大いに期待が持てるからです。
子供たちが賑やかに談笑する姿や、スポーツで汗を流す姿は私どもにとっては有難い希望を感じさせる姿です。
公園のイチョウやくぬぎもすっかり葉を落とすか、冬色に染まってきました。
自然は確実に巡ってくるものです。
あんなに記録的な酷暑はどこに行ったのでしょうかね。
記憶からも消え去りそうな位の季節の移り変わりです。
あんなに光り輝いていた木々の葉も来る厳しい冬に備え始めました。
人もそうですが、365日、四六時中緊張状態を持続することはできませんし、それはやがて破たんをきたしたりどこかに弊害をもたらすものです。
自然も同じですよね。
やがて来る春の為に、また光り輝くために休息や充電の時間が必要ということでしょう。
桜の木も、全ての木の葉を落とし、落とした木の葉を栄養として、自分が最も光り輝く季節を迎えるために、満開の花をつけるために備えるのです。
私どもの、時には全てのしがらみを忘れ、解放され、自らが過去の蓄えてきた知識や関係を栄養として、次に備える態度が大事なのかもしれませんね。
「経験に学ばず、歴史に学べ」と言われるように、
自然の一員として、身近な自然からも大いに学べることも多そうですね。
今朝も福岡市中央区の大濠公園のウォーキングで汗を流してきました。
長距離のスポーツのシーズンになると、大濠公園も早朝から賑わいが戻ってきます。
今朝は、公園を周回するマラソンが開催されるようで大勢のスタッフの方々がテントの設営やスタート地点の整備・・・・・に余念がありません。
7時を過ぎたころから、多分参加すると思われる高校生や中学生が集団をなして集まってきました。
嬉しいですね、
子供たちが寒さを押してスポーツに勤しむことは頼もしいことですし、嬉しくもなります。
だって、将来を担う彼らが健康で逞しく育つことは、未来に大いに期待が持てるからです。
子供たちが賑やかに談笑する姿や、スポーツで汗を流す姿は私どもにとっては有難い希望を感じさせる姿です。
公園のイチョウやくぬぎもすっかり葉を落とすか、冬色に染まってきました。
自然は確実に巡ってくるものです。
あんなに記録的な酷暑はどこに行ったのでしょうかね。
記憶からも消え去りそうな位の季節の移り変わりです。
あんなに光り輝いていた木々の葉も来る厳しい冬に備え始めました。
人もそうですが、365日、四六時中緊張状態を持続することはできませんし、それはやがて破たんをきたしたりどこかに弊害をもたらすものです。
自然も同じですよね。
やがて来る春の為に、また光り輝くために休息や充電の時間が必要ということでしょう。
桜の木も、全ての木の葉を落とし、落とした木の葉を栄養として、自分が最も光り輝く季節を迎えるために、満開の花をつけるために備えるのです。
私どもの、時には全てのしがらみを忘れ、解放され、自らが過去の蓄えてきた知識や関係を栄養として、次に備える態度が大事なのかもしれませんね。
「経験に学ばず、歴史に学べ」と言われるように、
自然の一員として、身近な自然からも大いに学べることも多そうですね。
Posted by misterkei0918 at
09:56
│Comments(0)