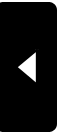2011年01月12日
嘘をついてもいいと教えてしまう世の中
嘘をついてもいいと教えてしまう世の中
子供にはさんざん嘘をついてはいけないと云いながら、片方の口では平気で嘘をつく。
人の嘘にはさんざんの文句を言うくせに自分は平気で嘘をつく。
「嘘も方便」などと逃げ口上を言い、自己弁護だけはしっかりする大人たち。
権力を握った途端に、約束事の全てを反故にし、時間が足りない、お金が足りない、出来なかった理由だけはしっかり探し出す。
嘘をついた事を咎められると、逆切れをし、逆恨みをする癖・・・・・・
世の中の構造が、嘘をついても構わないと如何にも教えているようです。
「正直者が馬鹿を見る」とは、昔の事ではなくまさしく現代の事であるよう。
「嘘は泥棒の始まり」などとうそぶいて、嘘をつける時代にもなってしまいました。
悪びれることなく、平気で嘘のつける世の中、正直であることが馬鹿と称される世の中、悲しい気がします。
全てが正直であれば良いとは考えてはいませんが、嘘のまかり通る世の中が果たして希望や夢の持てる社会と言えるのでしょうか。
「騙し合い」
「化かし合い」
純粋無垢等の言葉さえ、何処かへ置き忘れてきたような世の中になってしまいました。
何処かで、貧しくても物に恵まれなくても心優しい、思いやりの社会が訪れてほしいものですね。
「嘘に塗(まみ)れた」社会などいずれは砂上の楼閣と化すのかもしれませんね。
『人々がいつでも、正直なことをいうのはなぜか。
神が嘘を禁じたからではない。
それは、嘘をつかないほうが気が楽だからである。ニーチェ(独 哲学者)』
『よほど巧みに嘘をつけない限り、真実を語るに越したことはない。Jジェローム』
子供にはさんざん嘘をついてはいけないと云いながら、片方の口では平気で嘘をつく。
人の嘘にはさんざんの文句を言うくせに自分は平気で嘘をつく。
「嘘も方便」などと逃げ口上を言い、自己弁護だけはしっかりする大人たち。
権力を握った途端に、約束事の全てを反故にし、時間が足りない、お金が足りない、出来なかった理由だけはしっかり探し出す。
嘘をついた事を咎められると、逆切れをし、逆恨みをする癖・・・・・・
世の中の構造が、嘘をついても構わないと如何にも教えているようです。
「正直者が馬鹿を見る」とは、昔の事ではなくまさしく現代の事であるよう。
「嘘は泥棒の始まり」などとうそぶいて、嘘をつける時代にもなってしまいました。
悪びれることなく、平気で嘘のつける世の中、正直であることが馬鹿と称される世の中、悲しい気がします。
全てが正直であれば良いとは考えてはいませんが、嘘のまかり通る世の中が果たして希望や夢の持てる社会と言えるのでしょうか。
「騙し合い」
「化かし合い」
純粋無垢等の言葉さえ、何処かへ置き忘れてきたような世の中になってしまいました。
何処かで、貧しくても物に恵まれなくても心優しい、思いやりの社会が訪れてほしいものですね。
「嘘に塗(まみ)れた」社会などいずれは砂上の楼閣と化すのかもしれませんね。
『人々がいつでも、正直なことをいうのはなぜか。
神が嘘を禁じたからではない。
それは、嘘をつかないほうが気が楽だからである。ニーチェ(独 哲学者)』
『よほど巧みに嘘をつけない限り、真実を語るに越したことはない。Jジェローム』
Posted by misterkei0918 at
21:44
│Comments(0)
2011年01月12日
知りませんでした。守・破・離
知りませんでした。守・破・離
初めてこの言葉に触れたのは、4年ほど前でした。
多分、剣道や柔道などの日本古来の武道に勤しんだ方々、或いはお茶やお花などの伝統的な作法や修練を重ねた方々は先生方から、多分一度や二度はお聞きになったのではないでしょうか。
私は武道では、剣道を小学校の頃に遊びのようにして教えて頂いた事はありましたが、正式に教えを請うたことはありませんでしたので、全くこの言葉を耳にする事はありませんでした。
多分、多くの皆さんはご存じだったかも知れませんね。
調べてみましたら、極めて日本らしい言葉ですね。
******************************
およそ600年前、室町の三代将軍足利義満の時代に、「能」を育て上げた観阿弥、世阿弥親子が「風姿花伝」(「花伝書」ともいう。)のなかで展開した芸能論の一部のようです。
現在は能だけでなく、歌舞伎や狂言といった日本の伝統芸能、剣道や居合道、空手など武道の世界でも守破離という言葉が広く使われています。
守・・・ひたすら教えを守り、学ぶ。
ひたすら師の教えを守り、多くの話を聞き、師の行動を見習って、自分のものへとします。全てを習得できたと感じるまで、師の指導を繰り返します。
破・・・教えの言葉から抜け出し、真意を会得する。
既存の概念を破る事。疑問解決の為に、師の教えを守るだけではなく独自の工夫を重ね、師の教えにはなかった方法などを試していきます。意識的に師の教えを崩し、次第に発展し…独自の方法を築き上げていく事になります。
離・・・型に一切とらわれず、自在の境地に入ること。
この境地まで達すると、師のもとを離れていきます。破と違うのは、「一切のこだわりを捨て、自由に、思うままに考え、自然に身を置いて行えば、言わば合理の極致としておのずから至芸の境地に至る」事です。離はいわば理想の段階ですが、その「道」を学ぶ者ならば、離の段階に入っていかねばならないのです。
******************************
人の成長もそうかもしれませんね。
親や周りのしつけや教育をひたすら学ぶ時期、
その教えを基本として、より人間らしい姿へ移り、
年齢を重ねるとともに、他人とは違う自分らしさを会得する。
企業経営でもそうです。
最初は先代の見よう見まね、
そのうちほぼ一人前と化し、
年月とともに、新しい事業形態であったり、
全く新しいビジネスモデルとなったり、独自性が滲み出てくるものです。
修練とでも言うのでしょうかね。
或いは、悟りの境地?
或いは達観?
まだまだですが、そんな世界へいつか辿り着く事を夢見て精進したいものですね。
初めてこの言葉に触れたのは、4年ほど前でした。
多分、剣道や柔道などの日本古来の武道に勤しんだ方々、或いはお茶やお花などの伝統的な作法や修練を重ねた方々は先生方から、多分一度や二度はお聞きになったのではないでしょうか。
私は武道では、剣道を小学校の頃に遊びのようにして教えて頂いた事はありましたが、正式に教えを請うたことはありませんでしたので、全くこの言葉を耳にする事はありませんでした。
多分、多くの皆さんはご存じだったかも知れませんね。
調べてみましたら、極めて日本らしい言葉ですね。
******************************
およそ600年前、室町の三代将軍足利義満の時代に、「能」を育て上げた観阿弥、世阿弥親子が「風姿花伝」(「花伝書」ともいう。)のなかで展開した芸能論の一部のようです。
現在は能だけでなく、歌舞伎や狂言といった日本の伝統芸能、剣道や居合道、空手など武道の世界でも守破離という言葉が広く使われています。
守・・・ひたすら教えを守り、学ぶ。
ひたすら師の教えを守り、多くの話を聞き、師の行動を見習って、自分のものへとします。全てを習得できたと感じるまで、師の指導を繰り返します。
破・・・教えの言葉から抜け出し、真意を会得する。
既存の概念を破る事。疑問解決の為に、師の教えを守るだけではなく独自の工夫を重ね、師の教えにはなかった方法などを試していきます。意識的に師の教えを崩し、次第に発展し…独自の方法を築き上げていく事になります。
離・・・型に一切とらわれず、自在の境地に入ること。
この境地まで達すると、師のもとを離れていきます。破と違うのは、「一切のこだわりを捨て、自由に、思うままに考え、自然に身を置いて行えば、言わば合理の極致としておのずから至芸の境地に至る」事です。離はいわば理想の段階ですが、その「道」を学ぶ者ならば、離の段階に入っていかねばならないのです。
******************************
人の成長もそうかもしれませんね。
親や周りのしつけや教育をひたすら学ぶ時期、
その教えを基本として、より人間らしい姿へ移り、
年齢を重ねるとともに、他人とは違う自分らしさを会得する。
企業経営でもそうです。
最初は先代の見よう見まね、
そのうちほぼ一人前と化し、
年月とともに、新しい事業形態であったり、
全く新しいビジネスモデルとなったり、独自性が滲み出てくるものです。
修練とでも言うのでしょうかね。
或いは、悟りの境地?
或いは達観?
まだまだですが、そんな世界へいつか辿り着く事を夢見て精進したいものですね。
Posted by misterkei0918 at
18:18
│Comments(0)
2011年01月11日
「礼を尽くす」と言います
「礼を尽くす」と言います
「あいつは礼儀知らずな奴」、
「挨拶の仕方も知らないのか」、
などと言われます。
逆に「過ぎる礼儀」もわざとらしく感じてしまいますし、嫌なものです。
たかが礼儀と言われそうですが難しいものですね。
不足は不足でいけませんし、過ぎるは過ぎるで顰蹙ものですし。
爽やかに心置きなく、わだかまりなく、優しく言えるお礼が良いですよね。
困ったことにお礼や礼儀は、早過ぎるのもいけませんし、
遅くて時期を失すると、人間関係を損なう事もあり得ます。
「機を損なうことなく」という事も頭に置かないといけませんからやはり訓練なんでしょうね。
自分がお礼を言われる立場になって考えてみたら、どのようにする事が相手の気持ちを損なうことなく、むしろ関係を深めるお礼の仕方や方法も思いつくかもしれません。
調べてみました。
お礼の旧字は「禮」
左のネは本来は「示」・・・神にいけにえを捧げる台の象形。
人に現わして見せる、教える、告げる、指図する、
旧字の右の「豊」は、あまざけの意味、
甘酒を神に捧げて幸福の到来を祈る儀式の意味。
人のふみ行うべきのり。
心の敬意を抱き、それを行動として、外に現わすみち。
作法、礼儀作法、儀式、国家や社会の秩序を維持する組織や掟。
贈り物、敬意を現わすための贈り物。
お礼を尽くす事は、杓子定規なものではなく、
心から滲み出る思いの発露ですから単純なものではなさそうですが、経験や訓練を小さいころから重ねる事が、大人としてそれとなく上手に関係を構築できる最も近く大事な所作です。
難しく考えないで、単純で純粋である事でしょうか。
『礼儀正しさはひとを飾り、しかも金はかからない。イギリスのことわざ』
『どのような防御も礼を尽くすことには及ばない。エドワードルーカス(作家)』
『人はくだらないとして礼儀作法をおざなりにするが、善人か悪人かを礼儀作法で決められることがよくある。ラブリュイエール』
『礼儀正しさが人の本性に訴えかける働きは、熱がロウに伝える働きのごとし。ショーペンハウエル(哲学者)』
「あいつは礼儀知らずな奴」、
「挨拶の仕方も知らないのか」、
などと言われます。
逆に「過ぎる礼儀」もわざとらしく感じてしまいますし、嫌なものです。
たかが礼儀と言われそうですが難しいものですね。
不足は不足でいけませんし、過ぎるは過ぎるで顰蹙ものですし。
爽やかに心置きなく、わだかまりなく、優しく言えるお礼が良いですよね。
困ったことにお礼や礼儀は、早過ぎるのもいけませんし、
遅くて時期を失すると、人間関係を損なう事もあり得ます。
「機を損なうことなく」という事も頭に置かないといけませんからやはり訓練なんでしょうね。
自分がお礼を言われる立場になって考えてみたら、どのようにする事が相手の気持ちを損なうことなく、むしろ関係を深めるお礼の仕方や方法も思いつくかもしれません。
調べてみました。
お礼の旧字は「禮」
左のネは本来は「示」・・・神にいけにえを捧げる台の象形。
人に現わして見せる、教える、告げる、指図する、
旧字の右の「豊」は、あまざけの意味、
甘酒を神に捧げて幸福の到来を祈る儀式の意味。
人のふみ行うべきのり。
心の敬意を抱き、それを行動として、外に現わすみち。
作法、礼儀作法、儀式、国家や社会の秩序を維持する組織や掟。
贈り物、敬意を現わすための贈り物。
お礼を尽くす事は、杓子定規なものではなく、
心から滲み出る思いの発露ですから単純なものではなさそうですが、経験や訓練を小さいころから重ねる事が、大人としてそれとなく上手に関係を構築できる最も近く大事な所作です。
難しく考えないで、単純で純粋である事でしょうか。
『礼儀正しさはひとを飾り、しかも金はかからない。イギリスのことわざ』
『どのような防御も礼を尽くすことには及ばない。エドワードルーカス(作家)』
『人はくだらないとして礼儀作法をおざなりにするが、善人か悪人かを礼儀作法で決められることがよくある。ラブリュイエール』
『礼儀正しさが人の本性に訴えかける働きは、熱がロウに伝える働きのごとし。ショーペンハウエル(哲学者)』
Posted by misterkei0918 at
15:19
│Comments(0)
2011年01月08日
人は本当に変われるの?
人は本当に変われるの?
現状から変わりたい、脱皮を図りたいと思う人、
そんなことを考えた事のない人、
全く変わる必要性を感じない人、
変わりたいと思いながら、行動に移せない人、
行動には移せても結果が見えてこない人、
過去、様々な努力をしたが結果が出ず、悶々としている人、
努力した結果が、結実し見事に変化を経験した人、
元の黙阿弥に戻ってしまった人・・・・・
人は様々、人はそれぞれですから周りからとやかく言う事でも、逆に言われる事でもありませんが世の中にはどうにかして自分を変えたいと思っている人は多いものです。
自分の現状に満足していて、変わる事の必要性が全くない、
或いは傍から見ていてもそのように感じさせる人もいますが、実は本人は変わりたがっているなどという事もあるものです。
変わった原因も、
家族のお陰、
友人知人の影響、
良き師との出会い、
学校、学業のお陰、
就職先、仕事のお陰、
偶然の産物、
結婚相手、
子供のお陰、
宗教、
お金、
発奮材料の出現(例:人前で大恥をかいた・・・)
・
・
・
明らかに変わった人を大勢知っていますがやはり自らが変わろうと意思を固めて辛抱して行動、努力した人が殆どですし、それが永続的に維持できるのも変わった事の喜びを実感し、体験の全てが体の一部として埋め込まれた人々のようです。
一時凌ぎ、その場限り、その場逃れの一過性ではなく心底から変わりたいと思う事、実践を真剣に真摯に取り組んでいる人のこそ、素晴らしい結実をわが物としているようです。
それと、人が変わった暁には新しい世界が待ち受けている事を信じ、行動し実感する事も大事な事のようです。
そして、人間ですからそう安々と変わるものではない事を最初から頭に入れておく事でしょう。
結果が出ないから、すぐ諦めるというような事では変われるものではありませんしそんな簡単なことでは変われるものでもありませんし、あるいは人間と言えないかもしれませんね。
人は変わる事の喜びや実感が出来る経験を重ねると、努力の楽しさや常に明るい未来志向に捕らわれますから歯車の回転スピードが上がっていくものです。
ですから、そのような意欲を以って努力する人とほどほどで満足してしまっている人、身近にある結実を見る事もなく挫折を繰り返す人では、長い人生においては大きな差となって現れてくるものです。
何も急ぐ事はなさそうです。
自分のペースに合わせて、他人と競う事もいらないと私は思っています。
人生は競争でもなく、自分自身をかなぐり捨てて生きていくものでもないと思うからです。
自分の変化のあり方、ペース・・・それを探索する事も人生の楽しみでもあって、自分の個性をより高める方策でもあるような気がするのです。
出ないと、人間が金太郎飴のようになってしまいます。
面白くない人間関係となって、結局は意味のない変化に終始する事にもなってしまいます。
変わるなら、自分らしい変わり方、自分らしい生き方に通じる変化にしたいものですね。
現状から変わりたい、脱皮を図りたいと思う人、
そんなことを考えた事のない人、
全く変わる必要性を感じない人、
変わりたいと思いながら、行動に移せない人、
行動には移せても結果が見えてこない人、
過去、様々な努力をしたが結果が出ず、悶々としている人、
努力した結果が、結実し見事に変化を経験した人、
元の黙阿弥に戻ってしまった人・・・・・
人は様々、人はそれぞれですから周りからとやかく言う事でも、逆に言われる事でもありませんが世の中にはどうにかして自分を変えたいと思っている人は多いものです。
自分の現状に満足していて、変わる事の必要性が全くない、
或いは傍から見ていてもそのように感じさせる人もいますが、実は本人は変わりたがっているなどという事もあるものです。
変わった原因も、
家族のお陰、
友人知人の影響、
良き師との出会い、
学校、学業のお陰、
就職先、仕事のお陰、
偶然の産物、
結婚相手、
子供のお陰、
宗教、
お金、
発奮材料の出現(例:人前で大恥をかいた・・・)
・
・
・
明らかに変わった人を大勢知っていますがやはり自らが変わろうと意思を固めて辛抱して行動、努力した人が殆どですし、それが永続的に維持できるのも変わった事の喜びを実感し、体験の全てが体の一部として埋め込まれた人々のようです。
一時凌ぎ、その場限り、その場逃れの一過性ではなく心底から変わりたいと思う事、実践を真剣に真摯に取り組んでいる人のこそ、素晴らしい結実をわが物としているようです。
それと、人が変わった暁には新しい世界が待ち受けている事を信じ、行動し実感する事も大事な事のようです。
そして、人間ですからそう安々と変わるものではない事を最初から頭に入れておく事でしょう。
結果が出ないから、すぐ諦めるというような事では変われるものではありませんしそんな簡単なことでは変われるものでもありませんし、あるいは人間と言えないかもしれませんね。
人は変わる事の喜びや実感が出来る経験を重ねると、努力の楽しさや常に明るい未来志向に捕らわれますから歯車の回転スピードが上がっていくものです。
ですから、そのような意欲を以って努力する人とほどほどで満足してしまっている人、身近にある結実を見る事もなく挫折を繰り返す人では、長い人生においては大きな差となって現れてくるものです。
何も急ぐ事はなさそうです。
自分のペースに合わせて、他人と競う事もいらないと私は思っています。
人生は競争でもなく、自分自身をかなぐり捨てて生きていくものでもないと思うからです。
自分の変化のあり方、ペース・・・それを探索する事も人生の楽しみでもあって、自分の個性をより高める方策でもあるような気がするのです。
出ないと、人間が金太郎飴のようになってしまいます。
面白くない人間関係となって、結局は意味のない変化に終始する事にもなってしまいます。
変わるなら、自分らしい変わり方、自分らしい生き方に通じる変化にしたいものですね。
Posted by misterkei0918 at
09:44
│Comments(0)
2011年01月07日
おもてなし(ホスピタリティ)を求めて・・・大晦日と元旦
おもてなし(ホスピタリティ)を求めて・・・大晦日と元旦
おもてなし(ホスピタリティ)と言えば、世界のリッツカールトンをすぐ頭に浮かべます。
一度、日本法人の支配人さんの話を直にお聞きする機会がありましたが、それはそれは「そこまでやるか」という感じでした。
何しろ世界一ですから、ちょっとやそっとのおもてなしでは話になりませんよね。
私どもの企業でも、その付近への配慮が働いてお客様から「あの会社は、他とどこかが違うよね」などと囁かれると嬉しいものです。
お店や会社へ一歩足を踏み入れた途端に、その違いは感じるものです。
という事は、俄かづくりや表向きだけのおもてなしなどすぐ化けの皮が剥げてしまいます。
不思議なものです。
人間の感覚というものは。
大晦日から元旦にかけて毎年同じ宿に宿泊することにしています。
それもやはり一年間のご褒美の意味もありますが、一番は「おもてなし」の心地よい雰囲気に浸るのが目的です。
温泉も雰囲気がありますし、食事の美味しさや細かい配慮、部屋の面持ち・・・・・
自宅で大晦日や新年を迎える事になると、当然それなりの準備も必要ですし、おせちも造ることになってしまいますから家内に大いに負担をかける事にもなってしまいますから、それからの解放の意味もありますが。
場所は、大分県中津市、福沢諭吉の故郷ですし、黒田長政の父親・黒田如水が藩主であり中津城主(日本三大水城の一つ)であった所でもあります。
中津市の山間部、六面山ふところ。
金色温泉・こがね山荘。
隣には、地域の方々も入れる温泉地。
福岡から九州縦貫道を経由し、東九州道路を利用して約2時間程度の道程です。
また、今年の大晦日から元旦にかけて再び訪れる事になります。
おもてなし(ホスピタリティ)と言えば、世界のリッツカールトンをすぐ頭に浮かべます。
一度、日本法人の支配人さんの話を直にお聞きする機会がありましたが、それはそれは「そこまでやるか」という感じでした。
何しろ世界一ですから、ちょっとやそっとのおもてなしでは話になりませんよね。
私どもの企業でも、その付近への配慮が働いてお客様から「あの会社は、他とどこかが違うよね」などと囁かれると嬉しいものです。
お店や会社へ一歩足を踏み入れた途端に、その違いは感じるものです。
という事は、俄かづくりや表向きだけのおもてなしなどすぐ化けの皮が剥げてしまいます。
不思議なものです。
人間の感覚というものは。
大晦日から元旦にかけて毎年同じ宿に宿泊することにしています。
それもやはり一年間のご褒美の意味もありますが、一番は「おもてなし」の心地よい雰囲気に浸るのが目的です。
温泉も雰囲気がありますし、食事の美味しさや細かい配慮、部屋の面持ち・・・・・
自宅で大晦日や新年を迎える事になると、当然それなりの準備も必要ですし、おせちも造ることになってしまいますから家内に大いに負担をかける事にもなってしまいますから、それからの解放の意味もありますが。
場所は、大分県中津市、福沢諭吉の故郷ですし、黒田長政の父親・黒田如水が藩主であり中津城主(日本三大水城の一つ)であった所でもあります。
中津市の山間部、六面山ふところ。
金色温泉・こがね山荘。
隣には、地域の方々も入れる温泉地。
福岡から九州縦貫道を経由し、東九州道路を利用して約2時間程度の道程です。
また、今年の大晦日から元旦にかけて再び訪れる事になります。
Posted by misterkei0918 at
23:07
│Comments(0)
2011年01月07日
一日一笑、一日一善、一日一役、一日一褒
一日一笑、一日一善、一日一役、一日一褒
今日1日、何か心に残るような出来事はありましたか?
今日1日、お腹から笑う事がありましたか?
今日1日、人に喜んで貰う事が出来ましたか?
今日1日、家族や周りの人々、社会に何か良い事をしてあげられましたか?
今日1日、自信を以って「良くやった」と言えるような事がありましたか?
今日1日、最後に自分を褒めてあげましょう。
いつも走り回る1日に終始してしまいます。
そしていつも反省です。
小さな事でもいいのです、
一日の終わりには心地よい達成感に酔いしれて、
腹に一物を持つことなく、大きな声で笑ってみたいものですね。
人の為に何をしたのか、自己犠牲とまではいかなくても、
或いは感謝はされないかもしれませんが、果たしてお役に立てた事があったのでしょうか。
「最善を尽くして、天命を待つ」という言葉がありますが、最善ではなかったかもしれませんが自分が為し得る努力を怠る事はなかったでしょうか。
褒められなくてもいいのです、素晴らしい評価など必要はありません。
第3者が見ても、確かな結果が残せたのでしょうか。
今日の自分は、心の鏡に照らしてみて、美しく輝いているのでしょうか。
曇ってはいませんか。
眉間に皺寄せるような事はなかったですよね。
最後に、心地よい疲れとともに、体を横たえるとき、自らに「良く頑張ったね」と優しく囁いてあげたいものです。
人は、悲しいかな、
反省などという習性を本能的に備えてしまいました。
生きて行くからには、せめて明日の為に心地よい反省で一日を終わりたいものです。
『多くの人は皆、成功を夢見、望んでいますが、私は「成功は、99パーセントの失敗に支えられた1パーセントだ」と思っています。
開拓精神によって自ら新しい世界に挑み、失敗反省勇気という3つの道具を繰り返して使うことによってのみ、最後の成功という結果に達することができると私は信じています。本田宗一郎』
『進歩とは反省のきびしさに正比例する。本田宗一郎』
『反省とは悔やむことではない。前進するための土台である。』
今日1日、何か心に残るような出来事はありましたか?
今日1日、お腹から笑う事がありましたか?
今日1日、人に喜んで貰う事が出来ましたか?
今日1日、家族や周りの人々、社会に何か良い事をしてあげられましたか?
今日1日、自信を以って「良くやった」と言えるような事がありましたか?
今日1日、最後に自分を褒めてあげましょう。
いつも走り回る1日に終始してしまいます。
そしていつも反省です。
小さな事でもいいのです、
一日の終わりには心地よい達成感に酔いしれて、
腹に一物を持つことなく、大きな声で笑ってみたいものですね。
人の為に何をしたのか、自己犠牲とまではいかなくても、
或いは感謝はされないかもしれませんが、果たしてお役に立てた事があったのでしょうか。
「最善を尽くして、天命を待つ」という言葉がありますが、最善ではなかったかもしれませんが自分が為し得る努力を怠る事はなかったでしょうか。
褒められなくてもいいのです、素晴らしい評価など必要はありません。
第3者が見ても、確かな結果が残せたのでしょうか。
今日の自分は、心の鏡に照らしてみて、美しく輝いているのでしょうか。
曇ってはいませんか。
眉間に皺寄せるような事はなかったですよね。
最後に、心地よい疲れとともに、体を横たえるとき、自らに「良く頑張ったね」と優しく囁いてあげたいものです。
人は、悲しいかな、
反省などという習性を本能的に備えてしまいました。
生きて行くからには、せめて明日の為に心地よい反省で一日を終わりたいものです。
『多くの人は皆、成功を夢見、望んでいますが、私は「成功は、99パーセントの失敗に支えられた1パーセントだ」と思っています。
開拓精神によって自ら新しい世界に挑み、失敗反省勇気という3つの道具を繰り返して使うことによってのみ、最後の成功という結果に達することができると私は信じています。本田宗一郎』
『進歩とは反省のきびしさに正比例する。本田宗一郎』
『反省とは悔やむことではない。前進するための土台である。』
Posted by misterkei0918 at
21:36
│Comments(0)
2011年01月07日
突然の七草粥を頂きました
突然の七草粥を頂きました
今日の夕刻と明日の賀詞交歓会で、所謂「新年会」が終わります。
ある意味、大人の踏み絵のような、体力気力を試されているような、そんな集まりのような気がします。
それは多分、私だけの感情ではなく参加する多くの方々の偽わざる思いではないでしょうか。
中には、好きなお酒が好きなだけ飲めるという期待を以って臨む人も多いのも事実ですが。
今日のお昼の賀詞交歓会の来賓の方のご挨拶で今日が「七草粥」の日である事を気付きました。
昔は、「今日は七草粥だね」などと口々に話したものです。
また、社内でも七草をスーパー等で買い求めて、みんなで頂いた時もあったものです。
本来大事な、季節を感じる行事ですのでみんなで語り合ったり、出来れば頂いたりしたいものですね。
その付近が日本人の素晴らしい所だった筈です。
調べてみました。(ネットからの拝借です)
************************
七草(ななくさ)は、人日(じんじつ:五節句の一つ)の節句(1月7日)の朝に、7種の野菜が入った羮を食べる風習のこと。
本来は七草と書いた場合は秋の七草を指し、小正月1月15日のものも七種と書いて「ななくさ」と読むが、一般には7日正月のものが七草と書かれる。
芹(せり)、薺(なずな)、御形(ごぎょう・現在名:母子草)、
繁縷(はこべら・現在名:ハコベ)、
仏の座(ほとけのざ・現在名:コオニタビラコ)
菘(すずな・現在名:カブ)、蘿蔔(すずしろ・現在名:大根)
この7種の野菜を刻んで入れたかゆを七種がゆといい、邪気を払い万病を除く占いとして食べる。呪術的な意味ばかりでなく、御節料理で疲れた胃を休め、野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄養素を補うという効能もある。
*************************
実は、ご挨拶の言葉に登場したのみでまさか七草粥が出てくるとは思わなかったのです。
いつものパーティでしたら、お蕎麦がお椀に継がれて出てくる事はいつもの事ですが。
いずれにしても、旬の季節の食べ物に触れただけでも嬉しい気分になっています。
今年は何か良い事が。
そういえば、昨夜の賀詞交歓会で実は景品が当たったのですが、これも幸先(さいさき)を暗示しているようで喜びのひと時でした。
でも、当たっていない同僚たちのまなざしが痛かった!!
そういう事でもありましたので、喜びは自分だけが占有してはいけませんから、博多駅に迎えに来てくれた社員の家族にお礼を兼ねて差し上げることにしました。
今日の夕刻と明日の賀詞交歓会で、所謂「新年会」が終わります。
ある意味、大人の踏み絵のような、体力気力を試されているような、そんな集まりのような気がします。
それは多分、私だけの感情ではなく参加する多くの方々の偽わざる思いではないでしょうか。
中には、好きなお酒が好きなだけ飲めるという期待を以って臨む人も多いのも事実ですが。
今日のお昼の賀詞交歓会の来賓の方のご挨拶で今日が「七草粥」の日である事を気付きました。
昔は、「今日は七草粥だね」などと口々に話したものです。
また、社内でも七草をスーパー等で買い求めて、みんなで頂いた時もあったものです。
本来大事な、季節を感じる行事ですのでみんなで語り合ったり、出来れば頂いたりしたいものですね。
その付近が日本人の素晴らしい所だった筈です。
調べてみました。(ネットからの拝借です)
************************
七草(ななくさ)は、人日(じんじつ:五節句の一つ)の節句(1月7日)の朝に、7種の野菜が入った羮を食べる風習のこと。
本来は七草と書いた場合は秋の七草を指し、小正月1月15日のものも七種と書いて「ななくさ」と読むが、一般には7日正月のものが七草と書かれる。
芹(せり)、薺(なずな)、御形(ごぎょう・現在名:母子草)、
繁縷(はこべら・現在名:ハコベ)、
仏の座(ほとけのざ・現在名:コオニタビラコ)
菘(すずな・現在名:カブ)、蘿蔔(すずしろ・現在名:大根)
この7種の野菜を刻んで入れたかゆを七種がゆといい、邪気を払い万病を除く占いとして食べる。呪術的な意味ばかりでなく、御節料理で疲れた胃を休め、野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄養素を補うという効能もある。
*************************
実は、ご挨拶の言葉に登場したのみでまさか七草粥が出てくるとは思わなかったのです。
いつものパーティでしたら、お蕎麦がお椀に継がれて出てくる事はいつもの事ですが。
いずれにしても、旬の季節の食べ物に触れただけでも嬉しい気分になっています。
今年は何か良い事が。
そういえば、昨夜の賀詞交歓会で実は景品が当たったのですが、これも幸先(さいさき)を暗示しているようで喜びのひと時でした。
でも、当たっていない同僚たちのまなざしが痛かった!!
そういう事でもありましたので、喜びは自分だけが占有してはいけませんから、博多駅に迎えに来てくれた社員の家族にお礼を兼ねて差し上げることにしました。
Posted by misterkei0918 at
14:55
│Comments(0)
2011年01月07日
過去の栄光の亡霊に心奪われては駄目
過去の栄光の亡霊に心奪われては駄目
新年を迎えた早々に、過去の話に終始するのはどうかとも思います。
或いは新年を迎えた時期だからこそ、自戒を込めて考えてみるのもいいかもしれませんね。
私自身に過去の栄光などと言われるものが存在するかも疑問ですが、それは私個人の胸の内で「あのときがそうだった」位の判断でいいのではないかと思っています。
例えば、
大企業に就職できたこと、
恋愛が成就し結婚まで辿り着いたこと、
首尾よく起業出来た事、
ここまで数十年に亘って経営できた事、
難しい時代にも関わらず、そこそこの事業として確立できたこと、
孫も順調に育ち、親族仲良く過ごせている事、
・
・
確かに人生は波乱万丈、さまざまな事がありました。
眠れない日を幾度となく迎えた事もありますし、自己否定をしてみたり、涙をぬぐってみたり・・・・・
でも、そのそれぞれが現在を構築するための踏み台であって、どうしても必要なものであったような気がします。
そして数少ない栄光も存在するものです。
「良くもここまで頑張ったとか」
「若しかすると奇跡じゃないの」
こんな時も存在するものです。
でも栄光に浮かれていても、殆ど得るものはありませんでしたしむしろそれが為に足かせになって身動きが取れないときが多いものです。
しかも喜びの絶頂期は、栄光に浸っている時ではなく苦難を克服した時や悲しみを乗り越えたときであったのです。
安堵感や充実感に浸れる時は、苦難を克服した時や悲しみを乗り越えたときであって、栄光の時ではないようです。
栄光は過去の遺産や亡霊ぐらいに思って、むしろ苦難を経験した道程こそ大事にし、かつ振り返る価値がありそうです。
経営をしていて、「柳の下にドジョウが2匹」いたためしは殆どありませんでしたが、そんな時に限って過去に執着し旨い話に心を奪われ、迷いや失敗を招いていたような気がします。
経験、特に成功体験や栄光に心を奪われることなく、謙虚に常に初心を見つめ、自分を戒め厳しく、嗜(たしな)めながらの生涯にしたいものです。
心休まる時はなかなか見いだせませんが、そんな厳しさの中に時々垣間見せる至福の時を大切にしながら・・・・・
『小生の最大の栄光は、一度も失敗しなかったことにあるのではなく、倒れるたびに起き上がることにある。ゴールドスミス』
新年を迎えた早々に、過去の話に終始するのはどうかとも思います。
或いは新年を迎えた時期だからこそ、自戒を込めて考えてみるのもいいかもしれませんね。
私自身に過去の栄光などと言われるものが存在するかも疑問ですが、それは私個人の胸の内で「あのときがそうだった」位の判断でいいのではないかと思っています。
例えば、
大企業に就職できたこと、
恋愛が成就し結婚まで辿り着いたこと、
首尾よく起業出来た事、
ここまで数十年に亘って経営できた事、
難しい時代にも関わらず、そこそこの事業として確立できたこと、
孫も順調に育ち、親族仲良く過ごせている事、
・
・
確かに人生は波乱万丈、さまざまな事がありました。
眠れない日を幾度となく迎えた事もありますし、自己否定をしてみたり、涙をぬぐってみたり・・・・・
でも、そのそれぞれが現在を構築するための踏み台であって、どうしても必要なものであったような気がします。
そして数少ない栄光も存在するものです。
「良くもここまで頑張ったとか」
「若しかすると奇跡じゃないの」
こんな時も存在するものです。
でも栄光に浮かれていても、殆ど得るものはありませんでしたしむしろそれが為に足かせになって身動きが取れないときが多いものです。
しかも喜びの絶頂期は、栄光に浸っている時ではなく苦難を克服した時や悲しみを乗り越えたときであったのです。
安堵感や充実感に浸れる時は、苦難を克服した時や悲しみを乗り越えたときであって、栄光の時ではないようです。
栄光は過去の遺産や亡霊ぐらいに思って、むしろ苦難を経験した道程こそ大事にし、かつ振り返る価値がありそうです。
経営をしていて、「柳の下にドジョウが2匹」いたためしは殆どありませんでしたが、そんな時に限って過去に執着し旨い話に心を奪われ、迷いや失敗を招いていたような気がします。
経験、特に成功体験や栄光に心を奪われることなく、謙虚に常に初心を見つめ、自分を戒め厳しく、嗜(たしな)めながらの生涯にしたいものです。
心休まる時はなかなか見いだせませんが、そんな厳しさの中に時々垣間見せる至福の時を大切にしながら・・・・・
『小生の最大の栄光は、一度も失敗しなかったことにあるのではなく、倒れるたびに起き上がることにある。ゴールドスミス』
Posted by misterkei0918 at
10:16
│Comments(0)
2011年01月06日
やはり生身の人間だった
やはり生身の人間だった
自分は、「体力には自信がある」と言いながら、早くに命を落としたり、
「精神力では人に負けない」などと言いながら、いつの間にか精神的な病いに襲われていたり、萎えていたりする事は良く耳にします。
誰でも自分は違うと思っているんですよね。
しかも体と心が連動しているなど、その経験をしてみないと理解は難しいかもしれません。
かといって、こればかりは経験を積み重ねる事も出来ませんので、独りよがりな考えに終始せず、いろんな方の話にしっかり耳を貸すという事でしょうね。
つい、体が健康で丈夫だと
「自分は違う、自分は例外」
「それは他人の話であって、自分にそんな事はあり得ないし、あっても問題はない」
などと終始してしまうものです。
しかし病は、
他から持ち込まれる事もありますし、事件、事故だってあり得ます。
また、心の関係から体が蝕まれる事もしばしばです。
一方、
体が萎(な)えてしまうと、不思議なもので心まで萎え萎(しぼ)んでしまうものです。
今度、そんな経験をしてしまいました。
決して他人ごとではなかったし、私自身も実は生身の人間であることを知る結果となりました。
昨年の暮は、数度、実は4回も日赤の救急に飛び込む体(てい)たらくでした。
私にとっては、想像外、あり得ない事だったのです。
極めつけは晦日の30日。
実は帯状発疹の痛みに耐えかねて既に休診になっている日赤の救急のお世話になってしまいました。
帯状発疹は「胴巻き」とも言われ、体を発疹が取り巻くと命を失う(今では殆どそんな事はないのですが)とも昔は聞かされたものです。
水疱瘡(みずぼうそう)のウイルスが体の神経節等に潜んでいて、体調が悪い時、疲れた時などに表面化して暴れる症状で人によって現れる場所や症状が事なり、しかも痛みや痒みを伴う困った症状です。
これも「自分は疲れ知らず」などと自慢げに話していても、体は正直なもの。
或いは警告を発しているのかもしれませんね。
私自身も、自分にはあり得ないと思っていましたし、他人事にしか考えていませんでしたが自分の身に引き起こってみると「やはり生身の人間だった」事につい思いが馳せてしまいます。
残念なことですが。
かといって、ゆっくりのんびりする事は自分が許せませんので従来通りの行動パターンに戻るのでしょうが。
でも、そんな事も現実にはあり得ることを認識していないととんでもない事にもなってしまいますよね。
反省!!反省!!
自分は、「体力には自信がある」と言いながら、早くに命を落としたり、
「精神力では人に負けない」などと言いながら、いつの間にか精神的な病いに襲われていたり、萎えていたりする事は良く耳にします。
誰でも自分は違うと思っているんですよね。
しかも体と心が連動しているなど、その経験をしてみないと理解は難しいかもしれません。
かといって、こればかりは経験を積み重ねる事も出来ませんので、独りよがりな考えに終始せず、いろんな方の話にしっかり耳を貸すという事でしょうね。
つい、体が健康で丈夫だと
「自分は違う、自分は例外」
「それは他人の話であって、自分にそんな事はあり得ないし、あっても問題はない」
などと終始してしまうものです。
しかし病は、
他から持ち込まれる事もありますし、事件、事故だってあり得ます。
また、心の関係から体が蝕まれる事もしばしばです。
一方、
体が萎(な)えてしまうと、不思議なもので心まで萎え萎(しぼ)んでしまうものです。
今度、そんな経験をしてしまいました。
決して他人ごとではなかったし、私自身も実は生身の人間であることを知る結果となりました。
昨年の暮は、数度、実は4回も日赤の救急に飛び込む体(てい)たらくでした。
私にとっては、想像外、あり得ない事だったのです。
極めつけは晦日の30日。
実は帯状発疹の痛みに耐えかねて既に休診になっている日赤の救急のお世話になってしまいました。
帯状発疹は「胴巻き」とも言われ、体を発疹が取り巻くと命を失う(今では殆どそんな事はないのですが)とも昔は聞かされたものです。
水疱瘡(みずぼうそう)のウイルスが体の神経節等に潜んでいて、体調が悪い時、疲れた時などに表面化して暴れる症状で人によって現れる場所や症状が事なり、しかも痛みや痒みを伴う困った症状です。
これも「自分は疲れ知らず」などと自慢げに話していても、体は正直なもの。
或いは警告を発しているのかもしれませんね。
私自身も、自分にはあり得ないと思っていましたし、他人事にしか考えていませんでしたが自分の身に引き起こってみると「やはり生身の人間だった」事につい思いが馳せてしまいます。
残念なことですが。
かといって、ゆっくりのんびりする事は自分が許せませんので従来通りの行動パターンに戻るのでしょうが。
でも、そんな事も現実にはあり得ることを認識していないととんでもない事にもなってしまいますよね。
反省!!反省!!
Posted by misterkei0918 at
08:19
│Comments(0)
2011年01月05日
またもや救急へ
またもや救急へ
年末の30日、また日赤の救急のお世話になる事になってしまいました。
26日の早朝、いつものように大濠公園のウォーキングです。
どうも左肩が可笑しいのです。
いつぞや経験した50肩の再来かと思ったほどです。
筋肉の痛みとか、傷の痛みでない事は多くの経験から素人の私でも分かります。
確かに痛みそのものは神経性。
その後、変だと思いながら数日が経過した29日夜。
体に何かしら痒みが感じられるようになってきました。
しかもそれが左胸から、左背中。
直感です。
「帯状発疹」
とうとう30日の朝に日赤へ飛び込む始末です。
当然、年末の30日ですから、通常の診察体制ではありませんでした。
11月の初旬に3度も日赤の救急にお世話になっていますからどうも常連になったようで困ったものです。
救急ですから当然皮膚科の先生は居られません。
どうも整形外科の先生らしく、
私が「先生、どうも帯状発疹のようです」
と、申しあげたら、
「どうもそのようですね」との診察。
飲み薬と塗り薬を頂いて帰宅。
2か月以内の救急ですから、家族もあきれ顔。
仕方ありません。
振り返ってみたら、
今年は、やはり無理なスケジュールで動いていたんですね。
体は疲れを感じていたわけでもなく、いつもの通りだと思っていたのですがやはり疲れが蓄積していたのでしょう。
先生から「当分の間、安静ですよ」
などと言われてしまいました。
年末の30日、また日赤の救急のお世話になる事になってしまいました。
26日の早朝、いつものように大濠公園のウォーキングです。
どうも左肩が可笑しいのです。
いつぞや経験した50肩の再来かと思ったほどです。
筋肉の痛みとか、傷の痛みでない事は多くの経験から素人の私でも分かります。
確かに痛みそのものは神経性。
その後、変だと思いながら数日が経過した29日夜。
体に何かしら痒みが感じられるようになってきました。
しかもそれが左胸から、左背中。
直感です。
「帯状発疹」
とうとう30日の朝に日赤へ飛び込む始末です。
当然、年末の30日ですから、通常の診察体制ではありませんでした。
11月の初旬に3度も日赤の救急にお世話になっていますからどうも常連になったようで困ったものです。
救急ですから当然皮膚科の先生は居られません。
どうも整形外科の先生らしく、
私が「先生、どうも帯状発疹のようです」
と、申しあげたら、
「どうもそのようですね」との診察。
飲み薬と塗り薬を頂いて帰宅。
2か月以内の救急ですから、家族もあきれ顔。
仕方ありません。
振り返ってみたら、
今年は、やはり無理なスケジュールで動いていたんですね。
体は疲れを感じていたわけでもなく、いつもの通りだと思っていたのですがやはり疲れが蓄積していたのでしょう。
先生から「当分の間、安静ですよ」
などと言われてしまいました。
Posted by misterkei0918 at
21:51
│Comments(0)