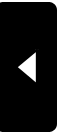2010年06月10日
大切の法則
大切の法則
そんな法則は聞いたことがありません。
でも、最近読んだ本「ザ・シークレット」には引き寄せの法則が細かく記載されていました。
であるならばと「大切の法則」と名づけてみました。
こんな文章を発見しました。
**********
『「大切にすると集まってくる」という法則があります。
人を大切にすれば人が集まってきます。
物を大切にすれば物が集まってきますし、
時間を大切にすれば時間が集まってきます。
今、与えられているところを大切に生きることが実り豊かな人生の秘訣のようです。
まずは自分自身を大切にしましょう。
あなたのまわりに幸せが集まってきます』。
* *********
確かにそうです。
大切にしようとする気持ちに魔法が備わっているようにも感じます。
以心伝心とも言います。
物を大切に思う心が物に伝わるのかも知れません。
人を大切にしたいと思う心も確実に伝わるものです。
逆もありますよね。
怨念がそうでしょう。
怨念は怨念を呼び、不幸のサイクルを作り、泥沼の坩堝を作ってしまいます。
這い上がることは容易な事ではありません。
むしろ地獄への坂道を滑り落ちる原因のようなものです。
物には心は無さそうに思えますが、そんな事はありません。
路傍の石にだって、照りつける太陽にだって、踏みつけられる草木や雑草にさえ心がありそうな気がします。
物や人を大切にする思い、大事に扱う姿勢はいつしか自分へ跳ね返って来ることを実感するものです。
世の中は不思議なことに覆われています。
今だって、その不思議なことの具現かも知れないのです。
そんな法則は聞いたことがありません。
でも、最近読んだ本「ザ・シークレット」には引き寄せの法則が細かく記載されていました。
であるならばと「大切の法則」と名づけてみました。
こんな文章を発見しました。
**********
『「大切にすると集まってくる」という法則があります。
人を大切にすれば人が集まってきます。
物を大切にすれば物が集まってきますし、
時間を大切にすれば時間が集まってきます。
今、与えられているところを大切に生きることが実り豊かな人生の秘訣のようです。
まずは自分自身を大切にしましょう。
あなたのまわりに幸せが集まってきます』。
* *********
確かにそうです。
大切にしようとする気持ちに魔法が備わっているようにも感じます。
以心伝心とも言います。
物を大切に思う心が物に伝わるのかも知れません。
人を大切にしたいと思う心も確実に伝わるものです。
逆もありますよね。
怨念がそうでしょう。
怨念は怨念を呼び、不幸のサイクルを作り、泥沼の坩堝を作ってしまいます。
這い上がることは容易な事ではありません。
むしろ地獄への坂道を滑り落ちる原因のようなものです。
物には心は無さそうに思えますが、そんな事はありません。
路傍の石にだって、照りつける太陽にだって、踏みつけられる草木や雑草にさえ心がありそうな気がします。
物や人を大切にする思い、大事に扱う姿勢はいつしか自分へ跳ね返って来ることを実感するものです。
世の中は不思議なことに覆われています。
今だって、その不思議なことの具現かも知れないのです。
Posted by misterkei0918 at
18:02
│Comments(1)
2010年06月10日
過去は神様が与えたもので、未来こそは自らが決める
過去は神様が与えたもので、未来こそは自らが決める
人は過去に囚われるとそれに就縛(しゅうばく)をされ、思い切った決断ができなくなったり、勇気を損なったりするものです
成功した過去体験にのみ執着するとつい慢心につながり、自己過信や他人の意見に耳を貸さないワンマン、独善的な判断、足元を見ない決断や人を見下げた人間性を持ち合わすことにもなりかねません。
失敗を繰り返す、トラウマ的な体験は人を萎縮させ、大切な決断をさえも先延ばしを促し折角の貴重な機会さえも失い、表情も暗いものとなり笑顔を捨てさってしまい、人との関係さえも冴えない環境に押しやって仕舞います。
そんな事はあり得ないという人もいるかも知れませんが。
少なくとも私のような小心者は、成功体験は如何にも我が意を得たりとばかりに有頂天になってしまいますし、失敗は意気消沈し、周りをも取り込んで暗い雰囲気を醸し出し、先への思いも憂愁不断の坩堝に嵌(はま)ってしまいます。
何事も、出来れば過去は過去、これからはこれからと割り切った方が良さそうです。
「過去は神様が与えたもので、未来こそは自らが決める」
つまり、割り切った思い、吹っ切れた状態、解き放たれた思い・・・・・
あまり過去に拘泥しない、左右されない・・・・・
失敗の極みを抱えた過去であっても、成功の連続であった過去も「あれは神様が与えてくれたもの。事前に決めていただいたもの」
これからこそ「自らが決める未来」。
新しい物事の出発点は、また新たなスタート地点に立ち望むような素直な気持ちになることが大切ではないでしょうか。
慢心や自己過信、過大な自己評価は決していい結果には結びつきませんし、
また過去を苦い体験は繰り返すのではないかとの恐れや気持ちの萎縮を齎し、自由な発想や思い切った決断を鈍らせてしまいます。
昔から「成功体験に学ばず、歴史に学びなさい」と良く言われました。
そうかも知れませんね。
自らの体験は偶然やたまたま、周りからの影響、時代の置かれた状況・・・・・
普遍的で確率の高い成功体験をしたければ、できるだけそのようなものを排除して考える方がいいのかも知れませんね。
当然、物事の成功は努力の賜物であることも充分承知した上で。
人は過去に囚われるとそれに就縛(しゅうばく)をされ、思い切った決断ができなくなったり、勇気を損なったりするものです
成功した過去体験にのみ執着するとつい慢心につながり、自己過信や他人の意見に耳を貸さないワンマン、独善的な判断、足元を見ない決断や人を見下げた人間性を持ち合わすことにもなりかねません。
失敗を繰り返す、トラウマ的な体験は人を萎縮させ、大切な決断をさえも先延ばしを促し折角の貴重な機会さえも失い、表情も暗いものとなり笑顔を捨てさってしまい、人との関係さえも冴えない環境に押しやって仕舞います。
そんな事はあり得ないという人もいるかも知れませんが。
少なくとも私のような小心者は、成功体験は如何にも我が意を得たりとばかりに有頂天になってしまいますし、失敗は意気消沈し、周りをも取り込んで暗い雰囲気を醸し出し、先への思いも憂愁不断の坩堝に嵌(はま)ってしまいます。
何事も、出来れば過去は過去、これからはこれからと割り切った方が良さそうです。
「過去は神様が与えたもので、未来こそは自らが決める」
つまり、割り切った思い、吹っ切れた状態、解き放たれた思い・・・・・
あまり過去に拘泥しない、左右されない・・・・・
失敗の極みを抱えた過去であっても、成功の連続であった過去も「あれは神様が与えてくれたもの。事前に決めていただいたもの」
これからこそ「自らが決める未来」。
新しい物事の出発点は、また新たなスタート地点に立ち望むような素直な気持ちになることが大切ではないでしょうか。
慢心や自己過信、過大な自己評価は決していい結果には結びつきませんし、
また過去を苦い体験は繰り返すのではないかとの恐れや気持ちの萎縮を齎し、自由な発想や思い切った決断を鈍らせてしまいます。
昔から「成功体験に学ばず、歴史に学びなさい」と良く言われました。
そうかも知れませんね。
自らの体験は偶然やたまたま、周りからの影響、時代の置かれた状況・・・・・
普遍的で確率の高い成功体験をしたければ、できるだけそのようなものを排除して考える方がいいのかも知れませんね。
当然、物事の成功は努力の賜物であることも充分承知した上で。
Posted by misterkei0918 at
09:02
│Comments(0)
2010年06月09日
良寛さんに学ぶ言動の様々
良寛さんに学ぶ言動の様々
以前にも良寛さんの下記の言葉をブログしたことがあります、
時々、思い出すことが大事ですよね。
例えブログで書いても一過性ではなくて時々振り返って、自分の反省材料としたり、戒めたり。
昔の方々の生き方は大いに勉強に、参考になります。
最近はできるだけ機会を作って一人でも多くの偉人たちの言葉やその生涯に触れたりしています。
昨日は、福岡市中央区平尾山荘に居を構え、維新の志士達を匿った事で知られる「野村望東尼」さんを学んできました。
私のことですから、覚えが悪く忘れやすく、一度や二度では理解し切れない頭ですので、繰り返し繰り返し勉強しないと人並みになりませんので困ったものです。
今日は良寛禅師さんの言葉をお借りしました。
心当たりのあることばかりで反省しきりです。
良寛さんは江戸後期の禅僧で歌人。
出家して諸国を行脚し各地に漂白転住。
のちに故郷の越後・国上山の五合庵に定住され、脱俗的な一生を送った。
和歌、俳句、書、詩に秀でておられ、生き方に通じる天衣無縫さが特徴のお方であった。
1、 こと多き(言葉の多い事)
2、 口のはやき
3、 話のながき
4、 手柄ばなし
5、 講釈のながき
6、 物言いのはてしなき
7、
8、 人の物言い切らぬうちに物言う
9、 人の話の邪魔をする
10、 さしたる事もなきことをこまごまという
11、 物知り顔に言う
12、 好んで唐言葉を使う
13、 都言葉を覚えて、したり顔に言う
14、 よく知らぬことを憚(はばか)りなく言う
15、 若者の無駄話
16、 見る事聞く事一つひとつ言う
17、 推し量りのことをまことにしていう
18、 さしで口
19、 よく心得ぬことを人に教える
20、 悪しきと知りながら言い通す
比較的軽妙な表現をされていますが、完結で単刀直入な表現をされていますので受け入れやすく、つい納得してしまいます。
やはり良寛さんのお人柄なのでしょうね。
人を諭(さと)すことの上手な人というのは良寛さんのような方の事を指すのでしょうね。
昔も今も変わらないものですね。
時代が違うと入っても人間としてのあり方は普遍的なものであるようです。
ですから、良く先人に学べと言われるのでしょう。
以前にも良寛さんの下記の言葉をブログしたことがあります、
時々、思い出すことが大事ですよね。
例えブログで書いても一過性ではなくて時々振り返って、自分の反省材料としたり、戒めたり。
昔の方々の生き方は大いに勉強に、参考になります。
最近はできるだけ機会を作って一人でも多くの偉人たちの言葉やその生涯に触れたりしています。
昨日は、福岡市中央区平尾山荘に居を構え、維新の志士達を匿った事で知られる「野村望東尼」さんを学んできました。
私のことですから、覚えが悪く忘れやすく、一度や二度では理解し切れない頭ですので、繰り返し繰り返し勉強しないと人並みになりませんので困ったものです。
今日は良寛禅師さんの言葉をお借りしました。
心当たりのあることばかりで反省しきりです。
良寛さんは江戸後期の禅僧で歌人。
出家して諸国を行脚し各地に漂白転住。
のちに故郷の越後・国上山の五合庵に定住され、脱俗的な一生を送った。
和歌、俳句、書、詩に秀でておられ、生き方に通じる天衣無縫さが特徴のお方であった。
1、 こと多き(言葉の多い事)
2、 口のはやき
3、 話のながき
4、 手柄ばなし
5、 講釈のながき
6、 物言いのはてしなき
7、
8、 人の物言い切らぬうちに物言う
9、 人の話の邪魔をする
10、 さしたる事もなきことをこまごまという
11、 物知り顔に言う
12、 好んで唐言葉を使う
13、 都言葉を覚えて、したり顔に言う
14、 よく知らぬことを憚(はばか)りなく言う
15、 若者の無駄話
16、 見る事聞く事一つひとつ言う
17、 推し量りのことをまことにしていう
18、 さしで口
19、 よく心得ぬことを人に教える
20、 悪しきと知りながら言い通す
比較的軽妙な表現をされていますが、完結で単刀直入な表現をされていますので受け入れやすく、つい納得してしまいます。
やはり良寛さんのお人柄なのでしょうね。
人を諭(さと)すことの上手な人というのは良寛さんのような方の事を指すのでしょうね。
昔も今も変わらないものですね。
時代が違うと入っても人間としてのあり方は普遍的なものであるようです。
ですから、良く先人に学べと言われるのでしょう。
Posted by misterkei0918 at
17:44
│Comments(0)
2010年06月08日
逆境の真骨頂はここ一番に発揮される?
逆境の真骨頂はここ一番に発揮される?
自らが逆境に立たされていると思えば、気持ちが萎(な)えてしまう人、
だからこそと奮起して、逆境からのし上がっていく人、
或いは逆境を逆境とも思わない人・・・・・
人の本当の姿など、他人がわかるわけがありません。
殆どの人は自らが逆境の最中にあると思っていますし、それを悔やんでいるものです。
所が本当に逆境に置かれている人は僅かだと思うのです。
日本人の特性で、自虐的なところがありますし、弱いものには同情的な側面がありますから自らを逆境と称することに遠慮をしない国民性と思います。
いけないのは本当に逆境に悩まされている方々が、それに打ちひしがれて辛い思いをすることですよね。
出来ればそんな人こそ、日の目を見たり、あるところでは恵まれたり、努力が早く報われたりするといいのですが。
でも逆境を逞しく生き抜いた人は逞しいものです。
はねのけた逆境の大きさを感じさせない人もいるものです。
つまり、真骨頂が発揮されると凄い力を生み出すと言うことでしょうね。
私の知人の中にも、生まれながらにして大きな障害を抱えていますが、物ともせず事業を大きくし、社会にも大きく貢献されている方も数人存じあげております。
また、一度は事業に失敗をされていながら、その債権を全て返済し新たにまた大きく事業を展開されたり。
両親にも恵まれず、苦難の少年時代、青春を送っていながら小さな資本を元手にコツコツと信用を積み上げ、今では地場でも堅実な会社のオーナーとして名を馳せている人もいます。
どうもその人々は逆境を自分の負の資産、負債とするのではなくそれに立ち向かう姿勢、或いは逆に見方にしてしまう考え、大事な自分の資産と考えているのかも知れませんね。
既に乗り越えた逆境は逆境ではなくなってしまいます。
乗り越えた真骨頂は、ここ一番の時にこそ発揮されるものです。
自らが逆境に立たされていると思えば、気持ちが萎(な)えてしまう人、
だからこそと奮起して、逆境からのし上がっていく人、
或いは逆境を逆境とも思わない人・・・・・
人の本当の姿など、他人がわかるわけがありません。
殆どの人は自らが逆境の最中にあると思っていますし、それを悔やんでいるものです。
所が本当に逆境に置かれている人は僅かだと思うのです。
日本人の特性で、自虐的なところがありますし、弱いものには同情的な側面がありますから自らを逆境と称することに遠慮をしない国民性と思います。
いけないのは本当に逆境に悩まされている方々が、それに打ちひしがれて辛い思いをすることですよね。
出来ればそんな人こそ、日の目を見たり、あるところでは恵まれたり、努力が早く報われたりするといいのですが。
でも逆境を逞しく生き抜いた人は逞しいものです。
はねのけた逆境の大きさを感じさせない人もいるものです。
つまり、真骨頂が発揮されると凄い力を生み出すと言うことでしょうね。
私の知人の中にも、生まれながらにして大きな障害を抱えていますが、物ともせず事業を大きくし、社会にも大きく貢献されている方も数人存じあげております。
また、一度は事業に失敗をされていながら、その債権を全て返済し新たにまた大きく事業を展開されたり。
両親にも恵まれず、苦難の少年時代、青春を送っていながら小さな資本を元手にコツコツと信用を積み上げ、今では地場でも堅実な会社のオーナーとして名を馳せている人もいます。
どうもその人々は逆境を自分の負の資産、負債とするのではなくそれに立ち向かう姿勢、或いは逆に見方にしてしまう考え、大事な自分の資産と考えているのかも知れませんね。
既に乗り越えた逆境は逆境ではなくなってしまいます。
乗り越えた真骨頂は、ここ一番の時にこそ発揮されるものです。
Posted by misterkei0918 at
15:34
│Comments(0)
2010年06月08日
ミヤマキリシマに魅せられて
ミヤマキリシマに魅せられて
私共夫婦にとって毎年の年中行事になりました。
6月第一日曜日は九重登山の日になってしまいました。
九重の山開きの日だからです。
今まで何回九重に出かけたか数知れずですが、山開きに出かけるようになって10年ほど。
特に5,6年前に登った平治岳のミヤマキリシマの美しさは脳裏から離れることはありません。
山の頂上に咲き誇ったミヤマキリシマは、月並みな言葉になってしまいますがまさしく「絨毯を敷き詰めた」といっても過言ではなかったのです。
家内が今年はそんなに遠くまで歩く自身がないとの言葉を受けて、長者原からせめて雨ヶ原程度で充分と思っていたのです。
所が雨が原についた途端に、「坊がつるまで行ってみたい」と言うではありませんか。
それから小一時間、一時半頃に到着。
三俣山と平治岳、大船山の間をぬって流れる小川の片隅でおにぎりに漬物、焼き魚を手でつまんで頬張ってきました。
今年は寒かったせいでしょうか、ミヤマキリシマの咲き具合は約1週間程度遅れているようで、毎年なら行列のようにして歩く登山道も幾らか寂しい状況でした。
でも私共夫婦にとっては、素晴らしい花の咲き具合のように感じましたし足の疲れもそんなになくて、しかも素晴らしい天気に恵まれた一日でした。
いつものことですが、いつもの家族風呂で疲れを癒し、一路家路へ。
この家族風呂に立ち寄るのも、最近の出来立ての頃から既に10回を数えたようです。
ミヤマキリシマは長崎県、鹿児島県の花にも指定されているようですが、この花の情報を少し借用いたしました。
『ミヤマキリシマ(深山霧島 Rhododendron kiusianum)は、ツツジの一種。九州各地の高山に自生する。
1m程度の低木で、花期は概ね5月下旬から6月中旬。枝先に2-3個ずつ紫紅色の花をつけるが、桃色、薄紅色の花も見られる。また、気候が似通った秋にも少し咲くことがある。
和名に冠された霧島山・えびの高原のほか、阿蘇山、九重山、雲仙岳、鶴見岳など九州各地の高山に分布する。
ミヤマキリシマは、火山活動により生態系が撹乱された山肌で優占種として生存できる。逆に火山活動が終息し植物の遷移によって森林化が進むと、優占種として生存できなくなる。
害虫としてキシタエダシャクが大発生することがある。
植物学者牧野富太郎が新婚旅行で霧島方面を旅行して発見して1909年に命名した。2009年は命名100年の年にあたる。』
何時までも私共の目を楽しませて欲しいものです。
私共夫婦にとって毎年の年中行事になりました。
6月第一日曜日は九重登山の日になってしまいました。
九重の山開きの日だからです。
今まで何回九重に出かけたか数知れずですが、山開きに出かけるようになって10年ほど。
特に5,6年前に登った平治岳のミヤマキリシマの美しさは脳裏から離れることはありません。
山の頂上に咲き誇ったミヤマキリシマは、月並みな言葉になってしまいますがまさしく「絨毯を敷き詰めた」といっても過言ではなかったのです。
家内が今年はそんなに遠くまで歩く自身がないとの言葉を受けて、長者原からせめて雨ヶ原程度で充分と思っていたのです。
所が雨が原についた途端に、「坊がつるまで行ってみたい」と言うではありませんか。
それから小一時間、一時半頃に到着。
三俣山と平治岳、大船山の間をぬって流れる小川の片隅でおにぎりに漬物、焼き魚を手でつまんで頬張ってきました。
今年は寒かったせいでしょうか、ミヤマキリシマの咲き具合は約1週間程度遅れているようで、毎年なら行列のようにして歩く登山道も幾らか寂しい状況でした。
でも私共夫婦にとっては、素晴らしい花の咲き具合のように感じましたし足の疲れもそんなになくて、しかも素晴らしい天気に恵まれた一日でした。
いつものことですが、いつもの家族風呂で疲れを癒し、一路家路へ。
この家族風呂に立ち寄るのも、最近の出来立ての頃から既に10回を数えたようです。
ミヤマキリシマは長崎県、鹿児島県の花にも指定されているようですが、この花の情報を少し借用いたしました。
『ミヤマキリシマ(深山霧島 Rhododendron kiusianum)は、ツツジの一種。九州各地の高山に自生する。
1m程度の低木で、花期は概ね5月下旬から6月中旬。枝先に2-3個ずつ紫紅色の花をつけるが、桃色、薄紅色の花も見られる。また、気候が似通った秋にも少し咲くことがある。
和名に冠された霧島山・えびの高原のほか、阿蘇山、九重山、雲仙岳、鶴見岳など九州各地の高山に分布する。
ミヤマキリシマは、火山活動により生態系が撹乱された山肌で優占種として生存できる。逆に火山活動が終息し植物の遷移によって森林化が進むと、優占種として生存できなくなる。
害虫としてキシタエダシャクが大発生することがある。
植物学者牧野富太郎が新婚旅行で霧島方面を旅行して発見して1909年に命名した。2009年は命名100年の年にあたる。』
何時までも私共の目を楽しませて欲しいものです。
Posted by misterkei0918 at
00:28
│Comments(0)
2010年06月07日
自慢の父親でありたいと願っている
自慢の父親でありたいと願っている
昨日は「最愛の夫でありたい」等と欲張ったブログを書きました。
それを多分、身の程知らずと言うのでしょう。
自分の夫としての技量や果たした役割、存在価値などは分からないものです。
欲張って、自己評価のみはしっかりしますから過大評価や尊大な自己をつい夢見てしまいます。
相手がどう見ているかを考えたら、自ずからそこに無理が生じていることを悟らないといけませんね。
反省です。
ついでにこんなことまで考えてしまいました。
「自慢の父親でありたい」
子供達には馬鹿な事を考える父親だなと後ろ指をさされそうですが、もうここまで書いてきたのですから、事のついでと許してくれることを乞い願って。
誰しも子供達から蔑(さげす)まれる父親、疎(うと)まれる父親にはなりたくはありませんし、そのような評価を下すとしたら多分、その責任を子供達の精にしてしまう父親が多いのではないでしょうか。
それがイケないのですよね。
若しもそのような評価が下っていたとしたら、素直に自己責任を認め、反省をし、しかも謝る。
所が男は謝ることに、絶対的な嫌悪感を持っていますからそれはないでしょうね。
一生、蔑まれる父親であり続けるのか、疎まれる父親を続けるのか。
「あの父親なら要らなかった」とか、
「あの父親がいなかったら、今頃はいい意味で異なった人生を歩んでいた」等と言われるとこれは大変な汚点です。
それこそ存在さえも否定されかねない状態です。
日頃からの姿勢なんでしょうね。
子供達に媚びへつらう様な父親はいけません。
むしろそれは子供の成長にマイナスの効果を持たらしてしまいます。
父親は毅然として、事の真実を見つめ、悪には敢然として立ち向かい、家庭のリーダーとして、大黒柱としてその存在を確立しておかねばいけないと思います。
とは言いながら、大変に難しいことですが。
でも、少なくとも「自慢の父親だった」程度は評価をして欲しいですね。
生きているときの男は常に今の自分に挑戦的で、周りに優しい心配りなどは気がつきませんしそんなゆとりや素振りも無いものです。
この世から去る時がどうも一番の勝負時に思えるのですがどうでしょうか。
その時のために粉骨砕身、逞しく、真摯に生き抜きたいものです。
夢のような事を語ってしまいました。
『父親は、最も厳しく叱る時も、言葉はきついが父親らしいそぶりを見せる。ギリシア』
『世界で一番有能な教師よりも、分別のある平凡な父親によってこそ、子供は立派に教育される。ルソー(仏・思想家)』
昨日は「最愛の夫でありたい」等と欲張ったブログを書きました。
それを多分、身の程知らずと言うのでしょう。
自分の夫としての技量や果たした役割、存在価値などは分からないものです。
欲張って、自己評価のみはしっかりしますから過大評価や尊大な自己をつい夢見てしまいます。
相手がどう見ているかを考えたら、自ずからそこに無理が生じていることを悟らないといけませんね。
反省です。
ついでにこんなことまで考えてしまいました。
「自慢の父親でありたい」
子供達には馬鹿な事を考える父親だなと後ろ指をさされそうですが、もうここまで書いてきたのですから、事のついでと許してくれることを乞い願って。
誰しも子供達から蔑(さげす)まれる父親、疎(うと)まれる父親にはなりたくはありませんし、そのような評価を下すとしたら多分、その責任を子供達の精にしてしまう父親が多いのではないでしょうか。
それがイケないのですよね。
若しもそのような評価が下っていたとしたら、素直に自己責任を認め、反省をし、しかも謝る。
所が男は謝ることに、絶対的な嫌悪感を持っていますからそれはないでしょうね。
一生、蔑まれる父親であり続けるのか、疎まれる父親を続けるのか。
「あの父親なら要らなかった」とか、
「あの父親がいなかったら、今頃はいい意味で異なった人生を歩んでいた」等と言われるとこれは大変な汚点です。
それこそ存在さえも否定されかねない状態です。
日頃からの姿勢なんでしょうね。
子供達に媚びへつらう様な父親はいけません。
むしろそれは子供の成長にマイナスの効果を持たらしてしまいます。
父親は毅然として、事の真実を見つめ、悪には敢然として立ち向かい、家庭のリーダーとして、大黒柱としてその存在を確立しておかねばいけないと思います。
とは言いながら、大変に難しいことですが。
でも、少なくとも「自慢の父親だった」程度は評価をして欲しいですね。
生きているときの男は常に今の自分に挑戦的で、周りに優しい心配りなどは気がつきませんしそんなゆとりや素振りも無いものです。
この世から去る時がどうも一番の勝負時に思えるのですがどうでしょうか。
その時のために粉骨砕身、逞しく、真摯に生き抜きたいものです。
夢のような事を語ってしまいました。
『父親は、最も厳しく叱る時も、言葉はきついが父親らしいそぶりを見せる。ギリシア』
『世界で一番有能な教師よりも、分別のある平凡な父親によってこそ、子供は立派に教育される。ルソー(仏・思想家)』
Posted by misterkei0918 at
19:33
│Comments(1)
2010年06月07日
最愛の夫でありたいけど
最愛の夫でありたいけど
自慢の夫になる必要はありませんが、せめて口には出さなくても心のなかで「最愛の夫だったね」くらいは呟いてもらえるような夫でありたいと願う旦那衆は私一人ではないでしょう。
どうせ先立つのは男が殆んどですから、残った妻から「あ、清々した!!」等と言われないようにその日まで毅然として、頼りにされて、介護の苦労などはさせないで終わりたいものです。
あるいは「もう少し頑張って欲しかった」等と。
夫婦のあり方は決して一様ではありませんし、お互いのあり方はそれぞれの夫婦で話し合い、若しくは年月の中で自然と醸成されるものですから、一言では語れないことは当然です。
私のあり方は私であって、それは私共が作り出した夫である私の存在であります。
あの人のようにありたいとか思うことはありますが、取り巻く環境や生まれた子供達との関わり、務める企業や地域、所得や日常の行動体系、受ける教育などによっても単純ではありません。
ましてやそこに妻という相手が存在し、彼女の有り様がまたそれぞれに異なることですから目標とする人にはなかなかならないものです。
多分、日常的にそんな事を考えながら生活をしているわけではありませんが、時々は自らの夫である立場やあり方を見つめ直す時間があっても良さそうです。
今の自分でいいのか、
果たして妻に対して居心地の良い家庭を築けているのか、
将来にわたって安定的で心休まる家庭を保証出来る環境を作っているのか、
お互いが信頼を築ける環境を作っているのか、
お互いがお互いの人生を高めあえる状況なのか、
出来れば最愛の夫であるのか・・・・・
一言で夫婦と言っても、自分の親以上に、しかもわが子たち以上に長い年月を共にします。
それは長い人になると、60年も70年連れ添うのですから甘いも酸いも、凪も荒波も経験をしていますからそれぞれの人間性や考え方、思想信条までも全て飲み込んでしまうものです。
後悔をしてみたり、半信半疑の時期が会ったり、不信感を持たれたり、頼りないと思われたり、絶対絶命の危機の瀕したり、様々な経験をするものです。
その原因の殆どは夫の方ですが。
阿吽の呼吸とか、以心伝心とか。
老夫婦が言葉少なく連れ添っている姿を見ていると「もう話すことが無くなった」と思いがちですがそれは違いますよね。
そこまでになると「話さなくてもお互いが考えていることくらいは既に伝わっている」と判断するのが正しいでしょう。
そうでないとしたら夫婦としてどうなんでしょうか。
話しても良し、話さなくても良し。
話せばお互いの思いを改めて確認していることでしょうし、話さなければ既に意思が疎通しあっていると言うものです。
最愛の夫である事は難しいとすれば、「少なくとも傍に頂けでも良かったね」
或いは「生涯、連れ添えて良かった」位の評価は頂きたいものです。
自慢の夫になる必要はありませんが、せめて口には出さなくても心のなかで「最愛の夫だったね」くらいは呟いてもらえるような夫でありたいと願う旦那衆は私一人ではないでしょう。
どうせ先立つのは男が殆んどですから、残った妻から「あ、清々した!!」等と言われないようにその日まで毅然として、頼りにされて、介護の苦労などはさせないで終わりたいものです。
あるいは「もう少し頑張って欲しかった」等と。
夫婦のあり方は決して一様ではありませんし、お互いのあり方はそれぞれの夫婦で話し合い、若しくは年月の中で自然と醸成されるものですから、一言では語れないことは当然です。
私のあり方は私であって、それは私共が作り出した夫である私の存在であります。
あの人のようにありたいとか思うことはありますが、取り巻く環境や生まれた子供達との関わり、務める企業や地域、所得や日常の行動体系、受ける教育などによっても単純ではありません。
ましてやそこに妻という相手が存在し、彼女の有り様がまたそれぞれに異なることですから目標とする人にはなかなかならないものです。
多分、日常的にそんな事を考えながら生活をしているわけではありませんが、時々は自らの夫である立場やあり方を見つめ直す時間があっても良さそうです。
今の自分でいいのか、
果たして妻に対して居心地の良い家庭を築けているのか、
将来にわたって安定的で心休まる家庭を保証出来る環境を作っているのか、
お互いが信頼を築ける環境を作っているのか、
お互いがお互いの人生を高めあえる状況なのか、
出来れば最愛の夫であるのか・・・・・
一言で夫婦と言っても、自分の親以上に、しかもわが子たち以上に長い年月を共にします。
それは長い人になると、60年も70年連れ添うのですから甘いも酸いも、凪も荒波も経験をしていますからそれぞれの人間性や考え方、思想信条までも全て飲み込んでしまうものです。
後悔をしてみたり、半信半疑の時期が会ったり、不信感を持たれたり、頼りないと思われたり、絶対絶命の危機の瀕したり、様々な経験をするものです。
その原因の殆どは夫の方ですが。
阿吽の呼吸とか、以心伝心とか。
老夫婦が言葉少なく連れ添っている姿を見ていると「もう話すことが無くなった」と思いがちですがそれは違いますよね。
そこまでになると「話さなくてもお互いが考えていることくらいは既に伝わっている」と判断するのが正しいでしょう。
そうでないとしたら夫婦としてどうなんでしょうか。
話しても良し、話さなくても良し。
話せばお互いの思いを改めて確認していることでしょうし、話さなければ既に意思が疎通しあっていると言うものです。
最愛の夫である事は難しいとすれば、「少なくとも傍に頂けでも良かったね」
或いは「生涯、連れ添えて良かった」位の評価は頂きたいものです。
Posted by misterkei0918 at
18:56
│Comments(0)
2010年06月03日
自分ははにかみ屋で、小心者だと言う君へ
自分ははにかみ屋で、小心者だと言う君へ
それでいいんです。
むしろ人はその方が良いと私は思っています。
当然の事だけど、だからこそ悩みもするし、歯痒かったり、悔しかったり、挫折の日々です。
時には、明日が来ることも拒絶したいほど苦難の現実にぶつかるものです。
それでいいと思うのです。
また、そうでないといけないと私は信じています。
そこで逃げてしまっては自分の未来をみすみす見捨てるようなものであり、場合によってはその事がより深刻な問題へと発展することだって多いものです。
はにかみ屋と言うことは、心の片隅にはにかみ屋でありたくない、はにかむような状況に自分を置きたくないと言う感情が渦巻いているものです。
ですから大切にしたいのです。
結局は向上心などや負けたくない、恥をかきたくない等の心理が大きく働いていると思ったらいいと思うのです。
自分の現状に満足していない自分が新しく生まれ出ようとして葛藤を繰り返していると。
ですから、逃げるのではなくそれを逆手にとってみると面白い結果が出てくるものです。
時には目をつむって、恥ずかしい場面などでも自ら直面してみることです。
それも数回。
小心者と思っていても、結局はそうでない人が多いものです。
人は誰でも臆病なものです。
勇敢そうには見えても。
それぞれに大した差など存在はしません。
ただ、少しだけ一歩を踏み出すか出さないか、勇気を出してなどと言う程ではなく。
私はだからこそ、人間味豊かで人への思いやりがあって、でしゃばらない人々の中にはむしろはにかみ屋で小心者の方々を多く拝見することがあります。
乗り超えた人には、そうでない人よりも素晴らしい人間性を体得した人が多いものです。
一歩を踏み出そうとしないことが怖いのです。
人生の差なんてそんな事かも知れませんね。
それでいいんです。
むしろ人はその方が良いと私は思っています。
当然の事だけど、だからこそ悩みもするし、歯痒かったり、悔しかったり、挫折の日々です。
時には、明日が来ることも拒絶したいほど苦難の現実にぶつかるものです。
それでいいと思うのです。
また、そうでないといけないと私は信じています。
そこで逃げてしまっては自分の未来をみすみす見捨てるようなものであり、場合によってはその事がより深刻な問題へと発展することだって多いものです。
はにかみ屋と言うことは、心の片隅にはにかみ屋でありたくない、はにかむような状況に自分を置きたくないと言う感情が渦巻いているものです。
ですから大切にしたいのです。
結局は向上心などや負けたくない、恥をかきたくない等の心理が大きく働いていると思ったらいいと思うのです。
自分の現状に満足していない自分が新しく生まれ出ようとして葛藤を繰り返していると。
ですから、逃げるのではなくそれを逆手にとってみると面白い結果が出てくるものです。
時には目をつむって、恥ずかしい場面などでも自ら直面してみることです。
それも数回。
小心者と思っていても、結局はそうでない人が多いものです。
人は誰でも臆病なものです。
勇敢そうには見えても。
それぞれに大した差など存在はしません。
ただ、少しだけ一歩を踏み出すか出さないか、勇気を出してなどと言う程ではなく。
私はだからこそ、人間味豊かで人への思いやりがあって、でしゃばらない人々の中にはむしろはにかみ屋で小心者の方々を多く拝見することがあります。
乗り超えた人には、そうでない人よりも素晴らしい人間性を体得した人が多いものです。
一歩を踏み出そうとしないことが怖いのです。
人生の差なんてそんな事かも知れませんね。
Posted by misterkei0918 at
11:46
│Comments(0)
2010年06月03日
「認知症サポーター養成講座」を受けてきました
「認知症サポーター養成講座」を受けてきました
今日、6月1日に「認知症サポーター養成講座」を受講してきました。
解説によると、
『認知症は誰にも起こり得る脳の病気によるもので、85歳以上では4人に一人にその症状があると言われています。
現在は、169万人ですが20年で倍増することが予想されています』
つまり、病気ではないということですよね。
昔で言えば、「ボケ」とか「痴呆症」とか言われてたことですよね。
身を持って、介護の難しさを体験していますが、一番に理解しなくてはいけないことは本人こそが一番辛いことであるということ。
私共が持っている病気であると言う認識をすてないといけないということ。
急激に増えてきているのは、社会情勢、環境の変化が引き金に成っていること。
高齢化が急速に進んでいることや核家族化、脳や神経を逆なでするような働き方や、人間関係の軋轢、急速な時代の変化などなど・・・・・
恥ずかしいことでもないということ。
身内に認知症の方がおられても、殆んどの方が口にすることはありません。
こちらが切り出すと、「そうなんです。うちも・・・・・」となるのですが。
持ち得た情報は、差し障りの無い範囲で、オープンにすることが自らにもそれ以上の貴重な情報やアイディアが飛び込んでくるものです。
母の認知症を目の当たりにして、私自身の知識不足や一般の方々の認知症に対する勘違いの多さに突き当たることになりました。
私自身もいずれはその予備軍なわけですから、母の教訓を無にすることなく自分の人生を見つめ直さないといけません。
大事なのは、今までの親子、母子としての関係を根底から覆すような出来事ですので、真剣に対処しないといけないようです。
悲しい、苦しいことですが。
今は、認知症について書くとつい涙が溢れてきますので幾らか落ち着いたら、ブログにも記載して皆さんの理解の一助にしてもらったり、生の情報として生かせればとも思っています。
或いは思い切って、母の生涯と認知症の本でも。
今日、6月1日に「認知症サポーター養成講座」を受講してきました。
解説によると、
『認知症は誰にも起こり得る脳の病気によるもので、85歳以上では4人に一人にその症状があると言われています。
現在は、169万人ですが20年で倍増することが予想されています』
つまり、病気ではないということですよね。
昔で言えば、「ボケ」とか「痴呆症」とか言われてたことですよね。
身を持って、介護の難しさを体験していますが、一番に理解しなくてはいけないことは本人こそが一番辛いことであるということ。
私共が持っている病気であると言う認識をすてないといけないということ。
急激に増えてきているのは、社会情勢、環境の変化が引き金に成っていること。
高齢化が急速に進んでいることや核家族化、脳や神経を逆なでするような働き方や、人間関係の軋轢、急速な時代の変化などなど・・・・・
恥ずかしいことでもないということ。
身内に認知症の方がおられても、殆んどの方が口にすることはありません。
こちらが切り出すと、「そうなんです。うちも・・・・・」となるのですが。
持ち得た情報は、差し障りの無い範囲で、オープンにすることが自らにもそれ以上の貴重な情報やアイディアが飛び込んでくるものです。
母の認知症を目の当たりにして、私自身の知識不足や一般の方々の認知症に対する勘違いの多さに突き当たることになりました。
私自身もいずれはその予備軍なわけですから、母の教訓を無にすることなく自分の人生を見つめ直さないといけません。
大事なのは、今までの親子、母子としての関係を根底から覆すような出来事ですので、真剣に対処しないといけないようです。
悲しい、苦しいことですが。
今は、認知症について書くとつい涙が溢れてきますので幾らか落ち着いたら、ブログにも記載して皆さんの理解の一助にしてもらったり、生の情報として生かせればとも思っています。
或いは思い切って、母の生涯と認知症の本でも。
Posted by misterkei0918 at
09:48
│Comments(0)
2010年06月02日
若い頃は貧乏がいい・・・清貧の思い
若い頃は貧乏がいい・・・清貧の思い
どこかの国の総理ではありませんが、月に1500万円も母親から貰っていて、全く記憶が無いなど私などの神経からすると想像を遥かに超えてしまいます。
ましてや何に使ったのかも知らないとか。
そうですよね、貰ったことすらわから無いのですから。
「私は余りにも恵まれ過ぎていたから」等と公然と口にするのですから呆れてしまいます。
当初は余るほどの期待をし、この日本の現状を大いに打破してくれるものと信じていたのですが。
結局は日本中の人々を不信、腐心そして疑心の坩堝に落としてしまいましたし、特に沖縄の方々に大変な心痛を掛けることになってしまいました。
裏切られるとはこの事ですね。
この8ヶ月間、政治の世界では本当に不思議な現象が続きすぎました。
やはり若い頃は貧乏が良さそうです。
そうです、清貧の思いですよね。
貧しいこと、
恵まれないこと、
苦労の絶えない事、
心配の種が尽きることがないこと、
・
・
そんな事が、努力の大切さや思いやり、人の痛みが分かる人間を作ってくれます。
努力を重ねて、勝ち取った幸せの味を知らない人間は幸せが何なのかを知りません。
自分の周りには小さい頃から捨て去りたいほどの幸せが転がっていて、何でも思うことは必ず実現をし、或いは望まないことまでも身の回りには溢れかえっているなどの人生は本当の中身のない人生であることを学んだような気がします。
頭が良すぎるのでしょうか。
高邁な理想と、大よそ実現性の無い言葉だけが先走り、多くの人の心の把握が出来ず、説得や根回しと言ったコンセンサスを得ることも必要なかったのでしょう。
苦労した人はどこか違うものです。
大きなことは言いません。
実現出来ないことなど言うわけがありません。
慎重です。
人心を惑わすことなど決して口にはしないものです。
常に相手の気持を読むことに余念がなく、自分が一歩下がってでも相手の事に思いが馳せるものです。
若い頃は苦労をしましょう。
「苦労は買ってでもしなさい」と先人は教えてくれました。
苦労して勝ち取った幸せほど長続きしますし、感慨も一入です。
どこかの国の総理ではありませんが、月に1500万円も母親から貰っていて、全く記憶が無いなど私などの神経からすると想像を遥かに超えてしまいます。
ましてや何に使ったのかも知らないとか。
そうですよね、貰ったことすらわから無いのですから。
「私は余りにも恵まれ過ぎていたから」等と公然と口にするのですから呆れてしまいます。
当初は余るほどの期待をし、この日本の現状を大いに打破してくれるものと信じていたのですが。
結局は日本中の人々を不信、腐心そして疑心の坩堝に落としてしまいましたし、特に沖縄の方々に大変な心痛を掛けることになってしまいました。
裏切られるとはこの事ですね。
この8ヶ月間、政治の世界では本当に不思議な現象が続きすぎました。
やはり若い頃は貧乏が良さそうです。
そうです、清貧の思いですよね。
貧しいこと、
恵まれないこと、
苦労の絶えない事、
心配の種が尽きることがないこと、
・
・
そんな事が、努力の大切さや思いやり、人の痛みが分かる人間を作ってくれます。
努力を重ねて、勝ち取った幸せの味を知らない人間は幸せが何なのかを知りません。
自分の周りには小さい頃から捨て去りたいほどの幸せが転がっていて、何でも思うことは必ず実現をし、或いは望まないことまでも身の回りには溢れかえっているなどの人生は本当の中身のない人生であることを学んだような気がします。
頭が良すぎるのでしょうか。
高邁な理想と、大よそ実現性の無い言葉だけが先走り、多くの人の心の把握が出来ず、説得や根回しと言ったコンセンサスを得ることも必要なかったのでしょう。
苦労した人はどこか違うものです。
大きなことは言いません。
実現出来ないことなど言うわけがありません。
慎重です。
人心を惑わすことなど決して口にはしないものです。
常に相手の気持を読むことに余念がなく、自分が一歩下がってでも相手の事に思いが馳せるものです。
若い頃は苦労をしましょう。
「苦労は買ってでもしなさい」と先人は教えてくれました。
苦労して勝ち取った幸せほど長続きしますし、感慨も一入です。
Posted by misterkei0918 at
23:31
│Comments(0)
2010年06月02日
政治家の資格って
政治家の資格って
先程、日本の総理が自ら辞任をされたようです。
理由は、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)移設をめぐる混乱や「政治とカネ」の問題で政権への信頼が大きく低下したこととされたようです。
振り返ってみると、何か不思議な気さえします。
信頼や期待が大きかっただけに、途中に失望は悲しいくらいに嘆かわしいことでした。
以前にも書いたことがありましたが、約2600年ほど前の中国の孔子が、弟子から政治家の資格について聞かれました。
その答えです。
「五美を実行し、四悪を排除できれば資格が充分だ」。
その五美とは?と問われて
「上に立つ者は、
人民に恩恵を与えてしかも国庫を乏しくしないこと。
人民を使役してしかも不満を抱かせぬこと。
気宇宏大であってしかも寡欲であること。
泰然としていてしかも傲慢でないこと。
最後に、威厳があってしかも圧迫を感じさせぬこと。
この五つがそれだ。」
では、四悪とは何ですか?と問われて
「社会教育をおろそかにしておきながら、
いきなり法律にそむいたといって人民を処罰するやり方、
これを残忍といわずに何といおう。
指導もせずにいて実績をあげろと強制する、
無茶としかいいようがない。
はっきり命令を下さずにいながら、突如として実行を迫る、
それは非道というものだ。
出すべきものもケチケチ出し惜しむもったいぶったやり方、
これが小役人根性である」
孔子の弟子の子夏(しか)の言葉にも、
「為政者は人民から信頼されてこそ、人民を公役に就かせることが出来る。
もし信頼されていなかったら、政府は俺たちを絞るだけだ、と人民は考えるだろう。
また、上司の信頼があってこそ、こちらの提案は採用される。
信頼も無いのにいくら提案したところで、バカにされたと思われるのが関の山だ。」
政治に期待をするのが間違っているのだろうかと考えたりもします。
政争の為に国民が不在状態で、ただ選挙の投票マシンとしてしか国民を見ていないのではないかとも思います。
政治家の質はその国民の質や程度を反映していると言いますが、この日本ではどうも違うようです。
最早、国民の方がその質や程度は上回っているようにも見えます。
国民を欺いてはいけませんよね。
先程、日本の総理が自ら辞任をされたようです。
理由は、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)移設をめぐる混乱や「政治とカネ」の問題で政権への信頼が大きく低下したこととされたようです。
振り返ってみると、何か不思議な気さえします。
信頼や期待が大きかっただけに、途中に失望は悲しいくらいに嘆かわしいことでした。
以前にも書いたことがありましたが、約2600年ほど前の中国の孔子が、弟子から政治家の資格について聞かれました。
その答えです。
「五美を実行し、四悪を排除できれば資格が充分だ」。
その五美とは?と問われて
「上に立つ者は、
人民に恩恵を与えてしかも国庫を乏しくしないこと。
人民を使役してしかも不満を抱かせぬこと。
気宇宏大であってしかも寡欲であること。
泰然としていてしかも傲慢でないこと。
最後に、威厳があってしかも圧迫を感じさせぬこと。
この五つがそれだ。」
では、四悪とは何ですか?と問われて
「社会教育をおろそかにしておきながら、
いきなり法律にそむいたといって人民を処罰するやり方、
これを残忍といわずに何といおう。
指導もせずにいて実績をあげろと強制する、
無茶としかいいようがない。
はっきり命令を下さずにいながら、突如として実行を迫る、
それは非道というものだ。
出すべきものもケチケチ出し惜しむもったいぶったやり方、
これが小役人根性である」
孔子の弟子の子夏(しか)の言葉にも、
「為政者は人民から信頼されてこそ、人民を公役に就かせることが出来る。
もし信頼されていなかったら、政府は俺たちを絞るだけだ、と人民は考えるだろう。
また、上司の信頼があってこそ、こちらの提案は採用される。
信頼も無いのにいくら提案したところで、バカにされたと思われるのが関の山だ。」
政治に期待をするのが間違っているのだろうかと考えたりもします。
政争の為に国民が不在状態で、ただ選挙の投票マシンとしてしか国民を見ていないのではないかとも思います。
政治家の質はその国民の質や程度を反映していると言いますが、この日本ではどうも違うようです。
最早、国民の方がその質や程度は上回っているようにも見えます。
国民を欺いてはいけませんよね。
Posted by misterkei0918 at
12:57
│Comments(0)