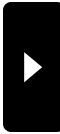2010年11月30日
「暇な時間は無いが良い」
「暇な時間は無いが良い」
人は張り詰めた状態だけでは、精神を病んでしまうこともありますし、いずれ何処かで破綻をきたしたり行き詰まりを感じるものです。
逆に、余りにも暇な状態ばかりでは人間としての勢いを失い、努力を忘れ、知力体力を高める努力や人との競争、自らの努力さえも忘れてしまいます。
人生は中庸が大事ですが、事はそんなに単純にはいかないものです。
忙しいときがあれば、暇なときもあったり。抑揚が大事。
リズムとでもいうのでしょうか。
それが上手く調和する人生が充実感が伴って、精神衛生上も素晴らしい生き方なのでしょうね。
実はタイトルには「暇な時間は無いが良い」と書きはしましたが、正確には「怠惰な時間は無いが良い」が最も相応しいかもしれませんね。
怠惰な人生は、人への恨み辛みや、他人依存、自らの努力を忘れて責任は他人に擦り付けてやがては自暴自棄な人間へと変化を遂げます。
自らが行動することなく、ただ惰性にのみ身を委ねる事は先には身の破滅が待ち構えているようです。
出来れば人生は目標を持って、それに向かって努力や精進を重ねる事が明るい展望を開き、自らにも自信が漲(みなぎ)り、幸せを引き寄せるものです。
「人生は、苦しい事のみ多かりき」、
それは確かにそうであることを否定する人は少ないと思われますし、お釈迦様でも人生は苦難の連続であってその代表格が四苦、「生・病・老・死」であると教えていただいています。
だからこそ人生はやめられない、生きる価値があると言うのも確かなところです。
一生は走り続ける事は、なかなか至難ですがだからこそ得るものも多いように思われます。
『われわれにとって怠惰ほど有害で致命的な習慣はない。
にもかかわらず、これほど身につきやすく、断ちがたい習慣もない。
ジョントッド「自分を鍛える」(三笠書房)より』
『われわれの本性は、怠惰へ傾いている。
だが、われわれは活動へと心を励ます限り、その活動の真の悦びを感ずる。ゲーテ』
『何もしないさきから、僕はもう駄目だときめてしまうのは、それが怠惰だ』
人は張り詰めた状態だけでは、精神を病んでしまうこともありますし、いずれ何処かで破綻をきたしたり行き詰まりを感じるものです。
逆に、余りにも暇な状態ばかりでは人間としての勢いを失い、努力を忘れ、知力体力を高める努力や人との競争、自らの努力さえも忘れてしまいます。
人生は中庸が大事ですが、事はそんなに単純にはいかないものです。
忙しいときがあれば、暇なときもあったり。抑揚が大事。
リズムとでもいうのでしょうか。
それが上手く調和する人生が充実感が伴って、精神衛生上も素晴らしい生き方なのでしょうね。
実はタイトルには「暇な時間は無いが良い」と書きはしましたが、正確には「怠惰な時間は無いが良い」が最も相応しいかもしれませんね。
怠惰な人生は、人への恨み辛みや、他人依存、自らの努力を忘れて責任は他人に擦り付けてやがては自暴自棄な人間へと変化を遂げます。
自らが行動することなく、ただ惰性にのみ身を委ねる事は先には身の破滅が待ち構えているようです。
出来れば人生は目標を持って、それに向かって努力や精進を重ねる事が明るい展望を開き、自らにも自信が漲(みなぎ)り、幸せを引き寄せるものです。
「人生は、苦しい事のみ多かりき」、
それは確かにそうであることを否定する人は少ないと思われますし、お釈迦様でも人生は苦難の連続であってその代表格が四苦、「生・病・老・死」であると教えていただいています。
だからこそ人生はやめられない、生きる価値があると言うのも確かなところです。
一生は走り続ける事は、なかなか至難ですがだからこそ得るものも多いように思われます。
『われわれにとって怠惰ほど有害で致命的な習慣はない。
にもかかわらず、これほど身につきやすく、断ちがたい習慣もない。
ジョントッド「自分を鍛える」(三笠書房)より』
『われわれの本性は、怠惰へ傾いている。
だが、われわれは活動へと心を励ます限り、その活動の真の悦びを感ずる。ゲーテ』
『何もしないさきから、僕はもう駄目だときめてしまうのは、それが怠惰だ』
Posted by misterkei0918 at
18:58
│Comments(0)
2010年11月27日
日本は何処にでも神様がいた・・・2
日本は何処にでも神様がいた・・・2
25日は年末恒例のNHK紅白歌合戦の出場者の発表がありました。
私が日頃から関心を寄せていた「トイレの神様」、植村花菜さんの歌が選ばれたのです。
嬉しい想いが駆け巡りました。
そして有難い想いも。
会社によってはトイレ掃除を社員に率先してさせるところもありますし、私の知人の社長は朝早くから会社のトイレ掃除を自分の日課として実践している方もいます
「日本は何処にでも神様がいた」と過去形にしたのには訳があります。
子どもたちがそこらじゅうにおしっこをすると、「そこには神様がいる」と諭され、悪い事をしようとすると「神様が見ておられる」注意をされたものです。
水の神様、
火の神様、
お天道様、
地方によっては、田の神様、
日本には昔から「八百万(やおよろず)の神様」が存在したものです。
あらゆる自然の物質、様々な自然現象に対してもそうでした。
それらの神々は、時には崇敬の念を持って感じ取られ、時には恐れおののく対象でもあり、大切にしなくてはいけない対象でもあったのです。
人も亡くなったら、神格化し、あるいは仏となって大切な存在として崇められ、尊敬を集める対象であったものです。
「山ノ神」は最近違った意味に使われますが。
子どもたちにもそんな事を口にする機会が少なくなりました。
或いは皆無と言っても言い過ぎではなさそうです。
日本古来の神道は、私どもの心の真髄にしみこんでいた筈なのですが。
日本古来のあり方、日本人が歴史的に培ってきた国民性や特筆すべき文化も戦後の様々なあり方の影響を蒙って何処かへ置き去りにしてしまいました。
その事に最近気付き始めた方々が多く出て来られているようにも思えますがどうでしょうか。
私自身も最近の近隣諸国のあり方や経済、金融の動き、日本の政治の現状を垣間見た時に私どもが失ってはいけない本来の日本人や日本を今一度思い起こし、再度原点に帰る時期に来たような気がするのです。
余りにも行き過ぎたグローバル化が、それぞれの国々が本来持っていた価値観や国民性が忘れ去られ、画一化し自国が本来大切にすべき文化までもが捨て去られそうになっています。
江戸末期に来日をした諸外国の人々が賞賛した日本や日本人の素晴らしさを、今一度研究をしなくてはいけないようです。
その一つが、「日本は何処にでも神様がいた」という考えではないでしょうか。
『我事において後悔せず、神仏を尊び神仏を頼まず。宮本武蔵』
『われわれが進もうとしている道が正しいかどうかを、
神は前もっては教えてくれない。アインシュタイン』
25日は年末恒例のNHK紅白歌合戦の出場者の発表がありました。
私が日頃から関心を寄せていた「トイレの神様」、植村花菜さんの歌が選ばれたのです。
嬉しい想いが駆け巡りました。
そして有難い想いも。
会社によってはトイレ掃除を社員に率先してさせるところもありますし、私の知人の社長は朝早くから会社のトイレ掃除を自分の日課として実践している方もいます
「日本は何処にでも神様がいた」と過去形にしたのには訳があります。
子どもたちがそこらじゅうにおしっこをすると、「そこには神様がいる」と諭され、悪い事をしようとすると「神様が見ておられる」注意をされたものです。
水の神様、
火の神様、
お天道様、
地方によっては、田の神様、
日本には昔から「八百万(やおよろず)の神様」が存在したものです。
あらゆる自然の物質、様々な自然現象に対してもそうでした。
それらの神々は、時には崇敬の念を持って感じ取られ、時には恐れおののく対象でもあり、大切にしなくてはいけない対象でもあったのです。
人も亡くなったら、神格化し、あるいは仏となって大切な存在として崇められ、尊敬を集める対象であったものです。
「山ノ神」は最近違った意味に使われますが。
子どもたちにもそんな事を口にする機会が少なくなりました。
或いは皆無と言っても言い過ぎではなさそうです。
日本古来の神道は、私どもの心の真髄にしみこんでいた筈なのですが。
日本古来のあり方、日本人が歴史的に培ってきた国民性や特筆すべき文化も戦後の様々なあり方の影響を蒙って何処かへ置き去りにしてしまいました。
その事に最近気付き始めた方々が多く出て来られているようにも思えますがどうでしょうか。
私自身も最近の近隣諸国のあり方や経済、金融の動き、日本の政治の現状を垣間見た時に私どもが失ってはいけない本来の日本人や日本を今一度思い起こし、再度原点に帰る時期に来たような気がするのです。
余りにも行き過ぎたグローバル化が、それぞれの国々が本来持っていた価値観や国民性が忘れ去られ、画一化し自国が本来大切にすべき文化までもが捨て去られそうになっています。
江戸末期に来日をした諸外国の人々が賞賛した日本や日本人の素晴らしさを、今一度研究をしなくてはいけないようです。
その一つが、「日本は何処にでも神様がいた」という考えではないでしょうか。
『我事において後悔せず、神仏を尊び神仏を頼まず。宮本武蔵』
『われわれが進もうとしている道が正しいかどうかを、
神は前もっては教えてくれない。アインシュタイン』
Posted by misterkei0918 at
00:06
│Comments(0)
2010年11月25日
日本は何処にでも神様がいた・・・1
日本は何処にでも神様がいた・・・1
昨日は年末恒例のNHK紅白歌合戦の出場者の発表がありました。
ところで「紅白歌合戦」という番組名も昔懐かしい感じがします。
と言うか、すっかり馴染んでしまいましたし現代風の言い回しをしなくても違和感がありませんよね。
多分、ラジオの時代からあるのですから60年位にはなるのではないでしょうか。
紅白の歴史を調べてみました。
ラジオ放送が行われたのが、1945年、終戦の年です。
テレビ放送が始まったのが、1953年。
長いですね。
もう国民的放送番組というところでしょうか。
今年の紅白に選ばれた歌曲の中で私の目を引いた曲があります。
「トイレの神様」、植村花菜さんの歌です。
変な曲名だとは思っていましたが、歌詞を聴いてみると極めて日本人的で懐かしささえ感じる歌です。
親子三世代の交流のあり難さや大切さを教えてくれます。
他のブログに記載してありました歌詞を拝借しました。
出来れば最後まで読んで下さいませ。
*****************************
作詞:植村花菜・山田ひろし 作曲:植村花菜 編曲:寺岡呼人
小3の頃からなぜだかおばあちゃんと暮らしてた
実家の隣だったけどおばあちゃんと暮らしてた
毎日お手伝いをして五目並べもした
でもトイレ掃除だけ苦手な私におばあちゃんがこう言った
トイレには それはそれはキレイな女神様がいるんやで
だから毎日 キレイにしたら 女神様みたいにべっぴんさんになれるんやで
その日から私はトイレをピカピカにし始めた
べっぴんさんに絶対なりたくて毎日磨いてた
買い物に出かけた時には 二人で鴨なんば食べた
新喜劇録画し損ねたおばあちゃんを泣いて責めたりもした
トイレには それはそれはキレイな女神様がいるんやで
だから毎日 キレイにしたら 女神様みたいにべっぴんさんになれるんやで
少し大人になった私は おばあちゃんとぶつかった
家族ともうまくやれなくて 居場所がなくなった
休みの日も家に帰らず 彼氏と遊んだりした
五目並べも鴨なんばも 二人の間から消えてった
どうしてだろう 人は人を傷付け大切なものをなくしてく
いつも味方をしてくれてた おばあちゃん残してひとりきり 家離れた
上京して2年が過ぎておばあちゃんが入院した
痩せて 細くなってしまった。おばあちゃんに会いに行った
「おばあちゃん、ただいまー!」ってわざと
昔みたいに言ってみたけど ちょっと話しただけだったのに
「もう帰りー。」って 病室を出された
次の日の朝 おばあちゃんは静かに眠りについた
まるで まるで 私が来るのを待っていてくれたように
ちゃんと育ててくれたのに 恩返しもしてないのに
いい孫じゃなかったのにこんな私を待っててくれたんやね
トイレには それはそれはキレイな女神様がいるんやで
おばあちゃんがくれた言葉は 今日の私をべっぴんさんにしてくれてるかな
トイレには それはそれはキレイな女神様がいるんやで
だから毎日 キレイにしたら 女神様みたいに
べっぴんさんになれるんやで
気立ての良いお嫁さんになるのが夢だった私は
今日もせっせとトイレを ピーカピカにする
おばあちゃん おばあちゃん ありがとう
おばあちゃん ホンマに ありがとう
******************************
昨日は年末恒例のNHK紅白歌合戦の出場者の発表がありました。
ところで「紅白歌合戦」という番組名も昔懐かしい感じがします。
と言うか、すっかり馴染んでしまいましたし現代風の言い回しをしなくても違和感がありませんよね。
多分、ラジオの時代からあるのですから60年位にはなるのではないでしょうか。
紅白の歴史を調べてみました。
ラジオ放送が行われたのが、1945年、終戦の年です。
テレビ放送が始まったのが、1953年。
長いですね。
もう国民的放送番組というところでしょうか。
今年の紅白に選ばれた歌曲の中で私の目を引いた曲があります。
「トイレの神様」、植村花菜さんの歌です。
変な曲名だとは思っていましたが、歌詞を聴いてみると極めて日本人的で懐かしささえ感じる歌です。
親子三世代の交流のあり難さや大切さを教えてくれます。
他のブログに記載してありました歌詞を拝借しました。
出来れば最後まで読んで下さいませ。
*****************************
作詞:植村花菜・山田ひろし 作曲:植村花菜 編曲:寺岡呼人
小3の頃からなぜだかおばあちゃんと暮らしてた
実家の隣だったけどおばあちゃんと暮らしてた
毎日お手伝いをして五目並べもした
でもトイレ掃除だけ苦手な私におばあちゃんがこう言った
トイレには それはそれはキレイな女神様がいるんやで
だから毎日 キレイにしたら 女神様みたいにべっぴんさんになれるんやで
その日から私はトイレをピカピカにし始めた
べっぴんさんに絶対なりたくて毎日磨いてた
買い物に出かけた時には 二人で鴨なんば食べた
新喜劇録画し損ねたおばあちゃんを泣いて責めたりもした
トイレには それはそれはキレイな女神様がいるんやで
だから毎日 キレイにしたら 女神様みたいにべっぴんさんになれるんやで
少し大人になった私は おばあちゃんとぶつかった
家族ともうまくやれなくて 居場所がなくなった
休みの日も家に帰らず 彼氏と遊んだりした
五目並べも鴨なんばも 二人の間から消えてった
どうしてだろう 人は人を傷付け大切なものをなくしてく
いつも味方をしてくれてた おばあちゃん残してひとりきり 家離れた
上京して2年が過ぎておばあちゃんが入院した
痩せて 細くなってしまった。おばあちゃんに会いに行った
「おばあちゃん、ただいまー!」ってわざと
昔みたいに言ってみたけど ちょっと話しただけだったのに
「もう帰りー。」って 病室を出された
次の日の朝 おばあちゃんは静かに眠りについた
まるで まるで 私が来るのを待っていてくれたように
ちゃんと育ててくれたのに 恩返しもしてないのに
いい孫じゃなかったのにこんな私を待っててくれたんやね
トイレには それはそれはキレイな女神様がいるんやで
おばあちゃんがくれた言葉は 今日の私をべっぴんさんにしてくれてるかな
トイレには それはそれはキレイな女神様がいるんやで
だから毎日 キレイにしたら 女神様みたいに
べっぴんさんになれるんやで
気立ての良いお嫁さんになるのが夢だった私は
今日もせっせとトイレを ピーカピカにする
おばあちゃん おばあちゃん ありがとう
おばあちゃん ホンマに ありがとう
******************************
Posted by misterkei0918 at
08:40
│Comments(2)
2010年11月22日
他人の目を通して自分を見ている
他人の目を通して自分を見ている
「人の目は気にした方がいい」というタイトルのブログを書きました。
有難いものです。
こんなコメントを頂きました。
「人の目だと思っているものは、実は自分の物の見方であったりすることはよくあります。
他者を通じて、そういった自分の見方を再確認していくことで、世界観が広がっていくように感じます」
そうなんです。
他人が見ていると思いがちですが、実は他人の目を借りて自分が見ていることがよくあるのです。
専門的な言い方があるのかもしれませんね。
心理学を研究されている方が若しおられたら教えてくださいませ。
私もそうですが、人の目は気になるものです。
「人が見ている、人に見られている」と思っていることが実は人は少しも私の事を見ているわけでもなく、気にしているわけでもない、意識なんかしていない・・・・・そんな事が良くあります。
自意識過剰というのか。
でも、それは全ての人が経験する事で決して特別な事でもなさそうですよね。
過剰になることがいけないのであって。
逆に頓着の無いのも困りものです。
全く、人の事が気にならない、意にしないというのか、そういう人もおられます。
しかし人間ですから、やはり人の事は気にして欲しいものです。
意識したり、人の振りみて我が振りを治すくらいの甲斐性はあって欲しいとおもいます。
鉄面皮だったりすれば別ですが。
他人の目を借りて自分を見ることであっても、
純粋に人の目を気にするであってもそのことが向上心に繋がったり、努力をする源泉であったり、いい方向に昇華される事が一番大事なことであって、それが歪になったり、萎縮したり、過度の緊張を呼んだりする様では困りものです。
人を意識する事が、却って人への関心を呼び、人の心の中へ自然と飛び込む縁になれば最高でしょう。
「人の目は気にした方がいい」というタイトルのブログを書きました。
有難いものです。
こんなコメントを頂きました。
「人の目だと思っているものは、実は自分の物の見方であったりすることはよくあります。
他者を通じて、そういった自分の見方を再確認していくことで、世界観が広がっていくように感じます」
そうなんです。
他人が見ていると思いがちですが、実は他人の目を借りて自分が見ていることがよくあるのです。
専門的な言い方があるのかもしれませんね。
心理学を研究されている方が若しおられたら教えてくださいませ。
私もそうですが、人の目は気になるものです。
「人が見ている、人に見られている」と思っていることが実は人は少しも私の事を見ているわけでもなく、気にしているわけでもない、意識なんかしていない・・・・・そんな事が良くあります。
自意識過剰というのか。
でも、それは全ての人が経験する事で決して特別な事でもなさそうですよね。
過剰になることがいけないのであって。
逆に頓着の無いのも困りものです。
全く、人の事が気にならない、意にしないというのか、そういう人もおられます。
しかし人間ですから、やはり人の事は気にして欲しいものです。
意識したり、人の振りみて我が振りを治すくらいの甲斐性はあって欲しいとおもいます。
鉄面皮だったりすれば別ですが。
他人の目を借りて自分を見ることであっても、
純粋に人の目を気にするであってもそのことが向上心に繋がったり、努力をする源泉であったり、いい方向に昇華される事が一番大事なことであって、それが歪になったり、萎縮したり、過度の緊張を呼んだりする様では困りものです。
人を意識する事が、却って人への関心を呼び、人の心の中へ自然と飛び込む縁になれば最高でしょう。
Posted by misterkei0918 at
23:41
│Comments(0)
2010年11月21日
人の目は気にした方がいい
人の目は気にした方がいい
周りからは「人の目を気にしなくてもいい」とか教えられたものです。
それを精神的な負担として感じる人、
実力を発揮するのに妨げになる人、
煩わされたくない人、
・
・
などの影響を受ける人がいますから、絶対的にそうだとはいい難いところですが、人間はどうも人の目を気にしたり、言動に惑わされたりする動物ですから所詮逃げ出すわけにはいきません。
また、周りの目や言動を気にするようにできているという事は逆にそのことを利用して新たな人間性が出来上がったり、思わぬ副産物や発展の糧にする力や本能的な能力を有しているような気がするのです。
言わば逆療法とでも言うのでしょうかね。
人の目を心が萎縮する原因と考えたり、精神的な重要な負担とするのであれば、あまり拘る事はいけませんが
私はこれを大いに利用する事で大いに変りえる大事な能力と考えれば極めて大切な人間として与えられた能力のような気がしないでもありません。
恥ずかしがり屋の私にしてみれば、人の目ほど嫌なものはありませんでした。
完全に思考停止に追い込まれますし、人の前に出る事さえも遠慮をしてしまうものです。
遠慮をすると書いたのには理由が存在します。
遠慮とは、積極的、絶対的に嫌とか、何が何でも拒否という理由でもないというところが大事なのです。
という事は何処かに「人の目を受け入れる」側面が存在するという事でもあるのです。
人間はそんなもののような気がします。
「人の目は気にしない方がいい」と考える事は簡単なことですが、人間はそんなに単純にはできていない事、
能力は無限で、何が引き金になるか、動機になるか、励みになるかは誰にも分からないことであり、その大きなインパクトになるのが「人の目」のような気がするのです。
デビュー当時の女優さんが、
最初は田舎の女の子のようだったのが人の目を意識するうちに修練され、自信に満ち溢れ、光り輝く素晴らしい女優に生まれ変わるのは明らかに「人の目」の恩恵を頂いているように思うのです。
これを利用しない手はありませんよね。
利用すると意識すれば、こんなに心地いいことはありませんし、その為の努力だって怠らないものです。
若い頃からこのことを知っているだけでも、大変な収穫のような気がしますね。
この事が自己顕示欲の発露になったり、出しゃばりや、自分だけが優位性を発揮できるような環境づくりに利用するようでは本末転倒です。
人は謙虚で、秩序を守り、自己犠牲の精神こそ大事にされるべきだから。
周りからは「人の目を気にしなくてもいい」とか教えられたものです。
それを精神的な負担として感じる人、
実力を発揮するのに妨げになる人、
煩わされたくない人、
・
・
などの影響を受ける人がいますから、絶対的にそうだとはいい難いところですが、人間はどうも人の目を気にしたり、言動に惑わされたりする動物ですから所詮逃げ出すわけにはいきません。
また、周りの目や言動を気にするようにできているという事は逆にそのことを利用して新たな人間性が出来上がったり、思わぬ副産物や発展の糧にする力や本能的な能力を有しているような気がするのです。
言わば逆療法とでも言うのでしょうかね。
人の目を心が萎縮する原因と考えたり、精神的な重要な負担とするのであれば、あまり拘る事はいけませんが
私はこれを大いに利用する事で大いに変りえる大事な能力と考えれば極めて大切な人間として与えられた能力のような気がしないでもありません。
恥ずかしがり屋の私にしてみれば、人の目ほど嫌なものはありませんでした。
完全に思考停止に追い込まれますし、人の前に出る事さえも遠慮をしてしまうものです。
遠慮をすると書いたのには理由が存在します。
遠慮とは、積極的、絶対的に嫌とか、何が何でも拒否という理由でもないというところが大事なのです。
という事は何処かに「人の目を受け入れる」側面が存在するという事でもあるのです。
人間はそんなもののような気がします。
「人の目は気にしない方がいい」と考える事は簡単なことですが、人間はそんなに単純にはできていない事、
能力は無限で、何が引き金になるか、動機になるか、励みになるかは誰にも分からないことであり、その大きなインパクトになるのが「人の目」のような気がするのです。
デビュー当時の女優さんが、
最初は田舎の女の子のようだったのが人の目を意識するうちに修練され、自信に満ち溢れ、光り輝く素晴らしい女優に生まれ変わるのは明らかに「人の目」の恩恵を頂いているように思うのです。
これを利用しない手はありませんよね。
利用すると意識すれば、こんなに心地いいことはありませんし、その為の努力だって怠らないものです。
若い頃からこのことを知っているだけでも、大変な収穫のような気がしますね。
この事が自己顕示欲の発露になったり、出しゃばりや、自分だけが優位性を発揮できるような環境づくりに利用するようでは本末転倒です。
人は謙虚で、秩序を守り、自己犠牲の精神こそ大事にされるべきだから。
Posted by misterkei0918 at
10:04
│Comments(0)
2010年11月20日
目先の利益を追うな!!
目先の利益を追うな!!
先日のテレビ、WBS(ワールドビジネスサテライト)に孫正義さんが登場されていました。
司会者から「今まで失敗した事はありますか」の問いかけに、
「たくさん失敗しました」
「目先の利益を追っては駄目ですよ。今は利益が出なくても将来に亘ってリスクを負う事が大事ですよ」
「政府が反対しようと、官僚が反対しようと社会のためになるという信念にしたがって突き進みます」
と答えておられます。
少しは字句に間違いがあるかもしれませんが大筋は間違っていないと思います。
私などとの一番の違いはそこなのかもしれませんね。
当然、頭の中身も違いますし人的コネやブレーンも違いますから私どもと比較するのが間違っているのですが、最初はそうでもなかったと思うのです。
つい目先の利益を追ってしまいます。
本当に儲かるのだろうか、
お客様が受け入れてくれるのだろうか、
失敗したらどうしよう、
周りから笑われはしないだろうか、
お金の工面はどうしようか、
・
・
自ら心配の種を掘り起こしているようなものです。
若しかすると、心の底ではそんな自分を肯定している、賞賛している自分が存在するのかもしれませんね。
目先の利益に捕らわれず、実現できた時、成功した時の自分の姿や周りからの賞賛をされる姿を想像できるといいのですが。
それらが心を殆ど支配するようになればしめたものなのですがね。
元来、利益や成功ははじめから存在するものではなく、
どれだけリスクを負うか、
どれだけ信念を貫くか、
どれだけ使命を感じるか、
どれだけ継続し我慢できるのか、
時には自分をどれだけ犠牲に出来るのか、
・
・
などに掛かっている様な気がします。
私どもはつい目先に捕らわれてしまいますが、そんなコツを体得できる人、それが成功者というのかもしれませんね。
『君子は、何事に臨んでも、それが道理に合っているか否かと考えて、その上で行動する。
小人は、何事に臨んでも、それが利益になるか否かと考えて、その上で行動する。
それ故に、君子となるのは困難ではないのである。孔子』
『他の人に一生懸命サービスする人が、最も利益を得る人間である。カーネルサンダース』
『人に施したる利益を記憶するなかれ、人より受けたる恩恵は忘るるなかれ。バイロン』
先日のテレビ、WBS(ワールドビジネスサテライト)に孫正義さんが登場されていました。
司会者から「今まで失敗した事はありますか」の問いかけに、
「たくさん失敗しました」
「目先の利益を追っては駄目ですよ。今は利益が出なくても将来に亘ってリスクを負う事が大事ですよ」
「政府が反対しようと、官僚が反対しようと社会のためになるという信念にしたがって突き進みます」
と答えておられます。
少しは字句に間違いがあるかもしれませんが大筋は間違っていないと思います。
私などとの一番の違いはそこなのかもしれませんね。
当然、頭の中身も違いますし人的コネやブレーンも違いますから私どもと比較するのが間違っているのですが、最初はそうでもなかったと思うのです。
つい目先の利益を追ってしまいます。
本当に儲かるのだろうか、
お客様が受け入れてくれるのだろうか、
失敗したらどうしよう、
周りから笑われはしないだろうか、
お金の工面はどうしようか、
・
・
自ら心配の種を掘り起こしているようなものです。
若しかすると、心の底ではそんな自分を肯定している、賞賛している自分が存在するのかもしれませんね。
目先の利益に捕らわれず、実現できた時、成功した時の自分の姿や周りからの賞賛をされる姿を想像できるといいのですが。
それらが心を殆ど支配するようになればしめたものなのですがね。
元来、利益や成功ははじめから存在するものではなく、
どれだけリスクを負うか、
どれだけ信念を貫くか、
どれだけ使命を感じるか、
どれだけ継続し我慢できるのか、
時には自分をどれだけ犠牲に出来るのか、
・
・
などに掛かっている様な気がします。
私どもはつい目先に捕らわれてしまいますが、そんなコツを体得できる人、それが成功者というのかもしれませんね。
『君子は、何事に臨んでも、それが道理に合っているか否かと考えて、その上で行動する。
小人は、何事に臨んでも、それが利益になるか否かと考えて、その上で行動する。
それ故に、君子となるのは困難ではないのである。孔子』
『他の人に一生懸命サービスする人が、最も利益を得る人間である。カーネルサンダース』
『人に施したる利益を記憶するなかれ、人より受けたる恩恵は忘るるなかれ。バイロン』
Posted by misterkei0918 at
22:17
│Comments(1)
2010年11月20日
快適さに心を奪われていると・・・
快適さに心を奪われていると・・・
快適な環境は、いずれ人の神経を麻痺させる恐ろしい効果をもたらします。
と言うと怖そうですが、
快適さが良くないのではなくてそこに安住の地を求めてはいけない、
安寧であるが故に変化を嫌い、
行動を起こす事の必要性を感じず、
周りに無関心を決め込んでしまう傾向が怖いのです。
人生は常に変化に晒されています。
今の幸せがいつまでも続くものでもありませんし、誰も保障もしてはくれません。
「余り幸せすぎて怖い」という話は良く聞きます。
ですから、備えの姿勢、緩急に備える心構えが必要なんでしょうね。
また、逆に今が不幸と感じていてもそれはいつまでもそうであるわけが無いのです。
でも、幸福な時がそうであるように、不幸な時には不幸から飛び出す準備や心構え、努力が必要ですよね。
不幸の神様は出来るだけ取り付いて離れる事を嫌うものです。
不幸の神様が嫌う事、
それは、真摯に人生を考える人や人のために尽くす人、笑顔を絶やさない人、そして人の為に苦労を厭わない人・・・・・どうもそんな人には寄り付いても長続くはしないようです。
幸福の神様は、浮気者ですからつい心を許すといつの間にか遠ざかってしまうものです。
幸福の神様が好きな事、
実は前記の不幸の神様が嫌う事と一緒なのです。
真摯に人生を考える人
人のために尽くす人、
笑顔を絶やさない人、
そして人の為に苦労を厭わない人・・・・・
自分が今、最高に幸せの渦中にいるとしたらそんな事に心を砕く事が大事なようです。
自分が心地いいと思われることや所、つまりコンフォートゾーン。
それを持続的に出来るだけ、続かせるには先ほどのことですよね。
難しい事ですし、そうであっても不幸や苦難は押し寄せてくるものです。
それは自分だけの原因でない事も多いものです。
という事は、自分にいいことだけではいけないようです。
周りに心遣い、腐心を忘れない事も大事でしょうね。
先ほどの「人の為に苦労を厭わない人」である事も大きく貢献しそうです。
世の中には人の都合の悪い事を率先してする人がいます。
こんな人の先は読めてますよね。
家庭生活も事業も、そんな事を自然体で出来ると嬉しいですよね。
今日から又、頑張りましょう。
快適な環境は、いずれ人の神経を麻痺させる恐ろしい効果をもたらします。
と言うと怖そうですが、
快適さが良くないのではなくてそこに安住の地を求めてはいけない、
安寧であるが故に変化を嫌い、
行動を起こす事の必要性を感じず、
周りに無関心を決め込んでしまう傾向が怖いのです。
人生は常に変化に晒されています。
今の幸せがいつまでも続くものでもありませんし、誰も保障もしてはくれません。
「余り幸せすぎて怖い」という話は良く聞きます。
ですから、備えの姿勢、緩急に備える心構えが必要なんでしょうね。
また、逆に今が不幸と感じていてもそれはいつまでもそうであるわけが無いのです。
でも、幸福な時がそうであるように、不幸な時には不幸から飛び出す準備や心構え、努力が必要ですよね。
不幸の神様は出来るだけ取り付いて離れる事を嫌うものです。
不幸の神様が嫌う事、
それは、真摯に人生を考える人や人のために尽くす人、笑顔を絶やさない人、そして人の為に苦労を厭わない人・・・・・どうもそんな人には寄り付いても長続くはしないようです。
幸福の神様は、浮気者ですからつい心を許すといつの間にか遠ざかってしまうものです。
幸福の神様が好きな事、
実は前記の不幸の神様が嫌う事と一緒なのです。
真摯に人生を考える人
人のために尽くす人、
笑顔を絶やさない人、
そして人の為に苦労を厭わない人・・・・・
自分が今、最高に幸せの渦中にいるとしたらそんな事に心を砕く事が大事なようです。
自分が心地いいと思われることや所、つまりコンフォートゾーン。
それを持続的に出来るだけ、続かせるには先ほどのことですよね。
難しい事ですし、そうであっても不幸や苦難は押し寄せてくるものです。
それは自分だけの原因でない事も多いものです。
という事は、自分にいいことだけではいけないようです。
周りに心遣い、腐心を忘れない事も大事でしょうね。
先ほどの「人の為に苦労を厭わない人」である事も大きく貢献しそうです。
世の中には人の都合の悪い事を率先してする人がいます。
こんな人の先は読めてますよね。
家庭生活も事業も、そんな事を自然体で出来ると嬉しいですよね。
今日から又、頑張りましょう。
Posted by misterkei0918 at
12:43
│Comments(0)
2010年11月20日
大和三山の旅・・・藤原京、平城京を廻る
大和三山の旅・・・藤原京、平城京を廻る
去る11月13・14の両日、久しぶりに奈良へ出かけました。
いつもの山の先輩方との同行です。
総勢10名、家内も一緒です。
遠出のの時には家内が一緒でないとどうも気が進みませんし、楽しみも半減というところでしょうか。
快くついてきてくれましたので有難い話です。
夫婦連れは二組。
冷やかされてみたり、羨ましがられたり。
歴史深い奈良をそういう意味で訪ねるのは本当に初めての事でした。
つい先日まで「平城京遷都1300年祭」が開催されていた直後でしたので、
祭りの後の怖いほどの静けさというか、
「夏草や兵(つわもの)どもが夢の跡」という句を思い出しました。
(松尾芭蕉が門下の河合曽良を共に旅した奥の細道の終点(一応平泉とされる)で 詠んだ句)
13日は
博多から新幹線→JR神戸線→環状線→近鉄に乗って大和八木駅から橿原神宮前着。
ウォーキングの開始です。
橿原神宮前駅→橿原神宮→畝傍(うねび)山→昼食→神武天皇陵→本薬師寺跡→天香久山
→藤原宮跡→耳成山→大和八木駅・・・・・また新大阪駅に戻り夕食のあとホテルへ
14日
新大阪→再び奈良へ→大和西大寺駅→西ノ京駅着→薬師寺→唐招提寺→昼食→近鉄西ノ京駅
→大和西大寺駅→平城京跡見学
→再び新大阪駅へ→博多駅・・・
皆さんは大和三山はご存知でしたか。
私は大和三山は知っていましたがどこにあるのか、三山とはどの山を指すのか、全く知りませんでした。
畝傍(うねび)山、
天香久山、
耳成山
やはり教えていただかないといけない、現地に行かないと分からないということでしょうね。
二日間で約25Kmを歩く行程でしたが、素晴らしく楽しい記憶に残る貴重な経験となりました。
丁度、大きな行事「平城京遷都1300年祭」が終わった後でしたので混雑に巻き込まれる事も無く、しかも紅葉の素晴らしき美しい季節で感激を致しました。
国内にも多くの行くべきところが山積です。機会は自分で率先して作っていかないといけませんね。
お世話を頂いた方々に心から感謝を申し上げたいと思います。
感謝!!感謝!!
25Kmを踏破しましたので家内の疲れが気になりましたが、却って私より元気な有様です。
やはり、歴史深い地の神社仏閣で両手を合わせて拝んだ功徳でしょうかね。
去る11月13・14の両日、久しぶりに奈良へ出かけました。
いつもの山の先輩方との同行です。
総勢10名、家内も一緒です。
遠出のの時には家内が一緒でないとどうも気が進みませんし、楽しみも半減というところでしょうか。
快くついてきてくれましたので有難い話です。
夫婦連れは二組。
冷やかされてみたり、羨ましがられたり。
歴史深い奈良をそういう意味で訪ねるのは本当に初めての事でした。
つい先日まで「平城京遷都1300年祭」が開催されていた直後でしたので、
祭りの後の怖いほどの静けさというか、
「夏草や兵(つわもの)どもが夢の跡」という句を思い出しました。
(松尾芭蕉が門下の河合曽良を共に旅した奥の細道の終点(一応平泉とされる)で 詠んだ句)
13日は
博多から新幹線→JR神戸線→環状線→近鉄に乗って大和八木駅から橿原神宮前着。
ウォーキングの開始です。
橿原神宮前駅→橿原神宮→畝傍(うねび)山→昼食→神武天皇陵→本薬師寺跡→天香久山
→藤原宮跡→耳成山→大和八木駅・・・・・また新大阪駅に戻り夕食のあとホテルへ
14日
新大阪→再び奈良へ→大和西大寺駅→西ノ京駅着→薬師寺→唐招提寺→昼食→近鉄西ノ京駅
→大和西大寺駅→平城京跡見学
→再び新大阪駅へ→博多駅・・・
皆さんは大和三山はご存知でしたか。
私は大和三山は知っていましたがどこにあるのか、三山とはどの山を指すのか、全く知りませんでした。
畝傍(うねび)山、
天香久山、
耳成山
やはり教えていただかないといけない、現地に行かないと分からないということでしょうね。
二日間で約25Kmを歩く行程でしたが、素晴らしく楽しい記憶に残る貴重な経験となりました。
丁度、大きな行事「平城京遷都1300年祭」が終わった後でしたので混雑に巻き込まれる事も無く、しかも紅葉の素晴らしき美しい季節で感激を致しました。
国内にも多くの行くべきところが山積です。機会は自分で率先して作っていかないといけませんね。
お世話を頂いた方々に心から感謝を申し上げたいと思います。
感謝!!感謝!!
25Kmを踏破しましたので家内の疲れが気になりましたが、却って私より元気な有様です。
やはり、歴史深い地の神社仏閣で両手を合わせて拝んだ功徳でしょうかね。
Posted by misterkei0918 at
11:44
│Comments(0)
2010年11月18日
素直な心でありたいけど
素直な心でありたいけど
いつも考える事があります。
もっと素直であれば気も楽になるはずなのに。
ところが人生はそれを許さないのですよね。
人生は素直であれば、気が楽になるほど単純なものではないようです。
ところが素直な人がいますよね。
その人には神様が、素直な心を与えてくださったのでしょう。
ところが私には、ひねくれた、猜疑心の塊のような性格を頂きました。
今生で「しっかり修行しなさい」との思し召し(おぼしめし)のようです。
今更、この場に及んで諦めの悪い事。
もうここまで来たのですから、今までのままで全うしなさいという事でしょう。
人生を歩んでいるとつい持ち合わせていないものに対する欲望が湧いてきます。
なんと往生際(おうじょうぎわ)の悪い事か。
周りにも本当に素直な方がいます。
考えが柔軟で、喜怒哀楽もスムースで物腰も穏やか、柔らかで。
羨ましい限りですが、どうも諦めが肝心なようです。
『もし自分が間違っていたと素直に認める勇気があるなら、災いを転じて福となすことができる。Dカーネギー』
『無理をするな、素直であれ。すべてがこの語句に尽きる、この心構えさえ失わなければ、人は人として十分に生きてゆける。種田山頭火』
『弱い人間は素直になれない。ラロシュフコー』
『うわべになにか「徳」のしるしをつけないような素直な「悪」はない。シェイクスピア』
『幸福を感じるのには童心とか、無心とか、素直さとか言うものが必要である。武者小路実篤』
『素直な心からは謙虚さが生み出され、謙虚さから人の話に耳を傾けるという姿勢が現れてくる。松下幸之助』
いつも考える事があります。
もっと素直であれば気も楽になるはずなのに。
ところが人生はそれを許さないのですよね。
人生は素直であれば、気が楽になるほど単純なものではないようです。
ところが素直な人がいますよね。
その人には神様が、素直な心を与えてくださったのでしょう。
ところが私には、ひねくれた、猜疑心の塊のような性格を頂きました。
今生で「しっかり修行しなさい」との思し召し(おぼしめし)のようです。
今更、この場に及んで諦めの悪い事。
もうここまで来たのですから、今までのままで全うしなさいという事でしょう。
人生を歩んでいるとつい持ち合わせていないものに対する欲望が湧いてきます。
なんと往生際(おうじょうぎわ)の悪い事か。
周りにも本当に素直な方がいます。
考えが柔軟で、喜怒哀楽もスムースで物腰も穏やか、柔らかで。
羨ましい限りですが、どうも諦めが肝心なようです。
『もし自分が間違っていたと素直に認める勇気があるなら、災いを転じて福となすことができる。Dカーネギー』
『無理をするな、素直であれ。すべてがこの語句に尽きる、この心構えさえ失わなければ、人は人として十分に生きてゆける。種田山頭火』
『弱い人間は素直になれない。ラロシュフコー』
『うわべになにか「徳」のしるしをつけないような素直な「悪」はない。シェイクスピア』
『幸福を感じるのには童心とか、無心とか、素直さとか言うものが必要である。武者小路実篤』
『素直な心からは謙虚さが生み出され、謙虚さから人の話に耳を傾けるという姿勢が現れてくる。松下幸之助』
Posted by misterkei0918 at
17:20
│Comments(0)
2010年11月18日
寛容の心について・・・2
寛容の心について・・・2
16日は国連が1995年に採択した「国際寛容デー」でした。
昨日はその当時のアナン事務総長のメッセージが興味深かったので勉強のために全文を引用させて頂きました。
寛容とはどういうことなのでしょうかね。
いつも考えさせられる事です。
辞書を引いてみました。
「度量が大きく、人の言動を良く受け入れる事」
「心が広く、人の過ちを許すこと」
「広い心で人の言う事を聞き入れる事」
「ゆったりとして、こせつかないこと」
象形は「小屋の中にゆったりとしている山羊のさま」
山羊の優しそうな様子を思い浮かべると、寛容の文字の意味も理解できるような気がします。
どうも寛容は許容とも違う意味に受け取れます。
寛容は優しさにも通じるような気もしますが、ただの優しさだけでもなさそうです。
寛容には人生のあり方を示唆する側面が見え隠れするのです。
時には厳しさや耳痛い言葉も寛容の一部でしょう。
相手を受け入れるには、いいも悪いもでは困りものです。
悪い側面はいなしてあげる、正しい道に導いてあげる事が大事であり、時には叱咤も必要なものです。
それが「懐の深さ」であり、本来の意味での「寛容」ではないでしょうか。
決して、迎合や従順、従属、許容でない肝要だと思います。
この付近が私の一番弱いところでしょうね。
何でも受け入れようとするタイプ。
人を戒める事が不得意なところ。
叱る事の出来ない人間。
困ったものです。
16日の「国際寛容デー」にちなんでこんな反省をしてしまいました。
孔子の言葉に出てくる「60歳 耳順」・・・人の言うことが素直に聞けるようになる年代。
これもそうですよね。
反省!!反省!!
16日は国連が1995年に採択した「国際寛容デー」でした。
昨日はその当時のアナン事務総長のメッセージが興味深かったので勉強のために全文を引用させて頂きました。
寛容とはどういうことなのでしょうかね。
いつも考えさせられる事です。
辞書を引いてみました。
「度量が大きく、人の言動を良く受け入れる事」
「心が広く、人の過ちを許すこと」
「広い心で人の言う事を聞き入れる事」
「ゆったりとして、こせつかないこと」
象形は「小屋の中にゆったりとしている山羊のさま」
山羊の優しそうな様子を思い浮かべると、寛容の文字の意味も理解できるような気がします。
どうも寛容は許容とも違う意味に受け取れます。
寛容は優しさにも通じるような気もしますが、ただの優しさだけでもなさそうです。
寛容には人生のあり方を示唆する側面が見え隠れするのです。
時には厳しさや耳痛い言葉も寛容の一部でしょう。
相手を受け入れるには、いいも悪いもでは困りものです。
悪い側面はいなしてあげる、正しい道に導いてあげる事が大事であり、時には叱咤も必要なものです。
それが「懐の深さ」であり、本来の意味での「寛容」ではないでしょうか。
決して、迎合や従順、従属、許容でない肝要だと思います。
この付近が私の一番弱いところでしょうね。
何でも受け入れようとするタイプ。
人を戒める事が不得意なところ。
叱る事の出来ない人間。
困ったものです。
16日の「国際寛容デー」にちなんでこんな反省をしてしまいました。
孔子の言葉に出てくる「60歳 耳順」・・・人の言うことが素直に聞けるようになる年代。
これもそうですよね。
反省!!反省!!
Posted by misterkei0918 at
08:51
│Comments(0)
2010年11月16日
寛容の心について・・・1
寛容の心について・・・1
今日は国連が1995年に採択した「国際寛容デー」らしいです。
皆さんはご存知でしたか。
私は始めて知りました。
当時のアナン事務総長のメッセージを興味深かったので引用しました。
*********************
「国際寛容デー」は、人類にとって最も重要な徳の一つに世界の関心を向けるものです。
寛容は、服従、自己満足、無頓着などと混同されるべきではありません。
寛容とは、人間の多様性に積極的かつ前向きに関わることであり、この多民族・多文化社会において民主主義の根本原理のカギとなるものです。
しかし依然として、不寛容が世界中で何百万もの人々の暮らしを荒廃させています。
21世紀は始まったばかりですが、私たちはすでに、不寛容がいかにすさまじい暴力の形となって表われ、世界中で死や苦悩を引き起こしているかを目撃しています。
だからこそ、不寛容は国連で最も議論を必要とするテーマとなっているのです。
不寛容は日々の生活に見られるものであり、他者の感情、権利、尊厳に対する無神経さにより人を傷つけるような行動や態度として表われます。
私たち一人ひとりが、毎日の暮らしの中で寛容の精神を推し進めなければなりません。
草の根レベルで不寛容や排除と戦うことが、世界的不寛容に打ち勝つ唯一の方法です。
他の多くの不合理な態度と同様、不寛容はしばしば恐怖に根ざしています。
未知のもの、自分と違うもの、他者に対する恐怖です。
このような恐怖の根元には、無知と教育の欠如があります。そこから偏見、憎しみ、差別が育つのです。
教育は、不寛容を予防する最も効果的な手段です。
特に子どもたちにとっては、なぜ人権と人間の尊厳と人間の多様性の尊重が切り離せないのか理解するためにも、寛容について学ぶことが絶対必要です。
教育自体が不寛容のウイルスに冒されていてはなりません。
教育は、人々に自分たちの権利と自由が何であるか、どのように尊重されるべきかを教え、また他人が権利と自由を謳歌することを守りたいという望みを抱かせるようにするものでなければなりません。
もし人間という家族がともに平和に暮らしたいと願うのなら、私たちは互いを知り、受け入れなければなりません。
寛容を推し進めようとするいかなる努力も、その中心に人と人、異なる文化、民族の間の開かれた対話が必要です。
対話なくしては、文化的多様性は脅かされます。
対話なくしては、社会のつながりそのものが危機に瀕します。対話なくして平和はありえません。
この「国際寛容デー」に際し、世界的に尊重すべき原則を私たちそれぞれが積極的に実践しましょう。
寛容のための努力が私たち一人ひとりから始まるのだということを認識しようではありませんか。
********************
今日は国連が1995年に採択した「国際寛容デー」らしいです。
皆さんはご存知でしたか。
私は始めて知りました。
当時のアナン事務総長のメッセージを興味深かったので引用しました。
*********************
「国際寛容デー」は、人類にとって最も重要な徳の一つに世界の関心を向けるものです。
寛容は、服従、自己満足、無頓着などと混同されるべきではありません。
寛容とは、人間の多様性に積極的かつ前向きに関わることであり、この多民族・多文化社会において民主主義の根本原理のカギとなるものです。
しかし依然として、不寛容が世界中で何百万もの人々の暮らしを荒廃させています。
21世紀は始まったばかりですが、私たちはすでに、不寛容がいかにすさまじい暴力の形となって表われ、世界中で死や苦悩を引き起こしているかを目撃しています。
だからこそ、不寛容は国連で最も議論を必要とするテーマとなっているのです。
不寛容は日々の生活に見られるものであり、他者の感情、権利、尊厳に対する無神経さにより人を傷つけるような行動や態度として表われます。
私たち一人ひとりが、毎日の暮らしの中で寛容の精神を推し進めなければなりません。
草の根レベルで不寛容や排除と戦うことが、世界的不寛容に打ち勝つ唯一の方法です。
他の多くの不合理な態度と同様、不寛容はしばしば恐怖に根ざしています。
未知のもの、自分と違うもの、他者に対する恐怖です。
このような恐怖の根元には、無知と教育の欠如があります。そこから偏見、憎しみ、差別が育つのです。
教育は、不寛容を予防する最も効果的な手段です。
特に子どもたちにとっては、なぜ人権と人間の尊厳と人間の多様性の尊重が切り離せないのか理解するためにも、寛容について学ぶことが絶対必要です。
教育自体が不寛容のウイルスに冒されていてはなりません。
教育は、人々に自分たちの権利と自由が何であるか、どのように尊重されるべきかを教え、また他人が権利と自由を謳歌することを守りたいという望みを抱かせるようにするものでなければなりません。
もし人間という家族がともに平和に暮らしたいと願うのなら、私たちは互いを知り、受け入れなければなりません。
寛容を推し進めようとするいかなる努力も、その中心に人と人、異なる文化、民族の間の開かれた対話が必要です。
対話なくしては、文化的多様性は脅かされます。
対話なくしては、社会のつながりそのものが危機に瀕します。対話なくして平和はありえません。
この「国際寛容デー」に際し、世界的に尊重すべき原則を私たちそれぞれが積極的に実践しましょう。
寛容のための努力が私たち一人ひとりから始まるのだということを認識しようではありませんか。
********************
Posted by misterkei0918 at
09:09
│Comments(2)
2010年11月12日
本当に当たってしまいました
本当に当たってしまいました
だいたいくじ運はいいんです。
デパートの一万円の金券も頂くこともありましたし、
忘年会でテレビや
ipad、
商店街の抽選会で一等賞、
高級自転車、
東京往復ペア航空券・・・当然高級ホテルの宿泊付
・
・
今回、宝くじが当たったと言いたいのですが実はそうではありません。
当たる人は欲が無いとも言いますよね。
確かにどうでもいいと思っているのです。
当たればいいし、当たらなくても悔しくもありませんしどうでもいいのです。
今日は、あのホリエモンの「100億稼ぐ仕事術」。
ある成功者の本を購入し、興味深く読ませていただきました。
時々その方からのメールも拝見させていただいていますが、数日前本の感想文のコメントを寄せてくれた人の中から抽選でプレゼントをくれるというものがありました。
当然、コメントは書いて送信しましたが、選ばれるなどは考えてもいませんでしたし、余り期待もしていなかったのです。
今日の正午ごろ、書籍が届きました。
もうすっかりコメントを書いたことなど忘れていました。
どんなプレゼントかも知りませんでしたが、開封してビックリ。
それがあのホリエモンの「100億稼ぐ仕事術」の冊子だったわけです。
明日から、奈良・平安遷都1300年の企画に乗ったわけではありませんが家内と「奈良三山、平城京の旅」へ出かけますが、往復の新幹線の中ででも拝読したいと思っています。
ついでにipadをもって行きますので、時間は却って不足するかもしれませんね。
旅の前日にありがたいプレゼントが当たりました。
だいたいくじ運はいいんです。
デパートの一万円の金券も頂くこともありましたし、
忘年会でテレビや
ipad、
商店街の抽選会で一等賞、
高級自転車、
東京往復ペア航空券・・・当然高級ホテルの宿泊付
・
・
今回、宝くじが当たったと言いたいのですが実はそうではありません。
当たる人は欲が無いとも言いますよね。
確かにどうでもいいと思っているのです。
当たればいいし、当たらなくても悔しくもありませんしどうでもいいのです。
今日は、あのホリエモンの「100億稼ぐ仕事術」。
ある成功者の本を購入し、興味深く読ませていただきました。
時々その方からのメールも拝見させていただいていますが、数日前本の感想文のコメントを寄せてくれた人の中から抽選でプレゼントをくれるというものがありました。
当然、コメントは書いて送信しましたが、選ばれるなどは考えてもいませんでしたし、余り期待もしていなかったのです。
今日の正午ごろ、書籍が届きました。
もうすっかりコメントを書いたことなど忘れていました。
どんなプレゼントかも知りませんでしたが、開封してビックリ。
それがあのホリエモンの「100億稼ぐ仕事術」の冊子だったわけです。
明日から、奈良・平安遷都1300年の企画に乗ったわけではありませんが家内と「奈良三山、平城京の旅」へ出かけますが、往復の新幹線の中ででも拝読したいと思っています。
ついでにipadをもって行きますので、時間は却って不足するかもしれませんね。
旅の前日にありがたいプレゼントが当たりました。
Posted by misterkei0918 at
23:30
│Comments(0)
2010年11月12日
後ろ指差されたい
後ろ指差されたい 平成16年11月17日
後ろ指を指されるというと、なんとなくいけないことで非難されているような距離を置かれるようなそれこそ後ろめたい感じがしますね。
でも言葉どおり捉えて後ろから指を指されたほうがいいと思いませんか。
前からそれこそ自分に向かって指を指されたら威圧的で失礼で腹が立ちません?。
よく人と話をしている時にやたらと私に向かって指を指しながら喋る方がおられます。
その方は悪気があってそうしているわけではないのですが癖なんでしょうね。
映画で見るヒットラーのようで命令口調に見えて先程記したように威圧的で、自分の意見に自信たっぷりで。
こちらの発言や意見には耳を貸しそうに無くて。
そんな時はやはり、指は指さないほうが。
悪口を言われたり非難されるなら後ろからそれとなく言って欲しいもの。
私などは気が弱い方なので前から単刀直入に言われるとグサッと来てしょげ返ってしまいます。
多分一週間は頭から離れず立ち直れないでしょう。
褒める事でも正面切って褒められると照れくさくていても立ってもおれなくなります。
やさしくそれとなくさりげ無く褒めて欲しいものです
。だから後ろから指されたいほうなのです。
それがまた相手に対する心遣いなのでしょうか。
怒る時も、褒める時も、悟す時も。手練手管もいやですが。
でもそれだけが全てではなく前から指を指して意見をしなくてはいけない場面もあることは事実。
口角泡を飛ばして顔色を変えて指を指してやる議論も否定はしません。
必要なのは心意気、心のあり方なのでしょう。
相手を思いやる心のゆとりとでも表現したらいいのでしょうか。
それとなく一歩下がって距離を計り時を見て場所をわきまえて。
後ろ指を指されるというと、なんとなくいけないことで非難されているような距離を置かれるようなそれこそ後ろめたい感じがしますね。
でも言葉どおり捉えて後ろから指を指されたほうがいいと思いませんか。
前からそれこそ自分に向かって指を指されたら威圧的で失礼で腹が立ちません?。
よく人と話をしている時にやたらと私に向かって指を指しながら喋る方がおられます。
その方は悪気があってそうしているわけではないのですが癖なんでしょうね。
映画で見るヒットラーのようで命令口調に見えて先程記したように威圧的で、自分の意見に自信たっぷりで。
こちらの発言や意見には耳を貸しそうに無くて。
そんな時はやはり、指は指さないほうが。
悪口を言われたり非難されるなら後ろからそれとなく言って欲しいもの。
私などは気が弱い方なので前から単刀直入に言われるとグサッと来てしょげ返ってしまいます。
多分一週間は頭から離れず立ち直れないでしょう。
褒める事でも正面切って褒められると照れくさくていても立ってもおれなくなります。
やさしくそれとなくさりげ無く褒めて欲しいものです
。だから後ろから指されたいほうなのです。
それがまた相手に対する心遣いなのでしょうか。
怒る時も、褒める時も、悟す時も。手練手管もいやですが。
でもそれだけが全てではなく前から指を指して意見をしなくてはいけない場面もあることは事実。
口角泡を飛ばして顔色を変えて指を指してやる議論も否定はしません。
必要なのは心意気、心のあり方なのでしょう。
相手を思いやる心のゆとりとでも表現したらいいのでしょうか。
それとなく一歩下がって距離を計り時を見て場所をわきまえて。
Posted by misterkei0918 at
23:01
│Comments(0)
2010年11月12日
対人恐怖症
対人恐怖症 平成16年11月12日
人に会うのが気になってしょうがない、
出来る事なら会いたくない、
会っても人の視線やしぐさが気になる、
目を合わせて言葉が交わせない、
周りが気になる。気後れをする。
……今、私がこんな事を友人知人に語ったら「嘘だろう」とか違う人の話だと受け取るに違いない。
事実今の私にはそんなそぶりはひとかけらも無いから他人がそんな風に思うのは無理も無い話である。
現在はそんな事はないといえば嘘になるけど、所謂普通の人々と同じような感覚に一応なったのかなと思わないではない。
気づき始めたのが中学2年~3年ぐらいと思う。
高校になると自覚が激しくなり社会人になると自分で異常さえ感じるようになってきた。
今思うと性格的に負けず嫌いで、かといって表立って競争するのは嫌い、屈辱感を味わうのがとてもいやでそれを恥ずかしいとさえ思うようになる所謂、羞恥心は強い。
向上心も割と強くて挫折はしたくない。
人との関わりが嫌かというと実はそうではなく気になってしようが無い、人との係わりを深く求めているのである。
人の目が気になる、つまり自分が人を良く見ていることに繋がっているんです。
人に上手が言えない、ある意味、馬鹿真面目で正直者。
人に後ろ指を刺されたりするのがいや。
オーバーな言い方をすれば自分の改造計画に取り掛かり始めた。
24歳で結婚をして、長男が生まれ、次男が生まれた年に脱サラ、その年に起業。
当然、人との接触をしないではこれから家族も路頭に迷う事となる。
その2~3年後からとにかく人に会うことに努力。
毒には毒を持って制す。
目には目を、歯には歯をと、
逆療法、荒療治を試みる事に踏み切った。
経営者団体にも参加、異業種の交流、ボランティア団体、PTA、政治団体……数えたらきりが無いほど。
経営者や異業種は自分で望んで加入したが後はほとんど招請を受けた形での加入である。
今、思うとそんな性格だから加入したら一生懸命に参加する、休まない、人に配慮する、勉強する、情報収集に努める……結果的には多くの方に信用を頂き大事な役回りを担当させられる事となりそれが引き金となって色んな団体や組織から声が掛かり重要な地位を任せられることとなった。
そうなると当然、多くの人の前で話す事も増え数え切れない人々にも接触をしなければいけない。失敗は許されない。
出来て当たり前。
そんな事で訓練に訓練を重ね、なんとか一人前の男として確立されてきたように思う。
失敗するのが嫌いだから用意は周到でありながら片や当たって砕けろ的なところもあるので、あるところまで努力したら諦めも早い。
表立って積極的に前に出ることはしない、控えめを旨としでしゃばらない。
自分としてはそんな荒療治が根本的な解決になるとは全く思いもよらない事でいわば結果が証明したという事ではないでしょうか。
普段会えない方々にも面識が出来信頼を頂き、むしろ天から頂いた災いは福を招いてくれたのである。
清水の舞台から飛び降りる気持ちが一か八かの瀬戸際で私に大きな転機を与えてくれたのである。
人生果敢に挑戦、
まさしくやってやれない事は無いとはこのことでしょうか。
一度しかない人生、出来る事なら明るく楽しく勇気を持って行きたいもの。
その一番大切なものはなんといっても人間関係、人に接する事が上手に出来ればそのほとんどが実現できたようなものです。
想像するに私が現状に甘んじて諦めの境地に陥っていれば今頃家族だけでなく会社をも路頭に迷わす結果になった事は明白。
今でも暗く寂しい人生を歩んでいた事と想像する事は難くない。
これが自分の持って生まれた性格と思い込まないで本来の自分は他にある、今の姿は自分ではない、新しい自分を作り出す、取り戻す勇気を持つか待たないか、その差は雲泥の差が眼前にある。
また克服の過程の中で、その結果副次的に派生する多くのものを得る事が可能なのである。
むしろそのことに着目した方が楽しい結果になるかも。
必ず人それぞれに自分が気づかない隠れた自分が存在する事を発見します。私がその実践者といっても過言ではないと思っています。
人に会うのが気になってしょうがない、
出来る事なら会いたくない、
会っても人の視線やしぐさが気になる、
目を合わせて言葉が交わせない、
周りが気になる。気後れをする。
……今、私がこんな事を友人知人に語ったら「嘘だろう」とか違う人の話だと受け取るに違いない。
事実今の私にはそんなそぶりはひとかけらも無いから他人がそんな風に思うのは無理も無い話である。
現在はそんな事はないといえば嘘になるけど、所謂普通の人々と同じような感覚に一応なったのかなと思わないではない。
気づき始めたのが中学2年~3年ぐらいと思う。
高校になると自覚が激しくなり社会人になると自分で異常さえ感じるようになってきた。
今思うと性格的に負けず嫌いで、かといって表立って競争するのは嫌い、屈辱感を味わうのがとてもいやでそれを恥ずかしいとさえ思うようになる所謂、羞恥心は強い。
向上心も割と強くて挫折はしたくない。
人との関わりが嫌かというと実はそうではなく気になってしようが無い、人との係わりを深く求めているのである。
人の目が気になる、つまり自分が人を良く見ていることに繋がっているんです。
人に上手が言えない、ある意味、馬鹿真面目で正直者。
人に後ろ指を刺されたりするのがいや。
オーバーな言い方をすれば自分の改造計画に取り掛かり始めた。
24歳で結婚をして、長男が生まれ、次男が生まれた年に脱サラ、その年に起業。
当然、人との接触をしないではこれから家族も路頭に迷う事となる。
その2~3年後からとにかく人に会うことに努力。
毒には毒を持って制す。
目には目を、歯には歯をと、
逆療法、荒療治を試みる事に踏み切った。
経営者団体にも参加、異業種の交流、ボランティア団体、PTA、政治団体……数えたらきりが無いほど。
経営者や異業種は自分で望んで加入したが後はほとんど招請を受けた形での加入である。
今、思うとそんな性格だから加入したら一生懸命に参加する、休まない、人に配慮する、勉強する、情報収集に努める……結果的には多くの方に信用を頂き大事な役回りを担当させられる事となりそれが引き金となって色んな団体や組織から声が掛かり重要な地位を任せられることとなった。
そうなると当然、多くの人の前で話す事も増え数え切れない人々にも接触をしなければいけない。失敗は許されない。
出来て当たり前。
そんな事で訓練に訓練を重ね、なんとか一人前の男として確立されてきたように思う。
失敗するのが嫌いだから用意は周到でありながら片や当たって砕けろ的なところもあるので、あるところまで努力したら諦めも早い。
表立って積極的に前に出ることはしない、控えめを旨としでしゃばらない。
自分としてはそんな荒療治が根本的な解決になるとは全く思いもよらない事でいわば結果が証明したという事ではないでしょうか。
普段会えない方々にも面識が出来信頼を頂き、むしろ天から頂いた災いは福を招いてくれたのである。
清水の舞台から飛び降りる気持ちが一か八かの瀬戸際で私に大きな転機を与えてくれたのである。
人生果敢に挑戦、
まさしくやってやれない事は無いとはこのことでしょうか。
一度しかない人生、出来る事なら明るく楽しく勇気を持って行きたいもの。
その一番大切なものはなんといっても人間関係、人に接する事が上手に出来ればそのほとんどが実現できたようなものです。
想像するに私が現状に甘んじて諦めの境地に陥っていれば今頃家族だけでなく会社をも路頭に迷わす結果になった事は明白。
今でも暗く寂しい人生を歩んでいた事と想像する事は難くない。
これが自分の持って生まれた性格と思い込まないで本来の自分は他にある、今の姿は自分ではない、新しい自分を作り出す、取り戻す勇気を持つか待たないか、その差は雲泥の差が眼前にある。
また克服の過程の中で、その結果副次的に派生する多くのものを得る事が可能なのである。
むしろそのことに着目した方が楽しい結果になるかも。
必ず人それぞれに自分が気づかない隠れた自分が存在する事を発見します。私がその実践者といっても過言ではないと思っています。
Posted by misterkei0918 at
22:54
│Comments(0)
2010年11月12日
楽しく生きるために自分が変わる
楽しく生きるために自分が変わる 平成16年7月30日
自分の思うように世の中が動かない、
そんな風に社会が出来ていない、相手が自分を理解してくれない、
私はこんなに情熱を傾けているのに全く解ってくれない。
つまり他人や社会を自分のものさしや価値観で持って接しているとついこんな歯がゆい思いで毎日を過ごしているものです。
地団駄踏んでも世の中や社会、家族や知人は自分が思うように動くものではない。
「生き残る種とは、もっとも強いものではない。もっとも知的なものでもない。
それは、変化にもっともよく適応したものである」(ダーウィン)
他人を変えようとすれば大変な労力が必要であり、所詮無理なこと。
十分な金銭でも積めば自分の思うように動く人が出てくるかもしれない。
そんな守銭奴みたいなことは出来ない。
最も簡単な方法は自分が変わることではなかろうか。
自分が変われば人が変わる、人の見方も変わってくるもの。
変われば周りの世界が楽しく見えてくる。変化する楽しみも覚えてくる。
自分の思うように世の中が動かない、
そんな風に社会が出来ていない、相手が自分を理解してくれない、
私はこんなに情熱を傾けているのに全く解ってくれない。
つまり他人や社会を自分のものさしや価値観で持って接しているとついこんな歯がゆい思いで毎日を過ごしているものです。
地団駄踏んでも世の中や社会、家族や知人は自分が思うように動くものではない。
「生き残る種とは、もっとも強いものではない。もっとも知的なものでもない。
それは、変化にもっともよく適応したものである」(ダーウィン)
他人を変えようとすれば大変な労力が必要であり、所詮無理なこと。
十分な金銭でも積めば自分の思うように動く人が出てくるかもしれない。
そんな守銭奴みたいなことは出来ない。
最も簡単な方法は自分が変わることではなかろうか。
自分が変われば人が変わる、人の見方も変わってくるもの。
変われば周りの世界が楽しく見えてくる。変化する楽しみも覚えてくる。
Posted by misterkei0918 at
22:35
│Comments(0)
2010年11月10日
「人生は楽しいもの」と思っていた方が良さそう
「人生は楽しいもの」と思っていた方が良さそう
人様々です。
人生は嫌な事が多すぎる、
人生は悩み多い、
人生は悲しみの連続、
人生は厳しすぎる・・・・・
或いは、
人生は愉快、
人生は楽しい・・・・・
また、人生はまさしく終わるまで何があるか分からないものです。
もう人生の終焉を迎える瞬間に、最も嫌な、最も起こってほしくない事が唐突に出現するかもしれません。
今まで、苦しみの連続、耐えない悲しみにくれていた人がもう命が絶える瞬間に世の中にはこんなに素晴らしいことがあるんだと感じるほどの事が眼前に出現するかもしれません。
分からないものです。
或いは、「貴女ほど幸せな人はいない」と周りから言われながら、本人は「こんな人生は嫌だ」と主張するかもしれませんよね。
逆に、周りから「あの人ほど、不幸のどん底の人はいない」と言われながら、本人は「幸せな人生だった」などと評するものです。
若い頃は今のような自分であれば、一生を全うできるのかとか、悲惨な障害になると毎日悲嘆に暮れたものですが、振り返ってみると案外そうでもない事に気付きます。
多分、比重的には苦しかったり、悲しかったり、思案投げ首、判断に迷ったり、酷い時には人生を投げ捨てかかったりもしたものです。
ところが、相対的には幸せだった、楽しかったと反省をする人が多いものです。
諦めの発言や、自分を宥(なだ)め好かす意味でそのように考えを落ち着かせる人もいるかもしれませんね。
また、不思議なもので人間は、
「喉元過ぎれば熱さを忘れる」
「時間が解決する」ではありませんが、物事を良法に考える習性を持っているものです。
恨み辛みでも、いつの間にか和らいでいくのがその証左でしょう。
お釈迦様は人生は「生老病死」、四苦といいます。
人生は苦難の道、茨の道と説いておられます。
ですが、「人生は楽しいもの」と思っていた方が気が楽ですし、それによって対処の仕方も前向き、積極的、能動的な解決方法を選択しますし、たとえ厳しい局面を迎えることがあってもそれを次へのステップとして対処するものです。
物事に直面している時、対峙している時は心のゆとりなどありませんし、腐心に終始しているものです。
ところが「人生は楽しいもの」と基本的に思っている人は、その後の行動や反省、振り返った時の感じ方がどうもそうでない人に比較して、大きな差が生じているようにも思えます。
日頃から「人生は楽しいもの」として、捉える癖をつけておきたいものですね。
人は苦しそうなそぶりをしていると、不幸の神様が目ざとく見つけるような気もします。
少々苦しくても笑顔を忘れない。
すると「幸福の女神」が前髪を眼前に垂らして待っていてくれるようですよ。
人様々です。
人生は嫌な事が多すぎる、
人生は悩み多い、
人生は悲しみの連続、
人生は厳しすぎる・・・・・
或いは、
人生は愉快、
人生は楽しい・・・・・
また、人生はまさしく終わるまで何があるか分からないものです。
もう人生の終焉を迎える瞬間に、最も嫌な、最も起こってほしくない事が唐突に出現するかもしれません。
今まで、苦しみの連続、耐えない悲しみにくれていた人がもう命が絶える瞬間に世の中にはこんなに素晴らしいことがあるんだと感じるほどの事が眼前に出現するかもしれません。
分からないものです。
或いは、「貴女ほど幸せな人はいない」と周りから言われながら、本人は「こんな人生は嫌だ」と主張するかもしれませんよね。
逆に、周りから「あの人ほど、不幸のどん底の人はいない」と言われながら、本人は「幸せな人生だった」などと評するものです。
若い頃は今のような自分であれば、一生を全うできるのかとか、悲惨な障害になると毎日悲嘆に暮れたものですが、振り返ってみると案外そうでもない事に気付きます。
多分、比重的には苦しかったり、悲しかったり、思案投げ首、判断に迷ったり、酷い時には人生を投げ捨てかかったりもしたものです。
ところが、相対的には幸せだった、楽しかったと反省をする人が多いものです。
諦めの発言や、自分を宥(なだ)め好かす意味でそのように考えを落ち着かせる人もいるかもしれませんね。
また、不思議なもので人間は、
「喉元過ぎれば熱さを忘れる」
「時間が解決する」ではありませんが、物事を良法に考える習性を持っているものです。
恨み辛みでも、いつの間にか和らいでいくのがその証左でしょう。
お釈迦様は人生は「生老病死」、四苦といいます。
人生は苦難の道、茨の道と説いておられます。
ですが、「人生は楽しいもの」と思っていた方が気が楽ですし、それによって対処の仕方も前向き、積極的、能動的な解決方法を選択しますし、たとえ厳しい局面を迎えることがあってもそれを次へのステップとして対処するものです。
物事に直面している時、対峙している時は心のゆとりなどありませんし、腐心に終始しているものです。
ところが「人生は楽しいもの」と基本的に思っている人は、その後の行動や反省、振り返った時の感じ方がどうもそうでない人に比較して、大きな差が生じているようにも思えます。
日頃から「人生は楽しいもの」として、捉える癖をつけておきたいものですね。
人は苦しそうなそぶりをしていると、不幸の神様が目ざとく見つけるような気もします。
少々苦しくても笑顔を忘れない。
すると「幸福の女神」が前髪を眼前に垂らして待っていてくれるようですよ。
Posted by misterkei0918 at
15:21
│Comments(0)
2010年11月09日
ラストラブレターとは?
ラストラブレターとは?
今日、生命保険の話を聞いていましたらイギリスなどでは生命保険の事を「ラストラブレター」と言うということを教えていただきました。
つまり「残る家族が金銭的なことや、苦労をすることの無いように、若しくは路頭に迷ったり、生活の基盤を失う事の無いように懇願して掛けた保険」をそのように表現しているようです。
確かに、大黒柱を失う事は生活の根底から大変な事態を迎えることになってしまいますし、希望や夢さえも吹き飛んでしまいます。
今は影の薄い主人、言葉だけ主人になってはいますが、その主人の命が途絶えたり、健康上の理由で収入の道が途絶えたとしたら家族にとっては霹靂の事態を迎えることになります。
良く聞く話です。
大学への進学をやめてしまった子ども、
或いは、パートやアルバイトに出る事をになった。
そうならないために備えと言うことでしょう。
「ラストラブレター」とは上手に表現するものです。
生命保険を悪企みの道具にしてしまう人間もいます。
命との引き換えに保険を掛けられたり。
「ラストラブレター」
聞いたときに一瞬、「息を引き取る瞬間に書かれる妻、若しくは夫への最後の恋文」と解釈したのです。
とんでもない間違いでした。
でもそんな事があっていいですよね。
生涯連れ添った人に、今生の別れをしたためた恋文。
でも、こんな事になったら或いは残された人が可哀想かもしれませんね。
いつまでも引きずってしまいそうです。
この世から去った人の事は一時的には、悔恨(かいこん)の情に駆られ、心の塞ぎこむことではありますがいつの日にかは良き思い出や心の拠り所としての存在と化していくものです。
恋文ならまだしも、怨念、恨み、辛みだったら大変な事です。
家庭争議の引き金にもなってしまいます。
いずれにしても、人の命の尊さや儚さは今昔変るものではありませんし変ってはいけませんが、生命を保険化してしまう人間の知恵も片方では賞賛してあげないといけないかもしれませんね。
それによって救われる多くの人々がいるのですから。
今日、生命保険の話を聞いていましたらイギリスなどでは生命保険の事を「ラストラブレター」と言うということを教えていただきました。
つまり「残る家族が金銭的なことや、苦労をすることの無いように、若しくは路頭に迷ったり、生活の基盤を失う事の無いように懇願して掛けた保険」をそのように表現しているようです。
確かに、大黒柱を失う事は生活の根底から大変な事態を迎えることになってしまいますし、希望や夢さえも吹き飛んでしまいます。
今は影の薄い主人、言葉だけ主人になってはいますが、その主人の命が途絶えたり、健康上の理由で収入の道が途絶えたとしたら家族にとっては霹靂の事態を迎えることになります。
良く聞く話です。
大学への進学をやめてしまった子ども、
或いは、パートやアルバイトに出る事をになった。
そうならないために備えと言うことでしょう。
「ラストラブレター」とは上手に表現するものです。
生命保険を悪企みの道具にしてしまう人間もいます。
命との引き換えに保険を掛けられたり。
「ラストラブレター」
聞いたときに一瞬、「息を引き取る瞬間に書かれる妻、若しくは夫への最後の恋文」と解釈したのです。
とんでもない間違いでした。
でもそんな事があっていいですよね。
生涯連れ添った人に、今生の別れをしたためた恋文。
でも、こんな事になったら或いは残された人が可哀想かもしれませんね。
いつまでも引きずってしまいそうです。
この世から去った人の事は一時的には、悔恨(かいこん)の情に駆られ、心の塞ぎこむことではありますがいつの日にかは良き思い出や心の拠り所としての存在と化していくものです。
恋文ならまだしも、怨念、恨み、辛みだったら大変な事です。
家庭争議の引き金にもなってしまいます。
いずれにしても、人の命の尊さや儚さは今昔変るものではありませんし変ってはいけませんが、生命を保険化してしまう人間の知恵も片方では賞賛してあげないといけないかもしれませんね。
それによって救われる多くの人々がいるのですから。
Posted by misterkei0918 at
18:23
│Comments(0)
2010年11月08日
人生はどうも物事に対する考え方で決まっている?
人生はどうも物事に対する考え方で決まっている?
良く「あの人は暗い、明るい」、
「あの人はネガティブ、ポジティブ」
「彼は後ろ向き、前向き」
「物事に消極的、積極的」
などと言います。
それは個々の人間の持ち味だったり、個性だったりしますから、だからいけないとか、改めなさいとか言う事ではありませんが、一般論として心豊かに、明るく楽しく生きている人は
「明るい」
「ポジティブ」
「前向き」
「積極的」な人間がそうであるようです。
だから悪いと言う事ではないのです。
暗くても、ネガティブでも、後ろ向き消極的でも人生を真摯に生きていることには間違いないでしょうし、だからこそそれが人生に有利に働く事だってありますよね。
友人も色んなタイプがいます。
概して言うと、先ほどのような事は当たらずとも遠からず!!
人付き合いが上手なのもやはりそうです。
社長仲間もそうです。
明るい、ポジティブ、前向き、積極的。
私は若い頃は、
そうですね、約35歳くらいまではどちらかと言うと暗いほどではなくても消極的。
多くの経営者や著名な方々との付き合いの中でふと気付いたのです。
「人生はどうも物事に対する考え方で決まっている」
苦難に立ち向かっても、決して怯まず、挑戦的で、笑顔を絶やさない。
歓喜は自分だけのものにせず、周りに分け与える事を忘れず、惜しまない。
艱難辛苦の中からでも、何かを得ようと務め、挑戦の時に生かすことを心に秘めている。
そんな気がします。
人は一筋縄では、そのようにはなれませんが心の片隅に人生はそのようなものである事を肝に銘じておくことでも良さそうですよ。
「人生はどうも物事に対する考え方で決まっている」
『どんな不幸な出来事でも、賢人はそこから自分の利になることを引き出す。
しかし、どんな幸運な出来事でも、愚者はそこから禍を引き出す。ラロシュフコー』
良く「あの人は暗い、明るい」、
「あの人はネガティブ、ポジティブ」
「彼は後ろ向き、前向き」
「物事に消極的、積極的」
などと言います。
それは個々の人間の持ち味だったり、個性だったりしますから、だからいけないとか、改めなさいとか言う事ではありませんが、一般論として心豊かに、明るく楽しく生きている人は
「明るい」
「ポジティブ」
「前向き」
「積極的」な人間がそうであるようです。
だから悪いと言う事ではないのです。
暗くても、ネガティブでも、後ろ向き消極的でも人生を真摯に生きていることには間違いないでしょうし、だからこそそれが人生に有利に働く事だってありますよね。
友人も色んなタイプがいます。
概して言うと、先ほどのような事は当たらずとも遠からず!!
人付き合いが上手なのもやはりそうです。
社長仲間もそうです。
明るい、ポジティブ、前向き、積極的。
私は若い頃は、
そうですね、約35歳くらいまではどちらかと言うと暗いほどではなくても消極的。
多くの経営者や著名な方々との付き合いの中でふと気付いたのです。
「人生はどうも物事に対する考え方で決まっている」
苦難に立ち向かっても、決して怯まず、挑戦的で、笑顔を絶やさない。
歓喜は自分だけのものにせず、周りに分け与える事を忘れず、惜しまない。
艱難辛苦の中からでも、何かを得ようと務め、挑戦の時に生かすことを心に秘めている。
そんな気がします。
人は一筋縄では、そのようにはなれませんが心の片隅に人生はそのようなものである事を肝に銘じておくことでも良さそうですよ。
「人生はどうも物事に対する考え方で決まっている」
『どんな不幸な出来事でも、賢人はそこから自分の利になることを引き出す。
しかし、どんな幸運な出来事でも、愚者はそこから禍を引き出す。ラロシュフコー』
Posted by misterkei0918 at
22:25
│Comments(0)
2010年11月08日
いつ如何なる時でも
いつ如何なる時でも
難しい時代になったものです。
企業でも普通ではなく。何処かで秀でている人間でなくてはいつ自分の立場を失ってしまうかもしれません。
昔、「生き馬の目を抜く」という言葉がありましたが、今ほど当てはまる時代は無いようです。
また、一旦失業してしまうと余程訴える能力が存在しないと重宝はされない時代です。
採用はされても、それなりのポジションを得る事は大変な事であり、人並み以上を今ほど要求される時代は無かったでしょうし、これからもそんな状況は続くでしょうし、或いは加速していくのかもしれません。
若しかすると油断大敵、足元を掬う輩も出没するものです。
しかも手練手管を巧みに使って。
こんな時代であれば、
どんな時でも自分の人間性に磨きをかけ、
研究や勉強に時間を惜しまず、
人間関係の構築に心を砕く・・・
そんな考えを若い頃から持つことが大事と思われます。
私のように馬齢を重ねてからでは「時既に遅し」。
今頃になって「如何なる時でも」等といっていると所詮体に影響が出てくるか、精神が不安定状態になってしまうか。
あるプロスポーツマンが言っています。
「我々は体を酷使し、時間を惜しみ、苦しみぬいて自分の地位を確立しようとする」
「ところがサラリーマンは企業に就職した途端、努力を忘れ、時間を浪費する」
「取り分け、アフターファイブに神経を使い過ぎる」
彼が言うには、サラリーマンが我々と同じ様な気持ちで努力するなら必ず人並み以上の人間になると言います。
言われてみるとそうですね。
企業という微温湯(ぬるまゆ)に浸かり、自らが茹で蛙に好んでなっていると言うのです。
考えてみました。
20歳から80歳まで、一日一時間を何かの為に使ったとしたら、累計22,000時間を生み出す事になります。
22,000時間は日に換算すると900日。
とんでもない時間です。
浪費の1時間にするか、人生を豊に出来る1時間にするか。
人によっては、酒を飲んでいるほうが余程生産的という発想の人もいるかもしれません。
でも1時間ですから、酒を飲んでも1時間を作れないことは無いでしょう。
例えば、友人と10時まで飲んだら、家に帰って十分に1時間は確保できるはず。
或いは、友達付き合いがより大事といっても、毎日夜中まで付き合っている訳ではないでしょう。
1時間は事も無く、取れるはず。
上手なものです。
出来ない理由、やらない理由作り。
私も年は重ねても、今からでも「如何なる時でも」の気持ちを持って挑戦的に頑張ってみたいものです。
老骨に鞭打ってでも!!
難しい時代になったものです。
企業でも普通ではなく。何処かで秀でている人間でなくてはいつ自分の立場を失ってしまうかもしれません。
昔、「生き馬の目を抜く」という言葉がありましたが、今ほど当てはまる時代は無いようです。
また、一旦失業してしまうと余程訴える能力が存在しないと重宝はされない時代です。
採用はされても、それなりのポジションを得る事は大変な事であり、人並み以上を今ほど要求される時代は無かったでしょうし、これからもそんな状況は続くでしょうし、或いは加速していくのかもしれません。
若しかすると油断大敵、足元を掬う輩も出没するものです。
しかも手練手管を巧みに使って。
こんな時代であれば、
どんな時でも自分の人間性に磨きをかけ、
研究や勉強に時間を惜しまず、
人間関係の構築に心を砕く・・・
そんな考えを若い頃から持つことが大事と思われます。
私のように馬齢を重ねてからでは「時既に遅し」。
今頃になって「如何なる時でも」等といっていると所詮体に影響が出てくるか、精神が不安定状態になってしまうか。
あるプロスポーツマンが言っています。
「我々は体を酷使し、時間を惜しみ、苦しみぬいて自分の地位を確立しようとする」
「ところがサラリーマンは企業に就職した途端、努力を忘れ、時間を浪費する」
「取り分け、アフターファイブに神経を使い過ぎる」
彼が言うには、サラリーマンが我々と同じ様な気持ちで努力するなら必ず人並み以上の人間になると言います。
言われてみるとそうですね。
企業という微温湯(ぬるまゆ)に浸かり、自らが茹で蛙に好んでなっていると言うのです。
考えてみました。
20歳から80歳まで、一日一時間を何かの為に使ったとしたら、累計22,000時間を生み出す事になります。
22,000時間は日に換算すると900日。
とんでもない時間です。
浪費の1時間にするか、人生を豊に出来る1時間にするか。
人によっては、酒を飲んでいるほうが余程生産的という発想の人もいるかもしれません。
でも1時間ですから、酒を飲んでも1時間を作れないことは無いでしょう。
例えば、友人と10時まで飲んだら、家に帰って十分に1時間は確保できるはず。
或いは、友達付き合いがより大事といっても、毎日夜中まで付き合っている訳ではないでしょう。
1時間は事も無く、取れるはず。
上手なものです。
出来ない理由、やらない理由作り。
私も年は重ねても、今からでも「如何なる時でも」の気持ちを持って挑戦的に頑張ってみたいものです。
老骨に鞭打ってでも!!
Posted by misterkei0918 at
21:49
│Comments(0)
2010年11月07日
救急外来に3度も飛び込んでしまいました
救急外来に3度も飛び込んでしまいました
自慢になることでもありませんし、読まれる方の参考にもなりませんが3度も救急に走ってしまいました。
或いは反面教師くらいにはなるかも知れませんね。
飛び込んだ先は福岡日赤病院。
痛さの原因は腎臓結石。
腎臓から尿道へ落ちてくる石が神経を刺激することによる痛み。
10年位前の時にも救急に飛び込みましたが、この時の先生に「今、治しておかないと人工透析を受ける体になってしまいますよ」と言われたのですが。
一度目は、1日の夕方、5時過ぎだったでしょうか。
朝から幾らか可笑しい事は分かっていたのですが、大丈夫と踏んでいたのです。
あまりの痛さに時間まで見るゆとりがありませんでした。
レントゲン撮影、血液検査、尿を採取、超音波で腹部を検査、点滴をしていただき座薬の痛み止めを持参して家路へ。
ほぼ5年に一度経験することになります。
七転八倒するほどの痛さにも係わらず、遣り過ごした後には痛みのかけらも残ることは無く、このことが結局は治療する事も、勧められる入院もしないで約30年を有に越えてしまいました。
痛みは幾らか治まったのでその夜は痛み止めを飲みながら何とか自宅で就寝。
2日は、やはり朝から変です。
食事の度に痛み止めの服用は止められません。
夕方は大事な会議です、どうしても出席しなくてはいけません。
ところが痛みが激しくなってきました。
一旦は、痛みの余り出席を断念すべく、自宅へ戻りかけましたが私の性格上、欠席は決して許しません。
痛みを押して参加することにしました。
何とか会議をこなしましたが、引き続いて懇親会です。
ビールジョッキ1杯で、乾杯を済ませ帰るつもりでしたが結局は最後まで、数杯のビールを飲んでしまいました。
思いの片隅にはビールで尿道結石を押し流してしまおうとする魂胆もあったことは間違いあありませんでした。
ところがそれからが大変だったのです。
その日の夜中は朝を迎えるまで、寝床の中で転げまわっていたのです。
頂いた座薬も数度使ったのですが、全く効き目なし。
二度目は3日、祭日。
先ほどの話のように夜中は痛みの極み状態。
朝の5時過ぎに再び、日赤病院へ。
対応していただいた先生が整形外科の担当と言うことで全く処置が出来ず。
偶然に3日・祭日の宿直が泌尿器科の先生で9時半に来られるという事で、その間救急室のベットに寝かせていただきましたが、先生がお見えになるまでの時間の長い事。
痛み止めの注射をして頂き、不思議な事に痛みが確実に引いていきます。
座薬の痛み止めが効かないことを申し上げ、飲み薬に切り替えていただき自宅へ。
お昼までは100%ではありませんが幾らかOKでした。
ところが夕方4時近くから又おかしくなって来ました。
三度目です。3日5時ごろ病院へ。
家内に事前の電話をしてもらい再び救急外来へ飛び込む始末。
1日に2度も救急に飛び込んで来る患者は珍しいでしょうね。
同じ泌尿器の先生がまだおられましたので、朝ほどの痛み止めに注射をしてもらい、痛みを和らげてもらう。
先生からは「今度、来られたら入院ですよ。泌尿器病棟にはベットは空いていませんがそれは何とかします」との事。
入院を絶対したくない私としては今回を終わりにすべく絶対に痛みを終息させねばなりません。
その願いが通じたのか、先生の脅しが効いたのか痛みが時間と共に和らいでいきます。
その夜は幾らか落ち着いての就寝でした。
4日と5日は、万全ではありませんでしたが、本来の痛みまではいきません。
尿道の石が、外に排泄できたのは6日の昼ごろのような気がします。
何度もこんな経験をすると、不思議なものです。
尿道から排泄される石の感覚まで分かるようになってしまいます。
自慢にもなりませんね、こんな事。
自慢になることでもありませんし、読まれる方の参考にもなりませんが3度も救急に走ってしまいました。
或いは反面教師くらいにはなるかも知れませんね。
飛び込んだ先は福岡日赤病院。
痛さの原因は腎臓結石。
腎臓から尿道へ落ちてくる石が神経を刺激することによる痛み。
10年位前の時にも救急に飛び込みましたが、この時の先生に「今、治しておかないと人工透析を受ける体になってしまいますよ」と言われたのですが。
一度目は、1日の夕方、5時過ぎだったでしょうか。
朝から幾らか可笑しい事は分かっていたのですが、大丈夫と踏んでいたのです。
あまりの痛さに時間まで見るゆとりがありませんでした。
レントゲン撮影、血液検査、尿を採取、超音波で腹部を検査、点滴をしていただき座薬の痛み止めを持参して家路へ。
ほぼ5年に一度経験することになります。
七転八倒するほどの痛さにも係わらず、遣り過ごした後には痛みのかけらも残ることは無く、このことが結局は治療する事も、勧められる入院もしないで約30年を有に越えてしまいました。
痛みは幾らか治まったのでその夜は痛み止めを飲みながら何とか自宅で就寝。
2日は、やはり朝から変です。
食事の度に痛み止めの服用は止められません。
夕方は大事な会議です、どうしても出席しなくてはいけません。
ところが痛みが激しくなってきました。
一旦は、痛みの余り出席を断念すべく、自宅へ戻りかけましたが私の性格上、欠席は決して許しません。
痛みを押して参加することにしました。
何とか会議をこなしましたが、引き続いて懇親会です。
ビールジョッキ1杯で、乾杯を済ませ帰るつもりでしたが結局は最後まで、数杯のビールを飲んでしまいました。
思いの片隅にはビールで尿道結石を押し流してしまおうとする魂胆もあったことは間違いあありませんでした。
ところがそれからが大変だったのです。
その日の夜中は朝を迎えるまで、寝床の中で転げまわっていたのです。
頂いた座薬も数度使ったのですが、全く効き目なし。
二度目は3日、祭日。
先ほどの話のように夜中は痛みの極み状態。
朝の5時過ぎに再び、日赤病院へ。
対応していただいた先生が整形外科の担当と言うことで全く処置が出来ず。
偶然に3日・祭日の宿直が泌尿器科の先生で9時半に来られるという事で、その間救急室のベットに寝かせていただきましたが、先生がお見えになるまでの時間の長い事。
痛み止めの注射をして頂き、不思議な事に痛みが確実に引いていきます。
座薬の痛み止めが効かないことを申し上げ、飲み薬に切り替えていただき自宅へ。
お昼までは100%ではありませんが幾らかOKでした。
ところが夕方4時近くから又おかしくなって来ました。
三度目です。3日5時ごろ病院へ。
家内に事前の電話をしてもらい再び救急外来へ飛び込む始末。
1日に2度も救急に飛び込んで来る患者は珍しいでしょうね。
同じ泌尿器の先生がまだおられましたので、朝ほどの痛み止めに注射をしてもらい、痛みを和らげてもらう。
先生からは「今度、来られたら入院ですよ。泌尿器病棟にはベットは空いていませんがそれは何とかします」との事。
入院を絶対したくない私としては今回を終わりにすべく絶対に痛みを終息させねばなりません。
その願いが通じたのか、先生の脅しが効いたのか痛みが時間と共に和らいでいきます。
その夜は幾らか落ち着いての就寝でした。
4日と5日は、万全ではありませんでしたが、本来の痛みまではいきません。
尿道の石が、外に排泄できたのは6日の昼ごろのような気がします。
何度もこんな経験をすると、不思議なものです。
尿道から排泄される石の感覚まで分かるようになってしまいます。
自慢にもなりませんね、こんな事。
Posted by misterkei0918 at
23:42
│Comments(1)