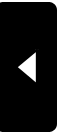2010年08月07日
どうする事が正しいのか
どうする事が正しいのか
人生には様々な事が付き纏います。
一日たりとも、何事もなく過ぎてゆくと事はありません。
正しい解決方法を見出すのにいつも考えます。
むしろ、そうだからこそ生きがいがあったり感慨も深まるものです。
ところが付き纏う諸問題をどのように解決する事がいいのか迷う事が度々です。
私のよううな未熟な者は、迷いが迷いを呼んでどのように解決策を見出すのさえおぼつかないものです。
糸口がつかめないとか、問題そのものの十分な正しい把握が出来ない事もありますが。
いつも思うのですが、正しい解決方法が最初から分かっていれば悩む事もいりませんしトラブルなど存在しないかもしれませんね。
「どうする事が正しいのか」という事と、
「自分が正しいと信じる事」や
「自分を有利にすること」
とは別のことが多いですよね。
「自分が正しいと信じる事」
得てして自分が正しいと思っていることが実は間違いであったり、真実ではなかったりすることも多いものです。
「自分を有利にすること」
自分を有利にしようとする事が実は解決を妨げたり、問題をこじらせたり、とんでもない方向へ飛び火をしたりするものです。
所詮、我田引水や自己利益への誘導は、逆に相手に不利益を与えようとするものであり、信頼関係や関わりまでも損なってしまうものです。
壊した関係はもう戻す事は不可能でしょう。
やはり正しい解決をしたいと言う思いや願望が大切かもしれませんね。
「念ずれば通ず」とも言います。
いい解決策を思う心は十分相手にも通じるものです。
また、正しいと思われる判断は、相手があるとしたら十分な説明が必要ですよね。
こちらにとってマイナスのこともありますし、相手にとって不利益な事もありますのでそのときほど時間を要して説明する事でしょうか。
自分の不利益ばかりの説明は聞いていて嫌なものですし、人としての足元を見られてしまいます。
それと自分で決めたことは、幾らかの迷いがあっても信じて進む事ではないでしょうか。
考える事は必要ですが、余りにも埋没してしまうと正しい事を見失ってしまうものです。
結果オーライで、余り後悔しないことも大事な事のようです。
自分が正しい道として選択した結果が思わしくなくても。
相手があるとしたら、「負けるが勝ち」などということもあります。
そのほうがむしろ今後の人生には有利に働いたりするものです。
勝ちに拘らない生き方、
時には開き直りの人生もいいかもしれませんね。
人生には様々な事が付き纏います。
一日たりとも、何事もなく過ぎてゆくと事はありません。
正しい解決方法を見出すのにいつも考えます。
むしろ、そうだからこそ生きがいがあったり感慨も深まるものです。
ところが付き纏う諸問題をどのように解決する事がいいのか迷う事が度々です。
私のよううな未熟な者は、迷いが迷いを呼んでどのように解決策を見出すのさえおぼつかないものです。
糸口がつかめないとか、問題そのものの十分な正しい把握が出来ない事もありますが。
いつも思うのですが、正しい解決方法が最初から分かっていれば悩む事もいりませんしトラブルなど存在しないかもしれませんね。
「どうする事が正しいのか」という事と、
「自分が正しいと信じる事」や
「自分を有利にすること」
とは別のことが多いですよね。
「自分が正しいと信じる事」
得てして自分が正しいと思っていることが実は間違いであったり、真実ではなかったりすることも多いものです。
「自分を有利にすること」
自分を有利にしようとする事が実は解決を妨げたり、問題をこじらせたり、とんでもない方向へ飛び火をしたりするものです。
所詮、我田引水や自己利益への誘導は、逆に相手に不利益を与えようとするものであり、信頼関係や関わりまでも損なってしまうものです。
壊した関係はもう戻す事は不可能でしょう。
やはり正しい解決をしたいと言う思いや願望が大切かもしれませんね。
「念ずれば通ず」とも言います。
いい解決策を思う心は十分相手にも通じるものです。
また、正しいと思われる判断は、相手があるとしたら十分な説明が必要ですよね。
こちらにとってマイナスのこともありますし、相手にとって不利益な事もありますのでそのときほど時間を要して説明する事でしょうか。
自分の不利益ばかりの説明は聞いていて嫌なものですし、人としての足元を見られてしまいます。
それと自分で決めたことは、幾らかの迷いがあっても信じて進む事ではないでしょうか。
考える事は必要ですが、余りにも埋没してしまうと正しい事を見失ってしまうものです。
結果オーライで、余り後悔しないことも大事な事のようです。
自分が正しい道として選択した結果が思わしくなくても。
相手があるとしたら、「負けるが勝ち」などということもあります。
そのほうがむしろ今後の人生には有利に働いたりするものです。
勝ちに拘らない生き方、
時には開き直りの人生もいいかもしれませんね。
Posted by misterkei0918 at
19:43
│Comments(0)
2010年08月07日
人の関係が希薄になっていく恐ろしさ
人の関係が希薄になっていく恐ろしさ
最近のニュースに改めて深刻に考えさせられた人は多いのではないでしょうか。
つい数日前の子供二人を置き去りにして死亡させた事件。
胸が詰まってしまいます。
親って何なんだ。
子供って何なのか。
命ってそんなに軽いものなのか。
人はそんなに残虐になれるのか。
社会は?
近隣は?
肉親は?
相手の男は?
コミュニティって存在しないのか。
人々の心はどこまで荒んでいくのか。
相談する人はいなかったのか。
逃げ込めるところは?
そんなに簡単に子供を作っていいのか。
母性は?
書いているだけで涙がこぼれます。
家族だけは最後の砦として、社会は成り立っている筈なのにどこまで崩壊を続けるのか。
せめて、地域は一番心が落ち着いて、助け合い、面倒を見合い、姿を確認し合い、気に掛け合う身近な存在であった筈なのに。
むしろ人との係わりを捨て、あくまでもビジネスライクに過ごす事や「忙しい」の合言葉の元に如何にもそれが最前線で在るかのごとき錯角をもち、人間としての本来の「人との関わりこそ大事」である事を忘れ去ってしまったのではないでしょうか。
煩わしいこと、
どろどろした事、
面倒くさい事、
おせっかいすぎる事、
立ち入りすぎる事、
甘えが過ぎる事、
・
・
・
家族で在ればこその事も存在するものです。
ですが、そこが人間の良さだったり、一旦緩急あったときの最大の防御であったり、支えだったり、勇気の源泉だったりするものです。
子供であれば尚更の事。
この頃の100歳以上の方々の所在や行方の問題にしてもしかり。
母親の行方を30年も知らないとか、引っ越していったきりどうなったか知らないとか。
死んでいるも生きているも分からないとか。
昨年の敬老の日に発表された100歳以上の方が約45,000人。
数字さえも疑ってしまいます。
行政も可笑しくなっているような気がしてなりません。
経済を優先する余り、家族の絆を置き去りにするか、捨て去ろうとしているとしか思えないのです。
政治も可笑しいです。
素人政治でどうするのでしょうか。
もう一度、原点へ立ち戻らないとどうしようもない時代が来るような気がしますが如何でしょうかね。
本来からして、大事にしなくてはいけない事をなおざりにするつけはまもなく来るのではないでしょうか。
素人判断ですが、かってのローマ帝国、近代のイギリスの破綻にも似ているような気がしますが如何でしょうか。
二宮尊徳さんが「道徳のない経済は陳腐である」と言われましたが、今の日本はその道に向かってまっしぐらに突っ走っているような気がします。
最近のニュースに改めて深刻に考えさせられた人は多いのではないでしょうか。
つい数日前の子供二人を置き去りにして死亡させた事件。
胸が詰まってしまいます。
親って何なんだ。
子供って何なのか。
命ってそんなに軽いものなのか。
人はそんなに残虐になれるのか。
社会は?
近隣は?
肉親は?
相手の男は?
コミュニティって存在しないのか。
人々の心はどこまで荒んでいくのか。
相談する人はいなかったのか。
逃げ込めるところは?
そんなに簡単に子供を作っていいのか。
母性は?
書いているだけで涙がこぼれます。
家族だけは最後の砦として、社会は成り立っている筈なのにどこまで崩壊を続けるのか。
せめて、地域は一番心が落ち着いて、助け合い、面倒を見合い、姿を確認し合い、気に掛け合う身近な存在であった筈なのに。
むしろ人との係わりを捨て、あくまでもビジネスライクに過ごす事や「忙しい」の合言葉の元に如何にもそれが最前線で在るかのごとき錯角をもち、人間としての本来の「人との関わりこそ大事」である事を忘れ去ってしまったのではないでしょうか。
煩わしいこと、
どろどろした事、
面倒くさい事、
おせっかいすぎる事、
立ち入りすぎる事、
甘えが過ぎる事、
・
・
・
家族で在ればこその事も存在するものです。
ですが、そこが人間の良さだったり、一旦緩急あったときの最大の防御であったり、支えだったり、勇気の源泉だったりするものです。
子供であれば尚更の事。
この頃の100歳以上の方々の所在や行方の問題にしてもしかり。
母親の行方を30年も知らないとか、引っ越していったきりどうなったか知らないとか。
死んでいるも生きているも分からないとか。
昨年の敬老の日に発表された100歳以上の方が約45,000人。
数字さえも疑ってしまいます。
行政も可笑しくなっているような気がしてなりません。
経済を優先する余り、家族の絆を置き去りにするか、捨て去ろうとしているとしか思えないのです。
政治も可笑しいです。
素人政治でどうするのでしょうか。
もう一度、原点へ立ち戻らないとどうしようもない時代が来るような気がしますが如何でしょうかね。
本来からして、大事にしなくてはいけない事をなおざりにするつけはまもなく来るのではないでしょうか。
素人判断ですが、かってのローマ帝国、近代のイギリスの破綻にも似ているような気がしますが如何でしょうか。
二宮尊徳さんが「道徳のない経済は陳腐である」と言われましたが、今の日本はその道に向かってまっしぐらに突っ走っているような気がします。
Posted by misterkei0918 at
13:20
│Comments(1)
2010年08月05日
思いは差し上げるもの
思いは差し上げるもの
最近、国会などでも良く使われます、「思いやり予算」。
サービス業などの社員教育や、スキルアップセミナーなどでもしきりに言われます、「お客様の立場に立って。お客さまへの思いやりの気持ちを持って・・・・・」
おもてなしの気持ちを醸成するには、自らに思いやりの心が備わっていないといけませんよね。
「人をもてなす」と言う事は、相手の立場に立つとか、痒い所にも手が届くほどにとか、心地いい印象を植え付けるとか、とりなすとか言う事。
もてなすを漢字にすると「持て成す」。
気持ちの伴っていないおもてなしや思いやりは、嫌なものです。
ただ、杓子定規(しゃくしじょうぎ)にされているようで、笑顔に歪が見えたり、なんとなくビジネスライクであったりすると人は敏感に感じるものです。
そうなると逆効果ですよね。
却って釈然としなかったり、鼻についたり、わざとらしい行動や態度にお客様は目ざとくなってしまいます。
思いやりは漢字で「思い遣り」。
昔、遣唐使を中国へ遣わしたことは歴史で学びました。
西暦630年くらいから派遣され始め、唐時代の国際情勢や大陸文化を学ぶために約600名もの人々が派遣されたようです。
893年菅原道真は中止するまで、約260年に亘って行われており、往復に2、3年を掛けていたらしいとの事。
遣唐使の「遣」は、行かせる、差し向ける、つかわす、与える・・・・・などの意味で使われます。
そんな意味合いで「思い遣り」を解釈すると、自らの思いを一方的に上げるとか、与えるとか強制的なニュアンスを感じてしまいます。
子育てで言えば、溺愛などはその類(たぐい)ではないでしょうk。
子育てで最も困った事が溺愛。
放任よりも!!
でも私どもが日常的に使っている思いやりは異なっていますよね。
また異なっていないと困ります。
「自分の素直な気持ちやわだかまりのない無垢な気持ちを差し上げる」。
これが私どもが日常的に言う「思いやり」だと思うのです。
思いは「差し上げるもの」。
「やる」だとか「与える」とか、そんな一方的、頭ごなし的なものではないということを認識していたほうが良さそうです。
最高なのは笑顔が添えられた「思いやり」はそれこそ「最高」と叫びたくなります。
今日もそんな「思いやり」に出会えると嬉しいですね。
それには、こちらの受け入れ態勢も、チャンとしないといけませんよね。
最近、国会などでも良く使われます、「思いやり予算」。
サービス業などの社員教育や、スキルアップセミナーなどでもしきりに言われます、「お客様の立場に立って。お客さまへの思いやりの気持ちを持って・・・・・」
おもてなしの気持ちを醸成するには、自らに思いやりの心が備わっていないといけませんよね。
「人をもてなす」と言う事は、相手の立場に立つとか、痒い所にも手が届くほどにとか、心地いい印象を植え付けるとか、とりなすとか言う事。
もてなすを漢字にすると「持て成す」。
気持ちの伴っていないおもてなしや思いやりは、嫌なものです。
ただ、杓子定規(しゃくしじょうぎ)にされているようで、笑顔に歪が見えたり、なんとなくビジネスライクであったりすると人は敏感に感じるものです。
そうなると逆効果ですよね。
却って釈然としなかったり、鼻についたり、わざとらしい行動や態度にお客様は目ざとくなってしまいます。
思いやりは漢字で「思い遣り」。
昔、遣唐使を中国へ遣わしたことは歴史で学びました。
西暦630年くらいから派遣され始め、唐時代の国際情勢や大陸文化を学ぶために約600名もの人々が派遣されたようです。
893年菅原道真は中止するまで、約260年に亘って行われており、往復に2、3年を掛けていたらしいとの事。
遣唐使の「遣」は、行かせる、差し向ける、つかわす、与える・・・・・などの意味で使われます。
そんな意味合いで「思い遣り」を解釈すると、自らの思いを一方的に上げるとか、与えるとか強制的なニュアンスを感じてしまいます。
子育てで言えば、溺愛などはその類(たぐい)ではないでしょうk。
子育てで最も困った事が溺愛。
放任よりも!!
でも私どもが日常的に使っている思いやりは異なっていますよね。
また異なっていないと困ります。
「自分の素直な気持ちやわだかまりのない無垢な気持ちを差し上げる」。
これが私どもが日常的に言う「思いやり」だと思うのです。
思いは「差し上げるもの」。
「やる」だとか「与える」とか、そんな一方的、頭ごなし的なものではないということを認識していたほうが良さそうです。
最高なのは笑顔が添えられた「思いやり」はそれこそ「最高」と叫びたくなります。
今日もそんな「思いやり」に出会えると嬉しいですね。
それには、こちらの受け入れ態勢も、チャンとしないといけませんよね。
Posted by misterkei0918 at
09:34
│Comments(0)
2010年08月04日
出来れば断らないほうが良さそう
出来れば断らないほうが良さそう
人生は色んなところで断る場面が出現します。
顕著なところでは、お見合いを断る、
就職を断る・・・・・。
断る相手や内容によっては意を決しないと断れない事も多いものです。
食事を断るとか、会議の出席を断る事もありますが、そんなに勇気のいる事でもないですよね。
幾らか気は引けますが。
断るにも色んな計算をしてしまいますよね。
相手がどのように思うかとか、結果がどうなのかとか、今後に影響が及んでこないのかとか。
日常的に色んな会議や集まりに出ます。
色んなお願いがいつも付き纏います。
司会をしてください。
挨拶をお願いします。
乾杯を。
出来ればゆっくり参加したいのが本音ですが、実は何事も経験。
人からお願いをされると言う事は、出来ないと思うから頼むのでもありませんし、恥をかかそうとか、笑いものにしようとか、増してや陥れようなどと言う不届きな考えでお願いをする事は通常は考えられませんよね。
そもそも、そんな思いで人に頼みごとをする事はありません。
だって、頼む本人が困る事であり、恥をかくことですから。
何事も大きな経験です。
それを断って、のんびり構えていた人と、心配はしながらも何とか無難にこなしていく人。
回数が重なるととんでもない差になって現れるものです。
所詮、乗り越えられるお願いしか殆どは来ないのです。
最初から、とんでもない事など普段は来る訳がありませんし、来た時はその時。
やってみたらいいのです。
最初から自信のある人などいませんし、誰でも最初は始めてだし、大変だったんです。
何もしないでいるのか、何か少しでもお役に立てることに精を出すのか。
長い人生を考えてみたら、経験の積み重ねは尊いものです。
「やるか、やらないか、断るか」
一つの経験が次の高いハードルを飛び越える勇気を叡智を与えてくれます。
チャンスロス!!
一つに機会を逃すと次は廻って来ないかも知れません。
それこそ怖い事です。
人生は色んなところで断る場面が出現します。
顕著なところでは、お見合いを断る、
就職を断る・・・・・。
断る相手や内容によっては意を決しないと断れない事も多いものです。
食事を断るとか、会議の出席を断る事もありますが、そんなに勇気のいる事でもないですよね。
幾らか気は引けますが。
断るにも色んな計算をしてしまいますよね。
相手がどのように思うかとか、結果がどうなのかとか、今後に影響が及んでこないのかとか。
日常的に色んな会議や集まりに出ます。
色んなお願いがいつも付き纏います。
司会をしてください。
挨拶をお願いします。
乾杯を。
出来ればゆっくり参加したいのが本音ですが、実は何事も経験。
人からお願いをされると言う事は、出来ないと思うから頼むのでもありませんし、恥をかかそうとか、笑いものにしようとか、増してや陥れようなどと言う不届きな考えでお願いをする事は通常は考えられませんよね。
そもそも、そんな思いで人に頼みごとをする事はありません。
だって、頼む本人が困る事であり、恥をかくことですから。
何事も大きな経験です。
それを断って、のんびり構えていた人と、心配はしながらも何とか無難にこなしていく人。
回数が重なるととんでもない差になって現れるものです。
所詮、乗り越えられるお願いしか殆どは来ないのです。
最初から、とんでもない事など普段は来る訳がありませんし、来た時はその時。
やってみたらいいのです。
最初から自信のある人などいませんし、誰でも最初は始めてだし、大変だったんです。
何もしないでいるのか、何か少しでもお役に立てることに精を出すのか。
長い人生を考えてみたら、経験の積み重ねは尊いものです。
「やるか、やらないか、断るか」
一つの経験が次の高いハードルを飛び越える勇気を叡智を与えてくれます。
チャンスロス!!
一つに機会を逃すと次は廻って来ないかも知れません。
それこそ怖い事です。
Posted by misterkei0918 at
15:55
│Comments(0)
2010年08月03日
右か左、どうしてそうなのか
右か左、どうしてそうなのか
思想信条や宗教については、チャンと構えて会話をしないといけませんよね。
特に日本の場合は。
本来は、避けて通れない部分ですが日本人同士はついタブーとして避けてしまいます。
そういう意味ではまだ未成熟な国なのでしょうか。
或いは韓国の出身の作家の方が書いておられましたが、日本人のその曖昧さがいいとする考えもあります。
何から何まで、煎じ詰めるように縛りだしてしまう世界。
私もあまり好きではありません。
ベールに包まれたような、模糊とした、言い換えれば掴み所のないような国民性。
私自身もご他聞に漏れずそんな人柄のような気がします。
外国の方々が、日本へ来て一番に不思議な所であり、日本人の曖昧とした所がどうも理解できないようですが、2,3年も経験するとそれが素晴らしいと評価するようです。
そこが他人に対する思いやりの表現方法であったり、気配りであったりするものです。
先程の韓国出身の女性作家・呉善花さんの「日本の曖昧力」をお読みくださいませ。
日本人として勇気が湧いてきますし、自信が持てます。
実は今日のタイトルの右か左の話は思想信条の話ではなくて、大阪のエスカレーターでの話です。
私は月に何回か東京へ出ます。
空港や地下鉄にはどうしてもエスカレーターがつき物ですが、皆さんが立ち止まるのは東京だと左側と決まっています。
右に立とうものなら、お叱りを請いますし、顰蹙ものです。
ところが大阪はその全く逆。
いつものように左に立つことが癖になっている私としては一瞬戸惑ってしまいました。
違う行動パターンの理由は何なのでしょうか。
それとは違うでしょうが、
大濠公園をウォーキングしていますと、大勢の人は時計方向とは逆の左周りですが、ほんの一握りの方が時計方向の右回りをされるのです。
ある先輩にどうして右回りですかと聞きましたら「大勢の人が対面で見れるから、知っている人に会える」と答えました。
それも一理です。
心臓が左だから、左回りだとか言う人もいますし、どうなんでしょうかね。
エスカレーターの場合は人為的にそうした事は間違いがありません。
或いは大阪人の東京に対する対抗心の表れと言えば言いすぎでしょうか。
思想信条や宗教については、チャンと構えて会話をしないといけませんよね。
特に日本の場合は。
本来は、避けて通れない部分ですが日本人同士はついタブーとして避けてしまいます。
そういう意味ではまだ未成熟な国なのでしょうか。
或いは韓国の出身の作家の方が書いておられましたが、日本人のその曖昧さがいいとする考えもあります。
何から何まで、煎じ詰めるように縛りだしてしまう世界。
私もあまり好きではありません。
ベールに包まれたような、模糊とした、言い換えれば掴み所のないような国民性。
私自身もご他聞に漏れずそんな人柄のような気がします。
外国の方々が、日本へ来て一番に不思議な所であり、日本人の曖昧とした所がどうも理解できないようですが、2,3年も経験するとそれが素晴らしいと評価するようです。
そこが他人に対する思いやりの表現方法であったり、気配りであったりするものです。
先程の韓国出身の女性作家・呉善花さんの「日本の曖昧力」をお読みくださいませ。
日本人として勇気が湧いてきますし、自信が持てます。
実は今日のタイトルの右か左の話は思想信条の話ではなくて、大阪のエスカレーターでの話です。
私は月に何回か東京へ出ます。
空港や地下鉄にはどうしてもエスカレーターがつき物ですが、皆さんが立ち止まるのは東京だと左側と決まっています。
右に立とうものなら、お叱りを請いますし、顰蹙ものです。
ところが大阪はその全く逆。
いつものように左に立つことが癖になっている私としては一瞬戸惑ってしまいました。
違う行動パターンの理由は何なのでしょうか。
それとは違うでしょうが、
大濠公園をウォーキングしていますと、大勢の人は時計方向とは逆の左周りですが、ほんの一握りの方が時計方向の右回りをされるのです。
ある先輩にどうして右回りですかと聞きましたら「大勢の人が対面で見れるから、知っている人に会える」と答えました。
それも一理です。
心臓が左だから、左回りだとか言う人もいますし、どうなんでしょうかね。
エスカレーターの場合は人為的にそうした事は間違いがありません。
或いは大阪人の東京に対する対抗心の表れと言えば言いすぎでしょうか。
Posted by misterkei0918 at
15:53
│Comments(0)